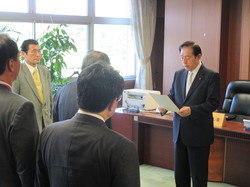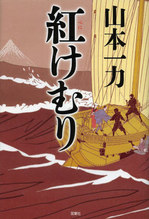10月18日、19日の土日、北海道に行き、要請・懇談・視察等を行いました。
18日は札幌――。道内の商工会議所連合会や経済連合会の代表、建設業、トラック、現場の職人さんをかかえる建専連、そして最も注目されている観光協会の代表から現状の報告、要請を受けました。北海道はこの2年、観光の伸びはめざましいものがあります。外国人観光客も急増し、WiFiや免税をはじめ、対応にかなり力を注いできました。農産物、水産物も日本の大きな柱です。自然環境の厳しいなかでの輸送のための道路整備、札幌までの新幹線、港湾整備などの要望を受けました。
18日の夜には日本最東端の道東に移動し(17時半にはもう真っ暗でした)、根室市長、羅臼や別海の町長、標津町、中標津町の代表、商工会議所の方々と懇談をしました。国交大臣がこの地に来るのは初めてということで、要望が相次ぎました。酪農、水産物が圧倒的で、道路や港湾整備について水揚げしても輸送ができないこともあるという切実な声が寄せられました。
19日は現場に出ました。国境最前線で領海警備をしている海上保安庁の状況を巡視船から視察、条件の厳しいなかで強い意志で働く職員を激励。JR北海道花咲線厚床を訪問、寒冷・軟弱地盤での保安状況を視察。別海町では最先端の搾乳機械を使う大規模酪農を視察、さらに酪農家18戸分の飼料の調整・配送の一括実施をする配合飼料供給施設を訪れました。
北海道のポテンシャルはきわめて大です。発展・振興に力を入れます。
10月17日、JR東海が2027年に開業を目指しているリニア中央新幹線東京(品川)~名古屋間の着工を認可しました。
リニア中央新幹線は最高時速500kmを超える速度で走行し、東京(品川)と名古屋間をわずか40分、更には大阪までを1時間強で結び、国民生活、経済活動にも強い影響を与える重要な事業です。さらに、超電導技術の高速鉄道への導入という世界に類を見ない先進的な技術は、我が国の高速鉄道の技術水準の高さを改めて世界に示すことになります。50年前の新幹線が「夢の超特急」といわれたように、再び日本に自信と希望をもたらすことになると思います。
その一方で、トンネルの掘削に伴う建設発生土が多いことや、その運搬に伴う地域住民の生活環境や自然環境への影響、事業に伴う水環境や生態系への影響など、多岐にわたる分野での影響が懸念されています。また、南アルプストンネルなど、難易度の高い工事も想定されています。
私は、認可に際し、JR東海に対し、地元住民などへの丁寧な説明を通じた地域の理解と協力を得るなど、事業の安全・円滑な推進に必要な措置を求めました。
大事な事業だけに、しっかりとJR東海を指導・監督していきたいと思います。
そして午後は、墨田区の下水道老朽化対策工事の現場を視察しました。東京都の下水道は大正時代から整備が進められ、高度成長期の1960年代から90年代にかけて急速に整備が進みました。それから約50年が経過し、老朽化対策が必要な時を迎えています。
今日見た現場では、SPR工法という世界一の技術を使って工事を実施中。この工法は、下水道をそのまま使いながら管の中に樹脂を巻き付けて行う画期的なもので、工事の大幅なスピードアップとコスト削減が可能です。
日本の技術のすばらしさ、老朽化対策の必要性、見えないところで黙々と働いている人たちの力を実感しました。
師父とは武智鉄二。「私の前に立ちはだかった相手は武智鉄二という、変わりすぎるほど変わった人物だった。・・・・・・通りいっぺんの道徳や、権威や、規範や、体制を蹴散らしながら歩き続けたこの人物を、私は一生の師と仰いだ」「武智師と私を結びつけたのは歌舞伎を主とした日本の伝統文化だった」――。
「『あんたはそうやって人に余計な気ィばっかりつかっているから疲れるんだっ』 文字通り雷電に打たれたごとく全身が硬直して棒立ちとなり、私は真っ赤に熾った師の顔を呆然と見ていた。・・・・・・そして本気の怒りは、長い年月をかけて私の人格をつるんと覆っていた硬質の膜のようなものを、みごとに突き破ったのである」――。まさに自己そのものをぶっ壊してくれるのが師だと思う。
武智鉄二、木下順二、中村扇雀。松井さんはこの3人をはじめとして、多くの人に恵まれ、歌舞伎などの芸術の世界でもまれにもまれ、格闘してきたことを、静かに語り続けている。師弟愛に生きるということは中道を歩むということだ。だから格闘しても根本的には、迷いがない。私とは全く異次元の話に圧倒されるが、武智鉄二の父・正次郎が京大土木工学科の先輩であったり、芸能好きのゆえの接点も時折り、交差する。
「武智鉄二との出会いをひと口で締めくくるのは難しいが、世間を相手に戦い続けてきた人は、他人様にどう思われようが、自分の殻を打ち破って全開で生きることの必要を私に説いたのだった」――師父の遺言だ。
花と緑があふれるまちづくりを進めよう――10月10日、有楽町の駅前広場で「都市緑化キャンペーン2014」のオープニングイベントを開催しました。10月は都市緑化月間。緑化への関心を高めようと、会場に並んだ多くの方々にマリーゴールド、リンドウ、ガーベラなど色とりどりの花の鉢を次々とお配りしました。
植物の緑は人に安らぎを与え、景観や環境の観点から大きな役割を果たします。防災・減災にも効果があり、私も「緑の防潮堤」の植樹を昨年6月に宮城県岩沼市で行いました。都市部でも、密集市街地での緑化は火災の延焼を防ぐ上で大きな効果があります。
緑への関心を高め、自然がもつ力を活かした「緑の防災・減災」を進めます。
また午前中は、建設業をテーマとした作文コンクールの表彰式を行い、国土交通大臣賞の受賞者(建設業で働く技術者2名と、これから建設業を目指している高校生2名)と懇談しました。
「若者が建設業に定着できるよう魅力を伝えたい」「土木は目に見えない部分でも社会を支えている。やりがいがある」「宮大工だった祖父を超える技術者になりたい」「職人になる意志を強く持って勉強したい」――建設業の将来を担う力強い意見が続きました。
現場を支える若い技能人材を増やして活躍してもらえるよう、しっかり取り組みます。