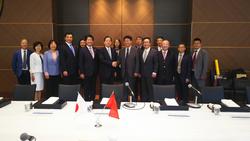「近江商人、温州企業、トヨタ、長期繁栄の秘密」が副題。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」の近江商人。小さな領地から飛び出し、多店舗展開、店員は信頼できる同郷人、相互扶助と共存共栄、社会貢献で広げていく。世界最強の田舎商人集団で欧州に一大コミュニティーとネットワークをつくる温州人。日用消費財に狙いを定め、加工業と卸・小売業で栄える強靭な相互扶助システムをつくって繁栄を築く。そして高い競争力を維持するトヨタのサプライチェーン。
「近江商人、温州企業、トヨタ、長期繁栄の秘密」が副題。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」の近江商人。小さな領地から飛び出し、多店舗展開、店員は信頼できる同郷人、相互扶助と共存共栄、社会貢献で広げていく。世界最強の田舎商人集団で欧州に一大コミュニティーとネットワークをつくる温州人。日用消費財に狙いを定め、加工業と卸・小売業で栄える強靭な相互扶助システムをつくって繁栄を築く。そして高い競争力を維持するトヨタのサプライチェーン。
そこにあるのは、同じコミュニティーのメンバー間で共有される「同一尺度の信頼」と、そこから派生し協力し合う「準紐帯」。長期にわたる参加者同士の相互作用によって、強靭な企業コミュニティーが進化していく。その目に見えない共通財(関係資本)、「コミュニティー・キャピタル」の重要性を指摘する。近江商人も温州人も時代の変化のなかで、凝集性の負の側面にもさらされ、血縁・地縁を超える新たな信頼関係の構築が飛躍のためには不可欠となる。トヨタのサプライチェーンも、アイシン火災事故や東日本大震災時のルネサス那珂工場の復旧等で、その信頼・準紐帯はより強化されることになる。企業等の長期繁栄のための「コミュニティー・キャピタル論」が具体的に展開される。
福島県を元気に、会津に活力を――。7日、福島県の会津に行き、会津若松市の室井照平市長、佐藤一栄喜多方市議会議長、下郷町の星學町長ら関係17市町村の首長、各議会の議長と要請・懇談、多くの要望を受けました。また、会津縦貫南道路の建設現場や茅葺屋根の民家が建ち並ぶ大内宿を視察しました。これには真山祐一前衆議院議員、甚野源次郎公明党県本部議長、会津若松市の土屋隆、樋川誠、大山享子の各市議らが参加しました。
とくに要請を受けたのは会津縦貫南道路(会津若松市と栃木県日光市を結ぶ)の建設促進。これが完成すると年間1200万人となる日光への観光客と歴史と文化の会津若松市や大内宿が直結、会津は元気になります。それとともに「いまだ続く農産物の風評被害の払拭を支援してほしい」「只見線の復活に感謝」「磐越道の四車線化を」「小中学校の冷房施設促進」などの要望を受けました。対応に注力します。
 結婚して20年、52歳の加能鉄平は、たまたま妻にかかってきた弁護士からの電話に出て、驚愕の事実を知る。妻・夏代が伯母から34億円もの遺産を相続し、それが現在総額で48億円にもなっているというのだ。リストラ、左遷、そして今、身内の会社でも閑職に追いやられていた鉄平にとって、衝撃であるとともに、人生そのものを揺さぶられることになる。「なぜ妻はこれを隠し、手をつけないできたのか」――。それだけでなく、別居する長女の妊娠、長男の同棲等、鉄平の知らない秘密が次々に明らかになる。加えて大爆発事故を起こして加速する社内抗争。「俺だけが知らない。どいつもこいつも勝手ばかりして」との心の空洞は「俺はいったい何をしようとしているのか」へと人生そのものの根源的問いかけへと進んでいく。
結婚して20年、52歳の加能鉄平は、たまたま妻にかかってきた弁護士からの電話に出て、驚愕の事実を知る。妻・夏代が伯母から34億円もの遺産を相続し、それが現在総額で48億円にもなっているというのだ。リストラ、左遷、そして今、身内の会社でも閑職に追いやられていた鉄平にとって、衝撃であるとともに、人生そのものを揺さぶられることになる。「なぜ妻はこれを隠し、手をつけないできたのか」――。それだけでなく、別居する長女の妊娠、長男の同棲等、鉄平の知らない秘密が次々に明らかになる。加えて大爆発事故を起こして加速する社内抗争。「俺だけが知らない。どいつもこいつも勝手ばかりして」との心の空洞は「俺はいったい何をしようとしているのか」へと人生そのものの根源的問いかけへと進んでいく。
「人生」「夫婦」「男女」「家族」「愛」「信頼」・・・・・・。大事件、大災害、生死の極みにはじめて顕わになる人間のコアー・核心。幸福感における男の「煩悩即菩提」、女の「生死即涅槃」の差異を浮かび上がらせている。
 たしかに江戸の町は、賑やかで粋で、色彩鮮やかで、自由で"とっぽい"。商人も職人も、こんなものを売り買いしていたのか、それで商売が成り立っていたのか。江戸の季節や祭りとのかかわり、風習などがのびやかにに描かれて楽しい。
たしかに江戸の町は、賑やかで粋で、色彩鮮やかで、自由で"とっぽい"。商人も職人も、こんなものを売り買いしていたのか、それで商売が成り立っていたのか。江戸の季節や祭りとのかかわり、風習などがのびやかにに描かれて楽しい。
8つの短編よりなっているが、「ぞっこん(看板書き栄次郎の筆)」「千両役者(贔屓客の心)」「晴れ湯(湯場のお晴)」「莫連あやめ(義姉の正体とは)」「福袋(当時からあったのか大食い大会)」「暮れ花火(枕絵が昔の恋を照らす)」「後の祭(神田祭の祭掛の大変さ)」「ひってん(卯吉と寅次が山ほどの櫛を拾うことに)」――。
歌丸さんらにやってもらったかのような"読む落語"となっている。江戸風情があふれる。