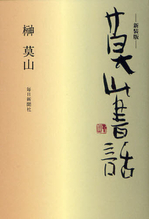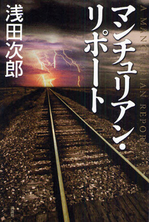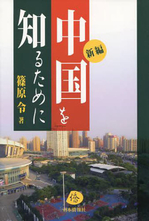 前著「友をえらばば中国人」も素晴らしかったが、本書はさらにいい。
前著「友をえらばば中国人」も素晴らしかったが、本書はさらにいい。
一つは、「中国人とは、どういう人たちか」「どういう思考法に立つか」を歴史、文化から浮き彫りにしてくれている。私は常々、日本人と中国人は同じような姿顔立ちをしている、だからわかりあっているはずだ、という大いなる錯覚が、事あるごとに両国関係を難しいものにしてきていると思っている。王敏法政大教授の「中国人の愛国心」「意の文化と情の文化」「ほんとうは日本に憧れる中国人(日本への愛憎共存)」だ。王敏さんは日本に住んで異文化を感じて書き、篠原さんは中国全土を歩いてこの書を書いている。
もう一つは、日中韓のナショナリズムをどう越えて和解と共生の道を歩むかということだ。篠原さんは、物質的文明を越えよ、精神性の文化が中国にも日本にもあるではないか、と嘆きながらも叫んでいる。松本健一さんが「日・中・韓のナショナリズム」のなかで、両国とも国内矛盾を外敵をつくって吐き出すのではなく東アジア共同体への道を探れといっているとおりだ。
 「ファンサービスが足りない」
「ファンサービスが足りない」
「取材も受けない」
「媚びない、はしゃがない、人目を気にしない」
「嫌われても筋を通す」
「誤解されても言い訳はしない」
――批判されようが、「俺は勝つことだけが唯一の仕事」「自分は人気商売じゃなくて"数字商売"」と徹して動く。 不気味さが武器の落合。超合理主義の落合。
他人を気にし、テレビや雑誌でいうことをうのみにし(食でさえも自分で判断できなくなってしまった)、幼稚化する日本人。文化や政治までもどんどん大衆迎合になって、独創性や創造力が低下する一方の二流国に転落するたむろする日本。
これを打開するのが「落合力」、落合の生き方だ。そう、熱烈な長嶋信者・テリー伊藤さんが寡黙にして勝負して勝つ落合を絶賛する。野球を超えて混迷日本の打開がテーマになっている。
 宇宙の解明は、全く新しい段階に突入したようである。衝撃的だ。
宇宙の解明は、全く新しい段階に突入したようである。衝撃的だ。
宇宙は何でできているのか――長い間、科学者達が挑んできた課題。今は高性能の望遠鏡のおかげで、はるか遠く、何億光年という光の星まで観測できる。
「アインシュタインの望遠鏡」というのは、これらの望遠鏡とは全く異なり、一般相対性理論――空間と時間はあらゆる質量によって曲げられる――をもとに、「重力」がつくる望遠鏡である。
いわば、宇宙そのものを望遠鏡として使うのである。この重力レンズによって視野の限界は打ち破られ、かつて見ることのできなかった宇宙の暗い領域が明らかになる。
10年ほど前、宇宙物理学は、ダークマター、ダークエネルギーという存在を発見した。