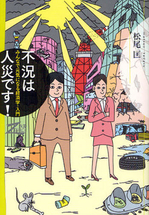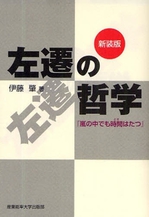 78年の初版だから30年もたつ。新装版が今年出たということでいただいて、本当に久し振りに伊藤肇さんの哲学に出会った。
78年の初版だから30年もたつ。新装版が今年出たということでいただいて、本当に久し振りに伊藤肇さんの哲学に出会った。
「闘病と浪人と投獄の三つの段階を通って実業人として完成する」という松永安左エ門さんの名言を受け、苦難・風雪のなかで人間が鍛えられるという書だ。
「自分の生のみすぼらしさ、つたなさがあわれでならなかった」という川端康成の言。
「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候。死ぬる時節には死ぬるがよく候」「縁ニ随ッテシバラク従容ス」という良寛の言。
「あがり(相場)さがりの十年間の辛抱のできる人が、すなわち大豪傑だ」「ヤセ我慢を張り通せ」という勝海舟や松永安左エ門の言。
「風車 風が吹くまで 昼寝かな」の広田弘毅。「今が最悪だといえるときはまだ最悪ではない」というシェークスピア。
この本の副題には「嵐の中でも時間はたつ」とある。私は、究極の人間哲学は師弟だと思う。
太田あきひろです。
スポーツの秋。11日、雲一つない青空のもと、北区民体育祭の開会式、幼稚園などの運動会が盛大に行われましたが、日本のトップアスリートをバックアップするナショナルトレーニングセンターでも「体育の日スポーツ祭り2010」が行われました。
このナショナルトレーニングセンターは、北区西が丘にありますが、私自身大きく力を入れてきました。オリンピックや各世界大会ともなると「メダルだ」「優勝だ」と盛んにいいますが、日本には他国のような国の施設がない状況で苦労してきました。
ここ10数年、やっと充実・強化され、アテネオリンピック37個のメダルをはじめ、結果が如実に出ています。スポーツの振興は若者を育てることの重要な柱です。
「冬のナショナルトレーニングセンター」が無くて、浅田真央選手たちもさぞ苦労していると思います。更に力を注ぐ決意です。