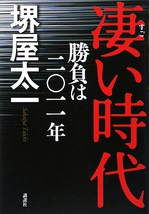 今こそ改革、そしてこの未曾有の1年の不況を乗り越え新しいスタートが切られるかどうか、そこに凄い時代が始まるかどうかのカギがあるという。堺屋さんの主張の全体の底流には「すべての根源は知価革命にある」が基調音のように流れている。知価革命の日米などの国々と、「物財の豊かさ」を追う近代工業社会への国々との凸凹の構造、しかもそれが水平分業ではなく、工程分業となっていることを示している。
今こそ改革、そしてこの未曾有の1年の不況を乗り越え新しいスタートが切られるかどうか、そこに凄い時代が始まるかどうかのカギがあるという。堺屋さんの主張の全体の底流には「すべての根源は知価革命にある」が基調音のように流れている。知価革命の日米などの国々と、「物財の豊かさ」を追う近代工業社会への国々との凸凹の構造、しかもそれが水平分業ではなく、工程分業となっていることを示している。
国際金融・ペーパーマネー体制(失敗を繰り返さない為には規制強化ではなく、金融に節度と理性、モノとカネの自由・迅速な流動を)、小泉改革(誤りではなく、賛成だが、ケインズ政策の否定と新たな産業と社会環境を生みだす成長戦略への手が打たれなかった)、知価革命(これからは規制・統制などの官僚主導とモノ造り依存を捨て、医療・介護・教育・保育・歩いて暮らせる街づくりなどの都市運営・農業などに力を注ぐことが大切)、過剰消費も知価革命が背景、都市の構造もコミュニティのあり方も、家族状況も、近代工業社会と知価社会では決定的に変化していること・・・・・・・。
毎年のように堺屋さんは指摘し続けているが、とくに本書には力業を感ずる。
私も「勝負は2011年」、この2,3年がとくに大事だと思う。
太田あきひろです。
12月5日の全国代表者協議会において、参院選比例代表の公認予定候補の決定をいただきました。公明チーム3000の最前線で勝利めざして、一生懸命、誠心誠意、動き抜き、頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。
師走のあわただしさが街を突っ切るような日々ですが、定例会、町会等の諸行事、各種忘年会(望年会)など走り抜いています。先週日曜日は町会等の餅つき大会9カ所や、イルミネーション点灯式2カ所など、18会合に出るなど一生懸命、とにかく現場を走っています。
いま大事なのは景気・経済対策。「とにかく、こんなひどい状況は仕事をして初めてだ(中小企業や飲食業者)」「補正予算はひどいものだ。いったい民主党、鳩山政権はいつになったら景気対策をやるんですかね(シンクタンクに所属する権威あるエコノミスト)」「雇用状況は最悪だ(これは全ての人が言います)」など、悲鳴と怒りが噴きあがってきました。
 山岡鐵舟は勝海舟、高橋泥舟とともに「幕末三舟」といわれるが、江戸城無血開城の立役者であり、明治天皇の侍従、剣・禅・書の達人だ。
山岡鐵舟は勝海舟、高橋泥舟とともに「幕末三舟」といわれるが、江戸城無血開城の立役者であり、明治天皇の侍従、剣・禅・書の達人だ。
その背後には、勝海舟あり、西郷隆盛あり、まさに「山岡は明鏡のごとく一点の私ももたなかったよ」(勝海舟)、「命もいらぬ、名もいらぬ、金もいらぬ、なんとも始末に困る人」(西郷隆盛)だったという。
半藤一利さんの「幕末史」にあるが、新しい国家をつくる以外に国家の生きる道はなかったあの幕末。統一の基軸のないまま、結局は攘夷の嵐、尊王攘夷運動が尊皇倒幕になり、暴力的権力闘争になってしまったなかで、勝海舟はそれを越えていた。
あの決定的瞬間に山岡鐵舟を頼みとするのだから、存在感の凄みと達人の境地はいかばかりであったろうか
 孫子は「敵の情を知らざる者は、不仁の至りなり。・・・・・・勝の主に非ざるなり」という。日本には戦略もなく、しかも情報の分野を最も軽視してきた。
孫子は「敵の情を知らざる者は、不仁の至りなり。・・・・・・勝の主に非ざるなり」という。日本には戦略もなく、しかも情報の分野を最も軽視してきた。
孫崎さんは、「そもそも今日日本では、安全保障や外交で、"勝利を得るには・・・・・・"の発想すらないのではないか」という。そして「情報に金を惜しむな、人を大事にせよ」と。
「イラン・イラク戦争(米国の変化)」「ベルリンの壁の崩壊(ハンガリーの動き)」「ニクソン訪中(ベトナム関連)」「フォーリンアフェアーズ誌」「9・11同時多発テロ(情報はあったがブッシュ動かず)」「米国情報機関の対日工作」「評価されていた日本の湾岸資金協力」等々。
具体的な事件について、なぜ予測ができたり、できなかったか、見逃したのか。――インテリジェンスとは何か(行動のための情報)を示している。
太田あきひろです。
赤羽東口、西口のイルミネーション点灯式が29日行なわれ、いよいよ今年も師走へのスタートです。昨日は北区西が丘サッカー場で高校サッカーの東京の決勝戦。しかも北区の成立学園と隣接する板橋区の帝京高校の戦いで、これまた正月の全国大会へのスタートです。
年末を迎える今、大事なのは景気・経済。鳩山不況、民主不況ということがいわれるように、執行予定であった第1次補正予算から3兆円削る逆噴射政策(全世界の財政出動のなかで日本だけ逆噴射)で、景気が「10月から急に仕事がなくなった」というように冷え込んでしまっています。
円高についても対処がゼロでは大変なことになります。経済政策の誤りを正さなくてはなりません。

