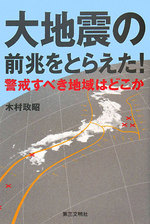太田あきひろです。
洞爺湖サミットの7月7日のクールアース・デー、そして、その日のライトダウン(消灯)。4月初頭から公明党が青年局を中心に動き、私も青年局の代表と共に福田総理に直接話をし、決定をみたものですが、東京タワー、レインボーブリッジ、名古屋のテレビ塔、通天閣をはじめ夜8時から10時までライトダウンを決めたのは全国で約7万施設に拡大しています。国会もライトダウンが決まりました。
地方議会でも公明党が推進し、次々と決定しています。地球温暖化対策は、いまや最も重要な安全保障であり、文明の転換を人類の意志として行う大作業です。しっかり頑張ります。
太田あきひろです。
昨日(6月30日)、潘基文国連事務総長と会見いたしました。短時間でしたが、世界的な原油の高騰や穀物価格の高騰に、国際的にどう対応するか――まさに台風やハリケーンのような投機マネー等の猛威に対して、「国連として、是非力を発揮してほしい」と強く要請しました。
潘基文事務総長からは自らサウジアラビアに原油の増産を働きかけたことや、国連機関で、更に努力していくとの話がありました。また私は地球環境問題への日本の取り組みも説明し、あわせて「国連の機関を沖縄や広島・長崎に」と、公明党の主張も述べ、協力を求めました。
潘基文事務総長とは2度目の会見ですが、穏やかで、芯の強さがにじみ出て、かみあったいい会談ができました。
グローバリゼーションの今、国連の役割りはますます大きくなっています。
太田あきひろです。
原油高と穀物などの異常な高騰が、運送費や漁業、そして生活や福祉現場までを直撃しています。原因は、サブプライムローン問題に始まる世界の投機マネーが台風やハリケーンのように市場を荒らし回っていることにあります。国際的な問題だけに、世界の諸会合で一致した対応をとる努力がまず不可欠。私は関係大臣に言い続けています。併せて、日本での対応策が急務です。
公明党が原油高対策について、一昨日、政府に申し入れを行い、「福祉ガソリンをはじめとする生活支援策」「高速料金の更なる引き下げ」などを主張。自民党よりもはるかに踏み込んだ対策で、本日26日、政府として決定した原油高対策について、関係者からも「公明党の主張が目玉ですね」と言われました。今後も生活者の目線での政策実現へ頑張ってまいります。