 じつに感動的だ。坂本先生はよく歩いて会社をみている。「顧客満足」とか「株主満足」というが、ここで紹介されている中小企業5社が、躍動しているのは「社員の幸福」を社長がめざし、その社員の喜び、真心が、下請け企業や地域の喜びへと連なり、それが増収・増益・発展をもたらしているということだ。
じつに感動的だ。坂本先生はよく歩いて会社をみている。「顧客満足」とか「株主満足」というが、ここで紹介されている中小企業5社が、躍動しているのは「社員の幸福」を社長がめざし、その社員の喜び、真心が、下請け企業や地域の喜びへと連なり、それが増収・増益・発展をもたらしているということだ。
環境が悪い(景気や政策が悪い、業種・業態が悪い、規模が小さい、ロケーションが悪い、大企業・大型店が悪い)という言い訳が全くない。
「杉山フルーツ」などは、悪戦苦闘の全国お決まりのさびれた商店街にあるという。「日本理化学工業」「伊那食品工業」「中村ブレイス」「柳月」――いずれも素晴らしい。「幸福」ということは、あくまで人、人財ということだ。
お客様から愛される、人と人との心を結ぶ――。
自分の問題として大いに考えさせられた。
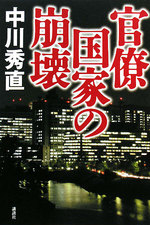 政治家の本は、読書録には書かない。野呂田芳成著「思い切なれば必ず遂ぐるなり」以外は、そうしてきた。ただ、このいわゆる上げ潮路線といわれる中川さんの新刊と消費税についても堂々と提起する与謝野馨著「堂々たる政治」は、党内にもこの4、5月の必読書だといってきた。私自身、「家計を元気に、国に勢いを」といい続けており、当然、両書は注目してきた。与謝野さんの本を読めば、それが単なる財政再建路線でないことはよくわかる。
政治家の本は、読書録には書かない。野呂田芳成著「思い切なれば必ず遂ぐるなり」以外は、そうしてきた。ただ、このいわゆる上げ潮路線といわれる中川さんの新刊と消費税についても堂々と提起する与謝野馨著「堂々たる政治」は、党内にもこの4、5月の必読書だといってきた。私自身、「家計を元気に、国に勢いを」といい続けており、当然、両書は注目してきた。与謝野さんの本を読めば、それが単なる財政再建路線でないことはよくわかる。
「上げ潮路線」と「両輪路線(成長力強化と財政再建)」、そして「日本を滅ぼす"ステルス複合体"(官僚制)批判」と「市場原理主義批判」、さらに「官愚を乗り越える民賢」と「堂々たる政治」――具体的な戦略、戦術をも含めて読ませていただいた。それに加えて、今、「グローバリゼーション」「世界に猛威をふるう金融、コモディティの新しい世界」の構造変化の要素をもっともっと踏まえなくては日本は行き抜けないと思っている。
この数日、何人もの人から「太田さん、公明党の動きが激しいですね」といわれました。5月後半からの2週間、「静かなる革命をしたい」と私にいっていた福田首相の動きが目に見え、そして常に公明党が「政策実現のアクセル」となっていることが、幾つもみられるようです。
5月17日に私は福田首相と3時間の会談。その日のぶら下がり会見で「高齢者を大切にする政策実現を」と訴えました。その後、党内で大きく論議が展開され、今週にも全体像を発表する予定です。
20日、公明党幹部と福田首相と懇談、「学校の耐震化の加速」を提起しましたが、これが政府・与党として大きく前進、いよいよ学校耐震化の補助率を1/2から2/3に上げる法案ができあがります。公明党が常に先頭を走ってきた成果です。
「クラスター弾の全面禁止」に政府が一気にカジを切り、公明の主張(23日には浜四津代表代行等が総理に申入れ)が、総理の決断を促すとの記事が、報道されました。
長寿医療制度の運用・改善では、地方議員の皆さんに呼びかけ、全県の意見を集約、舛添厚労大臣に申入れをしたのが5月28日。これが政府・与党案の軸となって、今、最終段階の詰めの作業が行われています。
アフリカの50か国以上の首脳が来日した「TICAD」。会議自体が歴史に残る成果をあげましたが、私はセネガル、ルワンダ、エリトリア、ケニア、スーダンなどの大統領やマータイ博士等と連続会談をしましたが、福田総理は40か国以上の首脳と会談。すさまじい動きですが、これが6月初頭のローマでの食糧会議、そして7月の洞爺湖サミットに連なることは間違いなく、いよいよ日本が環境、食糧などの重要課題のリーダーシップをとることとなります。
私が常にいい続けてきた消費者庁も大きなヤマ場で30日には中心となっている岸田担当大臣とも話し合いました。「生産者ではなく、生活者、消費者重視の政治・行政に」という福田首相の象徴的なものです。激しい攻防がありますが、消費者庁実現に進んでいます。
そして公務員制度改革。今国会では時間切れともみられていたこの改革法案が、ついに民主党との協議が成立。すでに衆院を通過、会期内成立のメドが立ちました。大きいことです。
「改革実現のトップバッター」、「福田内閣のアクセル役」、として、更に激しく動く決意です。
 長寿の時代。誰でも皆、最後はひとりになる。「家族にみとられないと孤独死でこわい」というが、違うのではないか。今の社会"家族"する期間の方が短くなっており、とくに女性はひとりになる。そのためには、ひとり暮らしのノウハウを準備しておこうと上野さんはいう。
長寿の時代。誰でも皆、最後はひとりになる。「家族にみとられないと孤独死でこわい」というが、違うのではないか。今の社会"家族"する期間の方が短くなっており、とくに女性はひとりになる。そのためには、ひとり暮らしのノウハウを準備しておこうと上野さんはいう。
「不安とは、おそれの対象がなにか、よくわからないときに起きる感情だ」「ニーチェは"見捨てられていることと、孤独とは別のことだ"というが、"孤独死"のほとんどは、孤独とは無関係の短時間の死。
むしろ孤独死か自分の理想の死と、東京監察医の小島原将直さんが講演している」など、ひとりの側、死にゆく側からものをながめ、智慧をはぐくむことを示している。
「後家楽を楽しむ」「"いっしょに暮らそう"は悪魔のささやき」「"ひとりでおさびしいでしょう"は大きなお世話」「家で暮らしたいと家族で暮らしたいは違う」「都会に住むか、地方で暮らすか」「いっしょにごはんを食べる相手はいる?」「老後とカネ、老にガネを生かす」「家族に頼らない・頼れない老後のためにできた介護保険」「ピン・ピン・コロリ主義や予防重視は、いかに介護を受ける状態を避けるか、規格はずれの異物を排除しようとする人間の品質管理思想」「介護される側の心得」など、母のことを思いながら読んだ。


