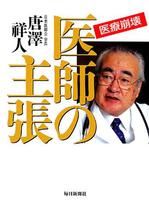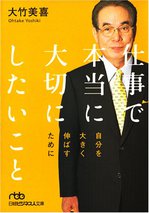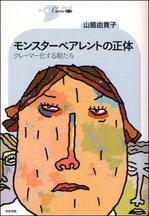 クレーマー化する親たちは、余裕がなく、いっぱいいっぱいで、不満もストレスも不安もたまりにたまっている。
クレーマー化する親たちは、余裕がなく、いっぱいいっぱいで、不満もストレスも不安もたまりにたまっている。
そして不幸を嘆き、少しでも幸せそうな人に鬱積したものをぶちまけたいというマグマがたまっている。しかも、コミュニケーションの減少と不全があり、この国の人間関係は希薄化しているうえに、IT、携帯が仮想空間に拍車をかけている。そのうえ、教師(それは議員も役人も医者も)は、サービスするのが当然という店員扱いをされるという社会の大きな変化がある。
お医者様でも先生でもなく、保護者様、患者様意識はそうしたことからでき上がっている。山脇さんの「教室の悪魔」は攻撃的だったが、この本もまた見事に実態を見せてくれ、解決策を示してくれている。
「幸せになること、自分の力で幸せになるのだ」「人生とは勝ち負けなのだろうか。幸せか幸せではないかではないのだろうか」との締めくくりの言葉はズシッと心に響く。
5日、6日の土日は、各地で大変な人出となった。
天候に恵まれ、桜も踏んばって先週に引き続いて花見ができた。花吹雪も美しかった。舞踊の会も地元でいくつも催された。ソフトボール大会の開会式もあり、始球式で球を投げた。コースはストライクゾーンだったが、残念ながらワンバウンドした。 北区の桜ウォークには2000人もの人が参加して歩いた。諸行事を歩いて顔がヒリヒリするほど焼けたが、懇談も随分できた。
地元・足立では、なんといっても日暮里・舎人ライナーが開通して、地域行事に盛り上がりがある。これが道路特定財源ということを知る人はほとんどいない。都市整備は、地域の活力にとくに不可欠だ。足立が急速度に発展することは間違いない。
北区は歴史も伝統も文化も豊富だ。今、飛鳥山の桜は、上野と並んで東京の名所となっている。王子は吉宗の時代からの伝統があり、あわせて紙をはじめとして明治以来の産業の発生地だ。
先日は赤羽台に縄文と弥生の土器が出て、見てきた。太田道灌の出城も赤羽だ。田端には芥川龍之介などの文人が住み、先日の田端中学校の閉校式では、校歌の作詞がなんと室生犀星で驚いた。貝塚もある。私の住む滝野川はまた美しい土地だった。滝野川ごぼうも名高いし、桜並木のすぐ近くには、近藤勇の墓がある。西が丘には、オリンピックに向けての大拠点、ナショナル・トレーニングセンターがある。アテネ・オリンピック37個のメダルのうち、この地で訓練を受けたものが32個だ。
「家計を元気に」「地域に活力を」そして「国に勢いを」と思い、戦っている。