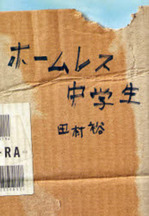日本人の人間関係と言葉は独特だ。「暗黙の了解」「以心伝心」「言わぬが花」「沈黙は金」――そうしたなかで培ってきた伝統は、今の時代に生きるのか、すたれているのか。すたれているから人間関係に悩むのか、時代・社会が変化してあわなくなっているから悩むのか。
日本人の人間関係と言葉は独特だ。「暗黙の了解」「以心伝心」「言わぬが花」「沈黙は金」――そうしたなかで培ってきた伝統は、今の時代に生きるのか、すたれているのか。すたれているから人間関係に悩むのか、時代・社会が変化してあわなくなっているから悩むのか。
川北さんは、「人間関係で、言っていい言葉、言わなくていい言葉――日本の伝統をもう一度見なおしたい」「今、若いビジネスマンの間では、ちょっとしたニュアンスの言葉が理解できない」という。
川北さんは62項目を示しているが、マズローの人間の5つの欲求――
(1)生理的欲求
(2)安全の欲求
(3)所属の欲求
(4)自尊の欲求
(5)自己実現欲求
――のうち第4の自尊欲求のレベル、自分が承認されたい、自分の存在価値を認めてほしい(否定されたくない)段階に日本があるという指摘はそのとおりだと思う。
16日(日)、北区西が丘のナショナル・トレーニングセンター建設工事の視察を区議団とともに行いました。科学の粋を集めたトレーニング施設をということで建設され、これがアテネ・オリンピックの38のメダル量産の原動力となりました。今、さらに拡大する工事が行われています。
来年は北京オリンピック、早く工事を終え、選手強化に走る構えです。私は学生時代、相撲部だったこともあり、スポーツ振興やこの西が丘の国立スポーツ科学センターとナショナル・トレーニングセンターの強化を推進してきただけに予算も含め、さらに力を注ぐ決意です。
またこの日は、地元の幼稚園の音楽祭がありましたが、感心しました。鍵盤ハーモニカで年少さんも年長さんも見事に演奏しました。学力低下が問題となっている今、私はスポーツ・芸術にもっと力を入れることが大事だと思っています。
ちなみに今回の税制改正で、わが党の主張が実って、伝統文化への固定資産税などの優遇措置を実現しました。中小企業の事業承継税制が抜本的に拡充をされたことなどは、公明党の戦いとして良く知られていますが、伝統文化に対しての、今回の画期的な措置はあまり知られていないので、ご報告致します。
 中央集権という後発国的な発展モデルを打破し、新しい「国のかたち」をつくるために、地域主権型道州制を主張する。
中央集権という後発国的な発展モデルを打破し、新しい「国のかたち」をつくるために、地域主権型道州制を主張する。
前者にある画一的、拘束的、不自由、個性を抑圧して、依存心と甘えを助長するこれまでを打ち破る。そして国、道州、基礎的自治体(15から40万人)の3層でいく。道州で税を徴収して国費分担金として国をまかなう。国民も地域も個人も自らの足で立ち、「自主自立」「自己責任を果たす」「個人の正当な努力が報われる」社会をつくる。地域個性を生み出し、国際社会で生き抜いていく道州拠点をつくる――そういった意欲的主張だ。
たしかに世界は動いている。日本を元気にするために、各車にエンジンのある新幹線型の日本にしないとやっていけない。このまま放置すれば、全国では取り返しのつかない高齢化と元気のない地方ばかりになりかねない。相当の智慧とやる気の人材集団が必要だ。それだけに私は、助走が大事だと思う。
原油高騰が大きな問題となり、中小企業や家計に大きな打撃を与えています。
これはアメリカのサブ・プライムローン問題に始まり、投機マネーが原油価格を押し上げているものですが、生活にかかわるだけにこのまま放置はできません。
私は11月12日、首相官邸における政府与党連絡会でも対応を強く求めてきました。
また現場に飛んで実状を調査したり、経済産業省や農林水産省、国土交通省、公正取引委員会にも要請を続けてきました。
昨日も党として町村官房長官を訪ね、原油高騰によってガソリンや灯油などの小売価格が最高値を更新し続け、国民生活や産業に深刻な影響をおよぼしていることを指摘し、「早急に対策を打たねばならない」と訴えました。
具体的には、一般消費者への支援に全力を挙げることを強調し、「寒冷地へ地域政策補助金」「高速料金の引き下げ検討」「運送業に別立て運賃設定」「バイオ燃料推進への税制措置」などを急ぐよう求めました。
今日、私は岩手県の公明党政経セミナーに行きますが、生々しい声を聞いて、安心して灯油を購入できるよう、私の考えを発表することにしています。