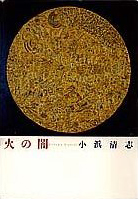週刊朝日の連載「船橋洋一の世界ブリーフィング」の最終本。その時々の論評、分析を5年後に本にすることは大変なことだ。よほど確かな眼をもっていること、そしてしっかり人に会って取材し、考えを総合化して自らの主張をもつことなしにはできるものではない。
週刊朝日の連載「船橋洋一の世界ブリーフィング」の最終本。その時々の論評、分析を5年後に本にすることは大変なことだ。よほど確かな眼をもっていること、そしてしっかり人に会って取材し、考えを総合化して自らの主張をもつことなしにはできるものではない。
世界の動きは速い。日本は遅れ、孤立する。とくに中国、そしてインド、ロシア。この間まさに9・11以後の世界の変化と激動のなかであった。そして特徴ある小泉、ブッシュ。私は西部劇政治と呼んだが、別のプレーヤーは、イラク、アフガニスタン、そしてイスラムの世界(中東だけでなく欧州への移動)とイスラム原理主義、さらに北朝鮮だ。
当然、国と国でなく、民族と宗教による抗争がそこにあり、船橋さんは、そのメガトレンドを如実知見しつつ日本の孤立を懸念する。日本は自ら外へ向かい戦略性をもってソフトパワー戦略を見直し、再構築することだ。福田訪米の日米同盟強化策のなかにその視点があることが、知られていないのは残念だが、大いに後押しし進めたいと思っている。
朝は寒く、昼の陽光は日焼けするほど強く、そして夜は木枯らし一号。
本当にめまぐるしい日曜日(昨日)でしたが、運動会や地域の街づくり行事、そして少年少女サッカー大会など、地域行事の多い日でした。サッカーでは「浦和レッズがアジアNo.1、昨日は北京五輪に向けて前進する勝利。来月には世界のチームが日本に来る。オシム監督の病状は心配だが、走って走って走り抜く、攻めて攻めて攻め抜くオシム監督のめざすサッカーで頑張ってほしい」と挨拶をしました。
このところ、産科・小児科などの医師不足、救急医療の対応策、東京の地域医療を支える中型・中核の病院の現状視察や対応に力を注いでいます。きわめて深刻。看護士さん不足、7対1の看護士問題や72時間問題など、制度変更がこうした病院を直撃しているのが現状です。現場から見る。現場から構造改革のゆがみを見る。その姿勢を常に貫いていきたいと思っています。
 57人のつづった後藤田正晴への感謝ともいえる言葉。まさに戦後史そのものだ。日本が国難ともいうべき時、判断の難しい時、即座の判断が求められる時、後藤田さんがいた。後藤田さんという座標軸をもっていたこと、鍛え抜かれた判断力と、それを実行する存在感をもつ人が権力の中枢にいたことは幸せだった。
57人のつづった後藤田正晴への感謝ともいえる言葉。まさに戦後史そのものだ。日本が国難ともいうべき時、判断の難しい時、即座の判断が求められる時、後藤田さんがいた。後藤田さんという座標軸をもっていたこと、鍛え抜かれた判断力と、それを実行する存在感をもつ人が権力の中枢にいたことは幸せだった。
日中友好会館、日中を中心にお話をさせていただいたが、もっとじっくり話したかったと今も思っている。
「政治は目的実現のために権力を使いこなす。しかし同時に大事なのは国家権力の怖さを知り、権力を細心にして丁寧に慎重に扱うことだ」
「権力者は謙虚であらねばならない。職権は行使するより話し合いを第一に考えることだ」
「国家の基本をゆるがせにするな」――後藤田さんの魅力を次々と本書は示しているが、その魅力を感じる57人もおやっと思う感性を見せてくれている。
昨今の日本の政治家に「政策通はいても政治通がいない」ことが問題だと指摘する人がいたが、「政治家とは」ということを考えさせる一書でもある。