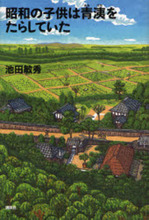秋の到来。地元では運動会、文化祭など諸行事が多く、走り回っています。
14日の日曜日も北区剣道大会を皮切りに、運動会や祝賀会、そして党として初の地方議員懇談会(東日本)などを行いました。
剣道大会で私が挨拶。「大相撲の朝青龍、ボクシングの亀田などが批判されている。それは日本の武道、そしてスポーツには、『勝てばよい、強ければよい』のではない。心のあり方、礼節、品格が求められているからだ。身心を鍛えるということが身体とともに、心を鍛え、心を養い、心を豊かにするということが大切だ。剣道をするなかで、人生にとって必要な攻める力と守る力、能動の力と受動の力の2つを築いてほしい」と話をしました。
子供たちが、伸びのびと元気に、声を出して気合をこめて試合をする光景に、うれしい思いがこみあげてきました。京大相撲部は「強き者よし、弱き者更によし」を部是としていました。いやこの部是は甘すぎる、強くなければダメだということを熱く論じたことがなつかしいですが、とにかく「人間を鍛える」ことこそが大事であることは時代を超えた真理だと思います。
 政府・企業・個人の連携による解決策、総力戦の必要性をいっている。この種の他の本と違うところがある。それは、国内そして諸外国を徹底して調査してきわめて現実的、具体的な方策を示していることだ。子どもを産みやすく、育てやすい環境を創造するために、企業のネットワークによる子育て支援サービス、生活塾。そして企業としてワーク・ライフ・バランス戦略は「海外の両立先進企業から学ぶ(両立支援はハイリターンの投資)」「中小企業から学ぶ(中小企業の職場環境は遅れているというのは誤り)」などを示す。育児休業を取得したとき、日本では「所得ロス」「キャリアロス」「業務知識ロス」の3つが生ずるが、欧米企業はそうでないことも示されている。
政府・企業・個人の連携による解決策、総力戦の必要性をいっている。この種の他の本と違うところがある。それは、国内そして諸外国を徹底して調査してきわめて現実的、具体的な方策を示していることだ。子どもを産みやすく、育てやすい環境を創造するために、企業のネットワークによる子育て支援サービス、生活塾。そして企業としてワーク・ライフ・バランス戦略は「海外の両立先進企業から学ぶ(両立支援はハイリターンの投資)」「中小企業から学ぶ(中小企業の職場環境は遅れているというのは誤り)」などを示す。育児休業を取得したとき、日本では「所得ロス」「キャリアロス」「業務知識ロス」の3つが生ずるが、欧米企業はそうでないことも示されている。
安部首相の突然の辞任、福田内閣のスタートと、あわただしい秋の国会となりましたが、「落ち着いた」とか、「冷静な国会論議を期待」という論調も出ています。
この間、9月24日に自民党との政権協議(9月25日に合意)を行い、「政治とカネについては1円以上の全ての支出に領収書添付の義務付け」「高齢者の医療負担を凍結(引き上げない)」「障害者自立支援法の抜本的見直し」など15項目にわたる合意をしました。
救急医療や医師不足対策、事業承継税制の拡充などの中小企業支援策なども盛り込みました。
政治の信頼回復と生活重視の公明党の姿勢が大きく反映しています。
また10月2日は、「沖縄戦の『集団自決』において旧日本軍が関与したことは否定できない事実である。
教科書検定において政治は関与してはならないことを踏まえたうえで、"沖縄の痛み""沖縄の心"を重く受け止め善処してほしい」と私は政府与党協議会において発言しました。
問題が次々指摘されるなか、公明党の主張をしっかりしていきたいと思っています。4日は、党を代表して私が代表質問をしました。
いよいよ10月。地元の運動会に連続して参加することになります。8月・9月は、夏祭り、納涼祭、盆踊りなどの諸行事が多く、私は多い日で36会場回った日もあります。地元では「身近なことから大きなことまですぐやる男・太田昭宏」といわれてきましたが、そのまま現場を徹底して走り抜き、現場からしっかりした発言をしていきたいと決意しています。
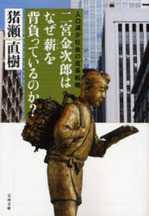 猪瀬さんからいただき、すぐ読んだ。薪を背負った勤勉な少年、「手本は二宮金次郎」は、勤勉、倹約の人と固定化されるのは誤りであり、努力によって得た薪は換金商品であり、それが金融として展開する。すぐれた経営コンサルタント。人口増の右肩上がりの江戸前半と人口減少社会であり、財政難、道徳的退廃の江戸後半。その難しい江戸後半において「分度」の概念と効率化と余剰を活用していく金次郎の実務の強さが表現される。
猪瀬さんからいただき、すぐ読んだ。薪を背負った勤勉な少年、「手本は二宮金次郎」は、勤勉、倹約の人と固定化されるのは誤りであり、努力によって得た薪は換金商品であり、それが金融として展開する。すぐれた経営コンサルタント。人口増の右肩上がりの江戸前半と人口減少社会であり、財政難、道徳的退廃の江戸後半。その難しい江戸後半において「分度」の概念と効率化と余剰を活用していく金次郎の実務の強さが表現される。
人口減少社会、低成長時代における人と産業の配置は、全く違ったものであることを思い知らないといけない。財政再建を凝視し、そのうえで地方分権、そして高齢者の安心ライフスタイルの再配置。相当ダイナミックに変えなければ地域の活性化は難しい。