29日、新型コロナ対策特別措置法と感染症法の改正案が衆院本会議で審議入りしました。対策をより実効性のあるものにすべく、飲食店の(営業)時間短縮や効果的な財政支援を図ること等を盛り込み、命令に応じない場合は、事業者への過料を定めること等のものです。
28日、自民・立民の幹事長会談で、修正を合意。その直前に自民・公明の幹事長会談でも、その内容を合意しています。内容は「感染症法改正案の刑事罰(前科がつく)は厳しすぎるので撤回し、入院に応じない感染者への懲役は削除し、罰金は行政罰の過料にする」「特措法改正案等の違反した事業者への過料を減額する」「『蔓延防止等重点措置』を講じる際は国会報告する(国会の関与)」等にしたもので、公明党としての主張が入っています。
29日からの国会審議で、より詳細、具体的な要件や手順などを詰めていくことになります。29日の衆院本会議では公明党として高木美智代衆院議員が質問に立ちました。コロナ対策、医療支援、ワクチン接種、生活者支援、企業・事業主支援に全力をあげます。
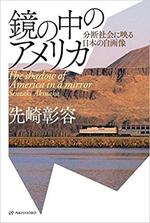 「分断社会に映る日本の自画像」が副題。2019年8月から1か月強、先崎さんはアメリカに滞在する。サンフランシスコからワシントンDCに飛び、帰りは東海岸から西海岸までぶっ通しで大陸横断鉄道に乗っての旅。明治維新時の岩倉使節団、そして昭和の敗戦とその後、先人はアメリカに何を見ていたのか。そして今の分断社会アメリカ・・・・・・。この150年、アメリカ文明を追い、今、価値を共有してきたかのようなアメリカ自体が、"分断国家"としての苦闇も抱え変質している。憧憬と翻弄のアンビバレンツの日米を今、「僕という鏡に映ったアメリカ」として描く。ヘレン・ミアーズの「アメリカの鏡・日本」を思いつつ、より長期の150年の日米を、そして日本と日本人を考える。
「分断社会に映る日本の自画像」が副題。2019年8月から1か月強、先崎さんはアメリカに滞在する。サンフランシスコからワシントンDCに飛び、帰りは東海岸から西海岸までぶっ通しで大陸横断鉄道に乗っての旅。明治維新時の岩倉使節団、そして昭和の敗戦とその後、先人はアメリカに何を見ていたのか。そして今の分断社会アメリカ・・・・・・。この150年、アメリカ文明を追い、今、価値を共有してきたかのようなアメリカ自体が、"分断国家"としての苦闇も抱え変質している。憧憬と翻弄のアンビバレンツの日米を今、「僕という鏡に映ったアメリカ」として描く。ヘレン・ミアーズの「アメリカの鏡・日本」を思いつつ、より長期の150年の日米を、そして日本と日本人を考える。
「翻弄され続けた150年」は事実だが、「ズレ」「きしみ」が自覚されているかといえば、人によってその濃淡は著しい。岩倉使節団――驚きは同居しても伊藤博文・森有礼の楽観的に見える「開国」と、久米邦武が描く「開国」とは全く異なり、久米は「壁」を実感する。久米の「米欧回覧実記」も、福澤諭吉の「文明論之概略」「西洋事情」も政治制度から生活・食事マナーに至るまで「具体的」だ。そしてその一つ一つに、固有の国家形成への歩みの違いを感じたのだ。1900年前後の西欧文明受容のなかに「日本人とは何か」を突き詰めて考え、世界に発信した内村鑑三、新渡戸稲造、岡倉天心、牧口常三郎・・・・・・。そして本書に出てくる戦後の昭和30年代の江藤淳「アメリカと私」や山崎正和「このアメリカ」・・・・・・。「つかの間の秩序維持こそが『大人』の仕事であり、常にマイナスをゼロに戻すこと、自分以外の存在が気づかずに歩いて通る道を舗装しているような作業を黙って続けることこそ、保守の定義である」という。
日米の「国家」に対する考え方も大いに異なる。「戦争」「敗北」から国家を嫌悪する傾向にある日本。あらゆる人種を受け入れ、「分裂するアイデンティティを唯一のアイデンティティとする人工性の高い国・アメリカ」「星条旗による移民族と広い国土の統合・アメリカ」とは全く違う。そのアメリカが今、移民を拒み、分断され、自己否定に陥り、自分で自分を壊す方向に進んでいる。先崎さんはかつて「分断社会と道徳の必要性」のシンポジウムで日本代表として発言する。「フィッテインジャー氏は、人間は家族、国家、そして教会に所属してこそ幸福を得られることを強調した。現代社会がここまで分断と孤立化を深めたのは、僕らが自由を"個人の選択できる権利"だと勘違いしたことにあるといっている。終始、国家、教会への所属を自分の好みの問題、共同体への所属は出入り自由だと考えてきたのが、僕らの時代である」という。「なぜ、疲弊するアメリカの真似をこれ以上日本はするのだ」と、ドック教授との対話のなかで考える。
「アメリカも日本も今、独自の文化を自分自身で失いかけている」「グローバル化は日本人から独自の文化である、寛容や忍耐を奪ってきたことに気付く」「欧米が常に最先端であり、正解を用意してくれる国家ではない。そこに疑問を感じ、自己とは何かを問う思想家になるか否か」・・・・・・。物乞いがいて、貧困と格差、銃撃戦が日常的にあり、その一方でGAFAが世界をリードするアメリカ。12.8と12.7と開戦がズレる日本とアメリカ。短期のアメリカの旅のなかで先崎さんの問いは根源的で重い。
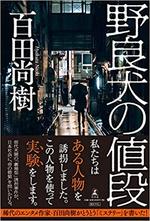 まことに不思議な誘拐事件が起きた。誘拐され人質になったのは会社の社長でもなければ金持ちの息子でも娘でもない。なんとホームレス。それも6人も揃ってだ。電話での脅迫ではなく、「誘拐サイト」を立ち上げて。しかもその相手は、名だたるメディア4社。
まことに不思議な誘拐事件が起きた。誘拐され人質になったのは会社の社長でもなければ金持ちの息子でも娘でもない。なんとホームレス。それも6人も揃ってだ。電話での脅迫ではなく、「誘拐サイト」を立ち上げて。しかもその相手は、名だたるメディア4社。
当初は、たんなるイタズラ、愉快犯の仕業と思われた。しかし、要求を飲まない場合は「人質を殺す」と脅し、その通り、渋谷に一人の人質の"首"が晒される。世論は緊張の度を増し、ツイート数は急増する。そして、2人目の殺人が続き、名指しされたメディア、警察は翻弄される。ネットを中心とした世論も、誘拐犯やメディアの印象操作、心理戦によって揺さぶられ変化していく。"潮目"の見きわめ――現代ネット社会の危うさ、脆弱性が、このネットを通じての"劇場型"誘拐事件として鮮烈に描かれる。犯人はいったい何を狙っているのか。
皮肉や風刺もエッジがきいている。正義を装う"偽善的論調"、ネット社会の暴走と脆弱性、キャッチフレーズ社会の浅薄さ・・・・・・。弱者に追い打ちをかける現代格差社会の矛盾と怒りが、"ホームレス"を題材として問題提起される。"野良犬の値段"だ。すでに始まっている新たなネット社会の負の断面を鮮やかに描いた傑作。
住居確保給付金が再支給可能に――。これまで、コロナの影響等で収入減となり、住居を失う可能性がある困窮者へ支給される住居確保給付金は、1度申請し支給が終了した場合、再申請はできませんでした。しかし、公明党の推進で、再申請が可能となるとともに、すでに支給を受けている方については、最長9か月から12か月まで延長されます。
21日にも、山本香苗参院議員、高木美智代衆院議員などが加藤勝信官房長官に再支給可能を申し入れたところです。
コロナ禍で、失業や極端な収入減で極めて厳しい人たちへの生活面の支援がますます重要です。しっかり支援できるよう、頑張ります。
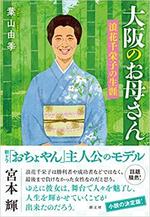 "大阪のお母さん"として愛され続けた浪花千栄子の波瀾万丈、辛抱、負けじ魂、好奇心の固まり、芸の道で天外を踏み越える、今日の日を体当たりでやってきたから今がある、仕事のためならムチ打ってでも頑張る――そうした次々に押し寄せる試練をくぐり抜ける人生を描く。今のNHKの朝ドラ。凄まじい。
"大阪のお母さん"として愛され続けた浪花千栄子の波瀾万丈、辛抱、負けじ魂、好奇心の固まり、芸の道で天外を踏み越える、今日の日を体当たりでやってきたから今がある、仕事のためならムチ打ってでも頑張る――そうした次々に押し寄せる試練をくぐり抜ける人生を描く。今のNHKの朝ドラ。凄まじい。
明治40年、これでもかというほどの極貧の家庭に生まれ育った南口キクノは、5歳で母を亡くす。キクノは朝4時に起きて食事の用意、弟の世話や鶏の世話、掃除に洗濯。学校にも行けない。再婚した父親は女と蒸発、丁稚奉公に出される。「今日から、おちょやんと呼ばれたら、大きな声で返事するんやで」「浪花料理の下働きが2年と持たないことは周知の事実。キクノが8年間勤めたことは前代未聞だった」「親の束縛を断ち切るのは今や。19歳のキクノは京都に出る」「あんたも女優にならへんか。浪花千栄子の誕生」「昭和3年9月、道頓堀角座で松竹家庭劇(座長・曽我廼家十吾、渋谷一雄)スタート。千栄子は松竹系の劇団を移動しながら女優修業」「昭和4年、一雄は2代目渋谷天外襲名。千栄子は正式に松竹家庭劇配属」「天外と結婚、舞台では代役の日々」「終戦。天外、松竹家庭劇を飛び出す」「昭和21年、天外『劇団すいと・ほーむ』旗揚げ、千栄子38歳、18歳の藤山寛美加わる」「昭和23年夏、五郎劇と家庭劇と天外が合併、松竹新喜劇誕生」「天外の裏切りで離婚、桂川の川べりで死を考える。しかし、なんでうちが死ななあかんねん。仕返ししたる。後悔させたる。あんたがひれ伏すまでうちはやったる。負けへんで」「NHKが花菱アチャコの相手役に指名。大阪弁が達者でアドリブにも臨機応変に対応できる人は浪花さんしかいない。昭和27年1月から『アチャコ青春手帖』に出演し大ヒット。映画界からも声」「昭和28年、溝口健二監督から声がかかり、舞台から映画へ」「千栄子の夢・嵐山に家を建てる(昭和31年)。もの心ついたころから、千栄子には安心して過ごせる家などなかった」「ラジオドラマを映画化した『お父さんはお人好し』シリーズを含め、千栄子は生涯200本以上の映画に出演」「テレビの全盛期となりテレビ出演に大忙しの身となる」・・・・・・。
「舞台の世界は、食うか食われるかの戦場と言うけど、その戦場で、自分らのお芝居が勝つためには、いかに和を作れるかっちゅことや。うちにしてみれば、いかに、そんなええお母ちゃんになれるかにかかってくるねん」と言ったという。昭和48年、泥水の中に生まれ生き抜き、大輪の花を咲かせて、66歳で逝去。


