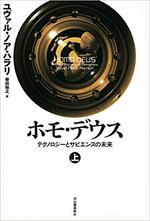
 「テクノロジーとサピエンスの未来」が副題。前作の「サピエンス全史」では、7万年前、認知革命が起き、言語が出現。さらに1万2千年前は農業革命、そして書記体系(記号を使っての情報保存)、貨幣を生み、近代科学の成立、科学と帝国の融合等を経て、全地球の主となったサピエンスが描かれた。そして最後に「私たちは以前より幸福になっているのか」「正真正銘のサイボーグ、バイオニック生命体に変身する超ホモ・サピエンス時代に突入する瀬戸際である」との2つの痛烈な疑問を突きつけた。
「テクノロジーとサピエンスの未来」が副題。前作の「サピエンス全史」では、7万年前、認知革命が起き、言語が出現。さらに1万2千年前は農業革命、そして書記体系(記号を使っての情報保存)、貨幣を生み、近代科学の成立、科学と帝国の融合等を経て、全地球の主となったサピエンスが描かれた。そして最後に「私たちは以前より幸福になっているのか」「正真正銘のサイボーグ、バイオニック生命体に変身する超ホモ・サピエンス時代に突入する瀬戸際である」との2つの痛烈な疑問を突きつけた。
その続編が本書。「人間は至福と不死、神性を追い求めることで、自らをホモ・デウス(神のヒト)へとアップグレードしようとしている」「人間は健康と幸福と力を追求しながら、自らの機能を徐々に変えていき、ついにはもう人間ではなくなってしまうだろう」という。いったい、我々はどこへ向かうのかを、生物学的に、科学・工学的に、科学と宗教や歴史を分析して提示する。「人類が新たに取り組むべきこと」「人新世」「人間の輝き」「物語の語り手」「科学と宗教というおかしな夫婦」の5章が上巻だ。そして下巻は「現代の契約」「人間至上主義革命」「研究室の時限爆弾」「知識と意識の大いなる分離」「意識の大海」「データ教」で、これら第3部は「ホモ・サピエンスによる制御が不能になる」だ。
現代社会は人間至上主義の教義を信じており、それを実行するため科学を利用する。科学と人間至上主義の間の現代の契約は崩れるだろうか。科学と何らかのポスト人間至上主義の宗教との取り決めに場所を譲る可能性があるのではなかろうか。その新しい取り決めとは一体何かを掘り下げる。生物は、遺伝子やホルモン、ニューロンに支配されたただのアルゴリズムであり、コンピューターが、人間を自分自身よりも詳しく把握することになる。人間至上主義に取って代わる有力なものはデータ至上主義だが、それは人間をアップグレードしても対処できない。「人間はその構築者からチップへ、さらにはデータへと落ちぶれ、データの奔流に溶けて消えかねない」と危惧する。しかし、そうした現実の動向を分析しつつも、最後に3つの重要な問いを提起して締めくくる。「生き物は本当にアルゴリズムにすぎないのか? そして、生命は本当にデータ処理にすぎないのか?」「知能と意識のどちらのほうが価値があるのか?」「意識は持たないものの、高度な知能を備えたアルゴリズムが、私たちが自分自身を知るよりもよく私たちのことを知るようになったとき、社会や政治や日常生活はどうなるのか」――。当然、そこには「世界に意味を与えている虚構を読み解くことが、絶対に必要となる」ということだ。
 「2025年に認知症700万人」「誰でも長生きすれば、認知症とつきあうことになる」「認知症というと医療やケアの問題だと思いがちだが、それは大事な要素ではあるが、もっと広いテーマ。法律や経済、情報化、コミュニケーション、家族など、社会全体の設計の問題。ATM、買い物、移動、交通、通信など全てにわたる」――。社会そのものを変える。認知症の人とそうでない人が別の世界に住んで暮らしている現状を変える。「まざっていく社会」になる。社会全体を認知症対応に"アップデート(更新)"する必要がでてきている。「認知症フレンドリー社会」は、漠然と"みんなにやさしい社会"というのではない。社会全体を認知症対応にアップデートするということだ、という。
「2025年に認知症700万人」「誰でも長生きすれば、認知症とつきあうことになる」「認知症というと医療やケアの問題だと思いがちだが、それは大事な要素ではあるが、もっと広いテーマ。法律や経済、情報化、コミュニケーション、家族など、社会全体の設計の問題。ATM、買い物、移動、交通、通信など全てにわたる」――。社会そのものを変える。認知症の人とそうでない人が別の世界に住んで暮らしている現状を変える。「まざっていく社会」になる。社会全体を認知症対応に"アップデート(更新)"する必要がでてきている。「認知症フレンドリー社会」は、漠然と"みんなにやさしい社会"というのではない。社会全体を認知症対応にアップデートするということだ、という。
「認知症フレンドリー社会」とは「認知症の人が高い意欲を持ち、自信を感じ、意味があると思える活動に貢献、参加できるとわかっている、そうした環境である(英国のアルツハイマー病協会の定義)」を示す。「認知症対処社会」ではなく、「認知症フレンドリー社会」だ。
最も進んでいる英国の認知症の課題に取り組む団体や企業を束ねるネットワーク「認知症アクション連盟(DAA)」が紹介される。プリマス市の活動、図書館やバス会社のヘルプカード。また空港やスーパーマーケットなどの工夫。日本の大牟田市(まちが変わると退院する人が増えた)、富士宮市(認知症の人の声からはじまるまちづくり)、町田市(アイ・ステートメント、Dカフェ、デイサービスの人が洗車など地域で仕事をする)などが紹介される。
認知症とそうでない人の間の目に見えない多くの壁を取り除く、互いが互いを支える。日本の最重要の課題だ。
29日(土)、神奈川県横浜市と川崎市で、佐々木さやか参院議員(参院選予定候補・神奈川選挙区)と街頭演説を行いました。雨模様のなか、大勢の方に参加していただき、参院選勝利への訴えをしました。
佐々木さやか参院議員は「命を守り、生活を守り、経済・雇用を守るために全力を尽くす」と実績を述べつつ、決意を表明。私は「佐々木さやかさんは小さな声を聴き、国会で6年間に140回の質問をした結果を出す議員だ」「全世代型社会保障が大きく前進している。子育て支援、教育支援が進み、有効求人倍率も1.62倍まで上がり、仕事がある日本になった」「人生100年時代、公明党はフレイル予防や認知症施策に全力をあげている」などと、支援を訴えました。







