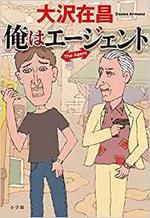2月3日、「薬害C型肝炎訴訟 国との基本合意10周年記念集会」が都内で開催されました。忘れもしない2007年も暮れの12月。寒空のなかでの座り込み、集会の姿を今も思い起こします。当時の福田首相と私(当時公明党代表)は何度も話し合い、この基本合意ができました。翌年の国会において、救済法が成立。衆議院通過の時に、公明党の議員総会で、山口美智子薬害肝炎全国原告団代表等から喜びの報告をしていただき、その光景は忘れることができません。
それから10年、まだC型肝炎感染であることを知らない被害者も多く、救済できるように救済法の延長を昨年働きかけ、昨秋の臨時国会で実現しました。
この日、山口美智子代表や浅倉美津子10周年記念集会実行委員長からも、私に「公明党に感謝しています」との言葉をいただきました。さらに、薬害被害の救済と再発防止に、力を注いでいきたいと強く思っています。
またこの日、「節分会」や「世界空手選手権大会の祝勝会」、地元の新年会などに参加し多くの方と懇談しました。
 ストレス社会から心と体をどう守るか。世界では、科学的方法でストレスに立ち向かおうという意識革命が始まっている。脳科学、心療内科等々で大きな進展があり、企業内でも取り入れが始まっている。
ストレス社会から心と体をどう守るか。世界では、科学的方法でストレスに立ち向かおうという意識革命が始まっている。脳科学、心療内科等々で大きな進展があり、企業内でも取り入れが始まっている。
ストレスとは何か。ストレスとは「変化」である。配偶者の死、会社の倒産、多忙による身の過労は勿論、家族が増えたり、引っ越しもストレスとなる。
最新の科学は、その詳細なメカニズムを明らかにする。「ストレス反応を起こす引き金となるのは扁桃体」「"支配―従属"の関係でストレスは生み出される」「ストレスホルモン『コルチゾール』」「体をむしばむストレスの暴走」・・・・・・。そこでどう対応するか。3つ提示される。「脳を変化させる運動と病を防ぐ食生活」「ストレスを観察し対処するコーピング」「世界の注目を浴びるマインドフルネス」だ。これまで、ストレス社会といいながら断片的知識で終わり、日常的に、しかも科学的に対処してこなかった。いいきっかけとなる本書の意味は大きい。
 2020東京オリンピック・パラリンピックまで1000日を切った。パラリンピックの意義は限りなく大きく、未来に向けて意識を変える大きなチャンスでもある。これこそが、最大のレガシーと言えるかも知れない。本書は、早稲田大学の全学共通プログラムとして、2015年度から「パラリンピック概論」を開講、その講義を中心に編んだもの。生きいきとした内容が伝わってくる。
2020東京オリンピック・パラリンピックまで1000日を切った。パラリンピックの意義は限りなく大きく、未来に向けて意識を変える大きなチャンスでもある。これこそが、最大のレガシーと言えるかも知れない。本書は、早稲田大学の全学共通プログラムとして、2015年度から「パラリンピック概論」を開講、その講義を中心に編んだもの。生きいきとした内容が伝わってくる。
「失われたものを数えるな、残されたものを最大限に生かせ」――。「パラリンピックの父」と呼ばれるルートヴィヒ・グットマン博士の言葉だ。ロンドン郊外のストーク・マンデビル病院でスポーツを通じて生きる喜びや希望や可能性を伝えた博士の言葉で、1948年のストーク・マンデビル大会がパラリンピックの原点となる。
第1回大会は1960年ローマ大会、パラリンピックの名称は1964年東京オリンピックからだ。そして「リハビリの大会」から「競技の大会」へと進展し、2012年ロンドンパラリンピックでは20競技503種目と拡大する。ロンドンオリンピックは26競技302種目で、パラリンピックの競技種目の方が多い。障がいの程度に応じた種目となっているためで、男子100mという種目は13個、車イスバスケットボールでも4クラスある。
課題は山ほどある。「パラリンピックの環境整備」「ボランティアを含めた人、そして物と資金」「注目度を高めるためのメディアの活用」「キメ細かなインフラの整備」「選手の声を聞いて対応する力とスピード(限界は伸びる)」「スポンサー企業を増加させる取り組み」「障がい者が頑張っているのではなく、スポーツに打ち込むアスリートという意識変革(パラリンピックはチャンス)」・・・・・・。
2020年に向けて①スポーツ・健康②街づくり・持続可能性③文化・教育④経済・テクノロジー⑤復興・オールジャパン・世界への発信――。これが5本柱だが、まさに「スポーツには世界と未来を変える力がある」。パラリンピックはチャンスだ。パラリンピックの魅力と凄さを知ることは、心のバリアフリー、共生社会の実現に大きくつながっていく。
 明治150年――。激動の幕末、それぞれの藩に激流が襲いかかった。苦悩し、生き残りを懸命に模索した。迷走もあり、運・不運もあったが、各藩はどう判断したか。幕末を各藩の命運という角度で切り取る。立体的で実に面白く、教訓を示唆する。
明治150年――。激動の幕末、それぞれの藩に激流が襲いかかった。苦悩し、生き残りを懸命に模索した。迷走もあり、運・不運もあったが、各藩はどう判断したか。幕末を各藩の命運という角度で切り取る。立体的で実に面白く、教訓を示唆する。
並べられたのは象徴的な14の藩。薩摩藩(維新回天の偉業を成し遂げた二才(にせ)と呼ばれる薩摩の若者たち)、彦根藩(薩長の走狗となって「生き残った」幕末最大の裏切り者)、仙台藩(東北を戦渦に巻き込む判断ミスを犯した"眠れる獅子")、加賀藩(一方の道を閉ざしてしまったことで、墓穴を掘った不器用な大藩)、佐賀藩(鍋島閑叟の下、一丸となって近代化の魁となった雄藩)、庄内藩(全勝のまま終戦した奇跡の鬼玄蕃(酒井玄蕃))、請西藩(徳川家への忠節を誓い「一寸の虫にも五分の魂」を実践した林忠崇)、土佐藩(無血革命を実現しようとした「鯨海酔候」山内容堂)、長岡藩(義を旗印に苦難が待ち受けていようと筋を通した河井継之助と長岡藩士)、水戸藩(明治維新の礎となった勤王の家譜)、二本松藩(義に殉じて徹底抗戦を貫いた武士の矜持)、長州藩(新時代の扉を開いたリアリストたち)、松前藩(辺境の小藩の必死の戦い)、会津藩(幕末最大の悲劇を招いた白皙の貴公子・松平容保)――。
幕末の激震のなかでの藩としての決断や岐路についての論考。