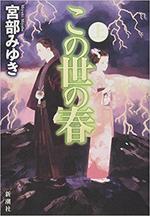
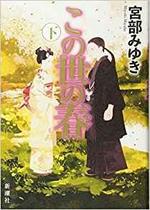 下野国の北見藩。六代藩主・重興は、26歳にして乱心による主君押込にあい、「五香苑」という屋敷の座敷牢に閉じ込められる。そこから夜な夜な女の啜り泣きや子供の笑い声が発せられる。重興に重用され押込時に切腹したはずの御用人頭・伊東成孝も山中の岩牢に閉じ込められていた。いったいなぜ、重興は乱心したのか。そこに宿る恐怖は何によるのか。御用人頭・成孝が狙ったものは何か。名君と称えられた五代藩主・成興、そして北見家に秘し潜められた闇と謎・・・・・・。宮部みゆき作家生活30周年記念作品。長編だが、緊迫感はとぎれることなく、最後まで引き付けられる。
下野国の北見藩。六代藩主・重興は、26歳にして乱心による主君押込にあい、「五香苑」という屋敷の座敷牢に閉じ込められる。そこから夜な夜な女の啜り泣きや子供の笑い声が発せられる。重興に重用され押込時に切腹したはずの御用人頭・伊東成孝も山中の岩牢に閉じ込められていた。いったいなぜ、重興は乱心したのか。そこに宿る恐怖は何によるのか。御用人頭・成孝が狙ったものは何か。名君と称えられた五代藩主・成興、そして北見家に秘し潜められた闇と謎・・・・・・。宮部みゆき作家生活30周年記念作品。長編だが、緊迫感はとぎれることなく、最後まで引き付けられる。
苦しむ重興を救うべく「五香苑」に集まった人々。主人公・各務多紀、元家老の石野織部、多紀の従弟の田島半十郎、主治医・白田登、奉公人の寒吉やお鈴、筆頭家老の脇沢勝隆らは、この重くて深い北見藩の闇と謎に挑んでいく。これらの人はいずれもしっかり者で、互いを思いやる優しさと明るさをもっており、重苦しく奇怪な世界を三変土田してくれる。人々の力が閉ざされた寒い雪の冬から春をもたらしていく。雪溶け。
 重厚な書である。現代社会の底流に横たわっている日本が挑んだ「近代化」の根源について考察、開示してくれる。学問の世界が専門化し各論化するのはやむを得ないが、「日本近代についての総論」を骨太に引き出している。まさに歴史を俯瞰し、綿密に深く入り、わしづかみする力を感ずる。
重厚な書である。現代社会の底流に横たわっている日本が挑んだ「近代化」の根源について考察、開示してくれる。学問の世界が専門化し各論化するのはやむを得ないが、「日本近代についての総論」を骨太に引き出している。まさに歴史を俯瞰し、綿密に深く入り、わしづかみする力を感ずる。
その日本の近代を形成したものとして「政党政治」「資本主義」「植民地帝国」「天皇制」の4つをあげ、「なぜ、どのように成立してきたか」を剔抉する。
19世紀後半に活躍した英国のウォルター・バジョットの示した「英国の国家構造」「前近代の要素"固有の慣習の支配"から近代を特徴づける"議論による統治"を成り立たせるものは何か」から、日本のこの4つを分析・解析する。いずれも根源は深く、成立への過程は激烈だ。「幕藩体制の権力抑制均衡メカニズム」「文芸的公共性の成立」「明治憲法下の権力分立制と議会制の政治的帰結」・・・・・・。「資本主義」については不平等条約の打開や外債に依存しない意志のなか、「自立的資本主義化への道」として政府主導の殖産興業、租税や教育など4つの条件が示される。そして日清戦争、日露戦争を経て、国際的資本主義への道が分析され、さらにその没落の過程が示される。「植民地帝国へ踏み出す日本」では、三国干渉がいかに大きかったか、枢密院の存在、韓国統治の中心統監の権限をめぐる争い、文民と陸軍、帝国主義に代わる地域主義の台頭など生々しい。そして「日本の近代にとって天皇制とは何であったか」では、ヨーロッパのキリスト教の機能を見出せない日本の「国家の基軸としての天皇制」「神聖不可侵性を積極的、具体的に体現された道徳の立法者としての天皇」、そこで憲法外で明示した「教育勅語」等が解説される。とくに教育勅語の中村正直の草案を覆した井上毅の「宗教教育から峻別」された「天皇自らの意思表明の形式」への思考回路が鮮やかに示される。全体を通じ、世界の列強のなか、明治、大正、昭和初期の短期間に遂行を迫られた「近代化」への苦悶が重厚に語られる。
晴天の2日、党新春街頭演説会を新宿で、地元でも北総支部街頭演説会を赤羽で行いました。
このなかで私は「今年は明治150年、平成30年という大きな区切りだ。仕事をする年だ」「日本は人口減少・少子高齢社会、急速に進むAI(人工知能)やIoTやバイオテクノロジー(BT)時代の2つの大きな構造変化を迎えている。これに備えてダッシュをする年だ」「公明党は昭和39年の立党以来、『大衆福祉の公明党』として一貫して進んできた。今、全世代型社会保障が政治のメインテーマになっているが、公明党がど真ん中に立って仕事をする時だ」。
また、「年金・医療・介護などの高齢者支援、幼児教育無償化や待機児童対策などの子育て支援、 私立高校の授業料無償化や大学における給付型奨学金、無利子奨学金の拡大などの教育支援などを前に進めるのが公明党の役割りだ」と訴えました。
しっかり頑張ります。










