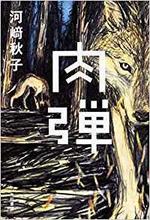新しい年を迎えました。昨年は皆様から一方ならぬ御支援を賜り、心より感謝申し上げます。真心を全身で受け止め、北朝鮮などの安全保障・外交問題、景気・経済、子育て・教育を含めた全世代型社会保障などに全力で取り組んでまいります。
何といっても景気・経済を活性化し、その果実を人口減少・少子高齢社会での子育て支援、教育支援、年金・医療・介護の安心に振り向けます。「人への投資」であり、一貫して主張し続けてきた全世代にわたる生活保障です。またIT・AI(人工知能)など技術革新に力を注ぎ、生産性向上を図ります。脆弱国土日本を災害に強いまちにすべく、防災・減災対策を強化させます。今年は「未来に責任」「仕事をする年」と決め、全力で頑張ります。
本年が良き一年でありますよう心よりお祈り申し上げます。
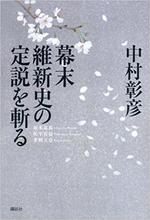 明治150年を迎える。幕末の大激動の渦中、謎も多い。膨大な史料、歴史家の研究をもってしても完全に定まるとは言えないものもある。中村彰彦氏が徹底して調べ、考える。
明治150年を迎える。幕末の大激動の渦中、謎も多い。膨大な史料、歴史家の研究をもってしても完全に定まるとは言えないものもある。中村彰彦氏が徹底して調べ、考える。
竜馬「暗殺」――。慶應3年(1867年)11月15日の夜5つ半(9時)前後、京都の河原町四条上ル蛸薬師角にある醤油業近江屋(井口新助)の母屋2階で、坂本竜馬、中岡慎太郎が暗殺される。幕府の見廻組組頭・佐々木唯三郎指揮の6人、その刺客団の1人であった今井信郎が竜馬を斬殺する。しかし、問題はその裏だ。「竜馬『暗殺』については、薩摩藩とくに西郷を黒幕とする仮説を立てると、かなりの事実を矛盾なく説明することができる」という。
「松平容保はなぜ京都守護職に指名されたか」――。それは、会津が最も信頼されていた藩であったこと。会津藩は保科正之に始まり、名家老・田中玄宰によって富国強兵に成功した雄藩であったがゆえに、幕府から尊王攘夷派というテロリストを制圧する役割を担わされた、という。
「孝明天皇は『病死』したのか」――。「孝明天皇病死説を主張する研究論文にはかなりの論理の飛躍や不備が存在する。その反対に毒殺説にはかなりの説得力がある」「岩倉具視を黒幕、かれにリモート・コントロールされていた宮中『討幕派』の女官を実行犯とする見解を考察すると・・・・・・」と闇に踏み込んでいる。
 「教育の深さが日本の未来を決定する」「教育は人格の完成を目指す」「学校教育は一人ひとりの子どもの未来を、そして我々の社会の将来を創る仕事であり、それを責任をもって担う存在こそ教師である」――。教育費の負担軽減は環境づくりとして大事なことだが、何といっても問われるのは教育の中身、教師の質だ。
「教育の深さが日本の未来を決定する」「教育は人格の完成を目指す」「学校教育は一人ひとりの子どもの未来を、そして我々の社会の将来を創る仕事であり、それを責任をもって担う存在こそ教師である」――。教育費の負担軽減は環境づくりとして大事なことだが、何といっても問われるのは教育の中身、教師の質だ。
本書は教育改革国民会議、中央教育審議会などで主要な役割を果たし、現在も新しい時代のなかでの教育、学校教育の再建と推進に熱く働き続ける梶田先生の「教師力の再興」への思いの込もった書だ。「なるほど、教師は使命職」「教師はさすがに人の心を耕し、鍛え、育むプロ」との思いがつのる。そして教師だけではない。各界のリーダー的立場にある者、そして父母保護者も参考になり、考えさせる。
「師道の再興を」「今、教師に求められる資質・能力」「確かな授業、熱意を込めた魅力と迫力ある授業」「真の授業力とは」「内面性の教育で確かな学力と豊かな心を」「加賀千代女、松尾芭蕉の句から何に気づかせるか」「開示悟入の教育の実現を」「"外れ"教師問題、"教えない"先生問題」「教師の不易の資質・能力とは」・・・・・・。柔軟で深く、どっしりした人間教育への指針が伝わる。
心を閉ざした息子・沢キミヤと父は、猟銃をかつぎ、とりつかれたように森林の中へと突き進む。北海道の、人も全く通わぬ奥深きカルデラの山中――。そこで狙った熊に逆襲され、群れをなす野犬にも襲われる。その獣との凄絶な戦いはすさまじい。いや北海道の開拓史には常にそうした言語絶する厳しい自然と野生動物との格闘があったことを想起させる。
父は倒され喰われるが、息子は戦い生き残る。凄絶な戦いには、人間もない、知性も理性もない、思考する暇もない。土壇場に立った時に噴出する野生の無限のエネルギー。ヒトと獣の生きる、食う、生殖――それは過酷な自然のなかで生命を繋ぐ残酷な結晶ですらある。人肉を喰らう極限の残酷さだ。「何でもよい。生きよ!」との声が原野に地響きのように聞こえてくる。まさに「肉弾」、むき出しの肉弾だ。
武田泰淳の「ひかりごけ」、コッポラの映画「地獄の黙示録」を思い出した。現代文明のなかで、人は何層にも分かれて生きるようだ。しかし究極する所、その生命の根源の所には生への執着と、とてつもない野生のエネルギーがあるようだ。北海道の原野で今も生き抜いている河﨑さんならではの野太い、荒削りの「生きる」「自然・動物と共に生きる」小説に、今回も"浴びせ倒され"た。