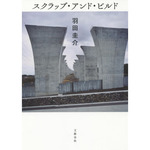訪日外国人客急増 ―― 昨年1973万人に!
 19日、広島市で開かれた公明党広島県本部(代表=斉藤鉄夫幹事長代行)の新年賀詞交歓会に出席、挨拶をしました。これには斉藤氏と、桝屋敬悟衆院議員、谷あい正明参院議員(参院選予定候補=比例区)のほか、湯崎英彦知事、松井一実広島市長ら多数の来賓が出席しました。
19日、広島市で開かれた公明党広島県本部(代表=斉藤鉄夫幹事長代行)の新年賀詞交歓会に出席、挨拶をしました。これには斉藤氏と、桝屋敬悟衆院議員、谷あい正明参院議員(参院選予定候補=比例区)のほか、湯崎英彦知事、松井一実広島市長ら多数の来賓が出席しました。
私は、「デフレ脱却ができるところまで経済最優先を貫く重要な年だ」「本日、昨年の訪日外国人数が1973万7000人となったことが発表された。観光には"見るもの""食べもの""買いもの"の三つが揃うことが大切だ。"見るもの"は景観とともに文化・歴史・伝統の奥深さが重要だ。平和の原点・広島は、さらに訪日外国人を呼び寄せるポテンシャルを持っているし、けん引して欲しい」と訴えました。
 訪日外国人数は、24年が836万人、私が国土交通大臣(観光庁所管)になった1年目の25年に、1000万人を超えて1036万人。26年が1341万人、そして昨年が1973万7000
訪日外国人数は、24年が836万人、私が国土交通大臣(観光庁所管)になった1年目の25年に、1000万人を超えて1036万人。26年が1341万人、そして昨年が1973万7000
人と急増。2020年に2000万人の政府目標を、実質的に5年前倒しでほぼ達成のところまできました。訪日外国人客の旅行消費額も一気に増えて3兆4771億円となり、旅行観光収支も大阪万博以来の大幅のプラスになりました。今後、3000万人時代を目指すわけですが、党に観光立国推進本部を立ち上げ、力を入れています。空港・航空の拡充、地方空港の充実、クルーズ船の誘致、ホテル不足への対応、Wi-Fiなどの外国人観光客の誘客対応など、多くの課題解決に全力をあげます。観光は成長産業の大きな柱に間違いなくなりました。さらに頑張ります。
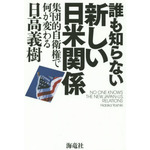 「日本は1950年のサンフランシスコ条約成立によって独立して以来、国の安全保障をすべてアメリカに依存し、危機的な状況に陥ることを避けることができた。だがいまやアメリカの影響力は急速に後退している。日本が築き上げてきた繁栄を守ろうとするのであれば、政治と経済においてだけでなく、軍事でも、主権に基づく独自性の高い行動をとる必要がある」「戦争というのは孤立した現象ではなくて、政治行為の一部である。これは世界の常識である」という。副題として「集団的自衛権で何が変わる」とある。
「日本は1950年のサンフランシスコ条約成立によって独立して以来、国の安全保障をすべてアメリカに依存し、危機的な状況に陥ることを避けることができた。だがいまやアメリカの影響力は急速に後退している。日本が築き上げてきた繁栄を守ろうとするのであれば、政治と経済においてだけでなく、軍事でも、主権に基づく独自性の高い行動をとる必要がある」「戦争というのは孤立した現象ではなくて、政治行為の一部である。これは世界の常識である」という。副題として「集団的自衛権で何が変わる」とある。
世界情勢は大きく変化している。それは米国の国民意識・関心の変化であり、"世界の警察官"米国の指導力や米軍の変化であり、ロシア・中国・ウクライナ・シリア・イスラム国等をめぐる状況変化であり、シェール革命をはじめとするエネルギー事情の変化であり、レーザー攻撃兵器や核兵器小型化、サイバー攻撃等の技術の変化など多岐にわたる。2016年の米国大統領選挙戦の現状には、それらが如実に現われていると指摘する。
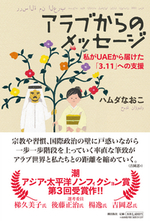 「私がUAEから届けた『3.11』への支援」と副題にある。1990年にUAEの男性と結婚してUAE(アラブ首長国連邦)に移住した著者。東日本大震災にドバイで「チャリティー着物ショー」を開催し、支援に乗り出す。政治・文化・慣習・システムの違いに直面し、苦難に次ぐ苦難。「認可のない義援金集めが犯罪となるこの国では、相手が認可をこの目に見せるまでは、着物ショーをする気は全くなかった」「2001年以来、アメリカの監視団が国際送金を厳視しているため、目的のはっきりした送金の形をとる必要がある」ために、大変な苦労が続く。「ほとほと私の神経も磨り減った」という6か月間だったという。しかし、その経過を語るなかで、政治・宗教・習慣・文化の違いのなかで、いかに心の交流が図られていくかが描かれる。現場の現実だけに生々しく、きわめて説得力をもつ。
「私がUAEから届けた『3.11』への支援」と副題にある。1990年にUAEの男性と結婚してUAE(アラブ首長国連邦)に移住した著者。東日本大震災にドバイで「チャリティー着物ショー」を開催し、支援に乗り出す。政治・文化・慣習・システムの違いに直面し、苦難に次ぐ苦難。「認可のない義援金集めが犯罪となるこの国では、相手が認可をこの目に見せるまでは、着物ショーをする気は全くなかった」「2001年以来、アメリカの監視団が国際送金を厳視しているため、目的のはっきりした送金の形をとる必要がある」ために、大変な苦労が続く。「ほとほと私の神経も磨り減った」という6か月間だったという。しかし、その経過を語るなかで、政治・宗教・習慣・文化の違いのなかで、いかに心の交流が図られていくかが描かれる。現場の現実だけに生々しく、きわめて説得力をもつ。
UAE、イスラーム、イフタール・・・・・・。これからの世界と日本を考えるなか、重要な指摘があふれている。
16日(土)、四日市で行われた、三重県公明党本部の賀詞交歓会に出席、参院選勝利に向けて挨拶をしました。比例区の浜田まさよし予定候補と、愛知県選挙区の里見りゅうじ予定候補も出席し、決意を述べました。
これに先立ち、鈴木英敬知事と懇談を行いました。また、今年5月には、ここ三重県で、「伊勢志摩サミット」が行われますが、その会場となる賢島(志摩市)や、国際メディアセンター(伊勢市)の視察を行いました。
17日(日)は、阪神・淡路大震災から21年となる日。地元では赤羽消防団の始式、団体の20周年行事、もちつき大会、町会の新年会など、多くの行事に参加しました。首都直下地震が切迫し、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しており、生業の傍ら地域の防災・減災に力を尽くして下さる消防団の方々に感謝です。