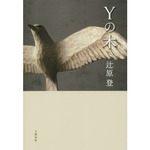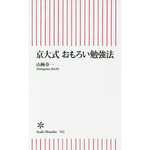 京大総長になっているのが、世界的なゴリラの研究者ということ自体が面白い。これは"勉強法"ではなく、人間学、人間論だ。サル、ゴリラ、人間――。ゴリラを通して人類の由来や人間とはどんな動物であるかが浮き彫りにされる。それに、アフリカの人たちとの付き合い、フィールドワークが付加され、対話や対人関係の術がいかに大事かを学ぶことができる。
京大総長になっているのが、世界的なゴリラの研究者ということ自体が面白い。これは"勉強法"ではなく、人間学、人間論だ。サル、ゴリラ、人間――。ゴリラを通して人類の由来や人間とはどんな動物であるかが浮き彫りにされる。それに、アフリカの人たちとの付き合い、フィールドワークが付加され、対話や対人関係の術がいかに大事かを学ぶことができる。
「"時間を切断してしまう"文明の利器」「"共にいる"関係を実らせてこそ幸福感」「ニホンザルとゴリラの目の合わせ方」「食事や会話は、対面を持続させる」「ゴシップが道徳をつくった(生の会話、うわさ話、雑談が大事で、文字情報だけで世界を判断しない)」「言葉より"構え"を磨け」「"分かち合って"食べる、飲む」「同調するなら、酒を飲め」「酒は"ケ"から"ハレ"へのスイッチ」「恋と動物」・・・・・・。
きわめてすぐれた人間学、人間論が自身の蓄積のなかで語られる。
22日、東京電力福島第一原発(福島県大熊町、双葉町)の構内を視察し、汚染水対策の進捗状況や作業員の労働環境を調査しました。
まず、防護服に着替え測量計を装着。高台から原子炉1~4号機を俯瞰した後、汚染水対策の切り札とされる「凍土遮水壁」の現場を視察しました。
同施設は、原子炉建屋周辺の地中を約1.5キロにわたって凍らせ、汚染地下水の発生量を大幅に減らそうというものです。この後、汚染地下水を汲み上げ、浄化後に海洋放出している「サブドレン計画」の運用状況を視察。さらに、今年10月に完成した全長約800メートルの「海側遮水壁」なども見て回りました。
来年3月11日で丸5年となります。廃炉に向けた各種作業が進められていますが、さらに取り組んでいかねばなりません。現在、現場の作業員は7000人に及んでおり、懸命な作業が続けられています。
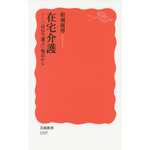 団塊の世代が75歳以上となる2025年問題。私はそれが80歳以上となる2030年問題がより深刻だと思うが、介護の問題は切羽詰まった段階に来ている。
団塊の世代が75歳以上となる2025年問題。私はそれが80歳以上となる2030年問題がより深刻だと思うが、介護の問題は切羽詰まった段階に来ている。
副題に「『自分で選ぶ』視点から」とあるように、介護の実態をわかりやすく説明している。「施設介護から在宅介護へ」は政府の大方針だが、施設も在宅介護も困難に直面している。「在宅介護の困難さ」「サ高住」「介護離職者10万人」「パラサイトシングル介護者の増加」「認知症高齢者の急増」「地域包括ケアシステム」「施設あっての在宅介護」「看護と介護(医療と介護の表裏一体)」「介護士不足」「介護保険制度の改正がもたらしているもの」「あるべき在宅介護と財源論」・・・・・・。
「介護」については、たしかにキメ細かく体制をとってきた。しかし、高齢者急増の大波に応える体制が財源的にも整えられない。医療も含めて"担い手"の不足がより深刻化している。さらにそもそも高齢者はどう生きていくか、生活していくか、という根源の問題が重くのしかかっていて厳しさを増している。裕福で人にも恵まれている高齢者は少ない。本書は現場の実態と「介護のあり方」の道筋を冷静に示している。
16日、与党の税制改正大綱が決定。17年4月から消費税率を10%に引き上げるのに合わせて「酒類、外食を除く食品全般と新聞の税率を8%に据え置く」という軽減税率の導入が決まりました。
「10%になっても、せめて食品は消費税を上げないでほしい」という庶民の願いが実現したものです。消費税は1%で約2.8兆円。従って2%で5.6兆円となり、約1兆円が軽減となります。この必要な財源については「『社会保障と税の一体改革』の原点に立ち、16年度末までに歳入および歳出における取り組みにより、与党の責任において、確実に安定的な恒久財源を確保する」としました。
高齢化が進むなか、社会保障費は急増しており、現在は消費税8%で約22.4兆円ですが、それではとても社会保障費はまかなえません。急増する社会保障の財源確保の為には、税制だけでなく経済全体の活性化(稼ぐこと)、行政改革などが重要です。団塊の世代が75歳以上となる2025年をはじめ、将来の日本のために更なる努力が必要です。