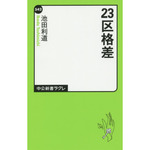 諸データで東京各区の違いを分析している。各区をランク付けするのは、いかがかと思うが、日本をけん引し、世界一の東京をめざしての役割分担として各区の特徴を考えてみるということだ。各区が独立してバラバラに競い合っている訳ではないからだ。
諸データで東京各区の違いを分析している。各区をランク付けするのは、いかがかと思うが、日本をけん引し、世界一の東京をめざしての役割分担として各区の特徴を考えてみるということだ。各区が独立してバラバラに競い合っている訳ではないからだ。
高齢化率、病院や大学の数、所得、子育てのための諸施策、防災・減災や犯罪抑止への努力、人口の増減や外国人の比率、1人暮らしの内容と現実・・・・・・。それぞれ提起される現実のデータはシビアだ。しかし、東京各区が懸命に努力しており、変化している。事実、そのデータも急速に変わってきている。「住」ということは、まさに○○区に住むことだが、「何かの縁」にふれることと、「住宅費」「交通の利便性」などがかなりの要素を占めると思う。私の住んだり、活動してきた北区、板橋区、足立区、文京区、台東区、中央区などは、個性も違うが、いずれもいい所だ。
 13日、新東名高速道路の浜松いなさジャンクションから豊田東ジャンクション間の約55kmが開通、愛知県内の新東名は全線開通となりました。このうち私の生まれ故郷である新城市での開通式に参加。新城市始まって以来の大きなイベントで、地元の多くの方々と喜びを共にしました。
13日、新東名高速道路の浜松いなさジャンクションから豊田東ジャンクション間の約55kmが開通、愛知県内の新東名は全線開通となりました。このうち私の生まれ故郷である新城市での開通式に参加。新城市始まって以来の大きなイベントで、地元の多くの方々と喜びを共にしました。
新城市といっても、全国的に知っている人が少ない小さな市ですが、発展への起爆力となることが期待されます。新城、豊橋、豊川、蒲郡、田原などの東三河地域は、世界第4位の自動車輸出入台数を取り扱う三河湾をはじめ、自動車関連企業も多く立地。農業でもキャベツ、柿やミカンなどの果物も豊富で、あさりの漁獲量も全国一。工業・農業・漁業などバランスのとれたポテンシャルの高い地域です。この新東名が、かつては田舎といわれた新城を走り、大きな変貌をみせています。大きな工場もすでに建ち始めました。
 観光面でも、あの長篠の古戦場の地域がジャンクションとなり、鳳来寺山や茶臼山の芝桜や中設楽の花祭りなど、奥三河の観光圏域が拡大します。インフラのストック効果は大きいものがあります。私の通った新城小学校などの児童とともに、テープカットをしました。
観光面でも、あの長篠の古戦場の地域がジャンクションとなり、鳳来寺山や茶臼山の芝桜や中設楽の花祭りなど、奥三河の観光圏域が拡大します。インフラのストック効果は大きいものがあります。私の通った新城小学校などの児童とともに、テープカットをしました。
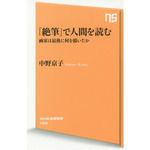 ゴヤの「我が子を喰らうサトゥルヌス」から最後の「俺はまだ学ぶぞ」、ミレーの絶筆「鳥の巣狩り」、ティツィアーノの絶筆「ピエタ」など、すさまじい気迫の絵画もあれば、色彩の艶は褪せ、無味乾燥の教科書のごときボッティチェリの「誹謗」、魂が抜け落ちたダヴィッドの「ヴィーナスに武器を解かれた軍神マルス」などの晩年の絵画もある。ボッティチェリ、ラファエロ、ブリューゲル、グレコ、ルーベンスからフェルメール、ゴッホに至るまでの15人の画家の「絶筆」に迫り、生きざまを剔り出す。「畢竟、芸術作品は、産み出した本人を語るものだから」と中野さんはいう。
ゴヤの「我が子を喰らうサトゥルヌス」から最後の「俺はまだ学ぶぞ」、ミレーの絶筆「鳥の巣狩り」、ティツィアーノの絶筆「ピエタ」など、すさまじい気迫の絵画もあれば、色彩の艶は褪せ、無味乾燥の教科書のごときボッティチェリの「誹謗」、魂が抜け落ちたダヴィッドの「ヴィーナスに武器を解かれた軍神マルス」などの晩年の絵画もある。ボッティチェリ、ラファエロ、ブリューゲル、グレコ、ルーベンスからフェルメール、ゴッホに至るまでの15人の画家の「絶筆」に迫り、生きざまを剔り出す。「畢竟、芸術作品は、産み出した本人を語るものだから」と中野さんはいう。
「明治時代に西洋文化を積極的に学び始めた日本は、ちょうどそのころ大人気を博していた印象派作品を、絵画の手本と思ってしまった節がある。・・・・・・それは長い絵画史におけるほんの最近の潮流にすぎない。西欧絵画はまず神とともにあり、王侯の嗜好とともにあり、時代ごとの民衆の生活とともにあった」・・・・・・。中野京子さんの著作にはいつも引き込まれる。
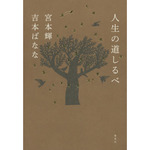 宮本輝・吉本ばななの対談。実にいい対談となっている。「ばななさんの小説には、下卑た人間、嫌なやつってあんまり出ていないんです」「文学というのは、自分の小さな庭で丹精して育てた花を、一輪、一輪、道行く人に差し上げる仕事なのではないか――。現実世界は、理不尽で大変なことばかりだからこそ、せめて小説の世界では、心根のきれいな人々を書きたいと。書き手の心構えとして、その点は、ばななさんとも通底するんじゃないですか」ということから対談が始まっている。
宮本輝・吉本ばななの対談。実にいい対談となっている。「ばななさんの小説には、下卑た人間、嫌なやつってあんまり出ていないんです」「文学というのは、自分の小さな庭で丹精して育てた花を、一輪、一輪、道行く人に差し上げる仕事なのではないか――。現実世界は、理不尽で大変なことばかりだからこそ、せめて小説の世界では、心根のきれいな人々を書きたいと。書き手の心構えとして、その点は、ばななさんとも通底するんじゃないですか」ということから対談が始まっている。
誰もが実は直面している日常の生老病死。生きて死んでいくことをどう捉えるか、そのなかでの幸福をどう捉えるか。有無の二の語も及ばず、断常の二見を越える世界を如実知見する生命力――そんな語らいが続く。宮本輝の最新作「田園発 港行き自転車」で私は、「縁の世界」と「肯定の世界」を感じたが、「小説の世界では、心根のきれいな人々を書きたい」(宮本輝)、「輝先生の小説を読むと、気持ちが大らかに、優しくなるのかもしれません。人生を肯定したくなるんですね」(吉本ばなな)という言葉で、対談は結ばれている。
 今年は参院選が焦点ですが、統一外の地方選挙が毎週のように行われています。
今年は参院選が焦点ですが、統一外の地方選挙が毎週のように行われています。
埼玉県新座市議選(定数26)が7日に告示され、公明党から7候補が出馬。勝利めざし、懸命の選挙戦が始まりました。
寒風をついての選挙戦ですが、多くの方々から声援をいただき、感謝です。
私は告示日のこの日、新座市議選への応援にかけつけ、志木駅南口などで各候補の応援演説を行いました。「政治は結果。現場の声を徹底して聞き、困っている人を助ける のが公明党だ」「公明党がいるから安心だ!とよくいわれるが、国政においても連立政権のブレーキ、アクセル役を的確に努めたい」と訴えました。
のが公明党だ」「公明党がいるから安心だ!とよくいわれるが、国政においても連立政権のブレーキ、アクセル役を的確に努めたい」と訴えました。
地元の北区、足立区では、餅つきや餃子パーティなど多くの行事に参加、懇談しました。

