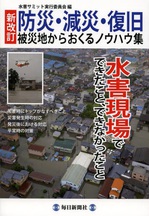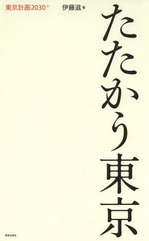「イラン革命(1979年2月)」「マッカのマスジド・ハラーム占拠事件(1979年11月)」「ソ連のアフガニスタン侵攻(1979年末)とそれに対するムジャーヒディーン(ムスリム戦士)のレジスタンス形成」「ジハード団によるエジプト、サダト大統領暗殺(1981年10月)」は、19世紀以降の欧米による植民地化、つまり政教分離の西欧自由民主主義と無神論の共産主義によって、イスラームをはじめとした宗教が政治から締め出されていたことに対する「イスラームの国際政治への再登場」を告げるものだという。そしてエジプトとチュニジアで民衆が政権を奪取した2010年の「アラブの春」――。その後の混迷はそうした世界史的文脈の深化の不十分さにあるという。
イスラーム世界は約16億の人口を抱え、若者も多い。世界の石油埋蔵量の約4分の3を有し、天然資源も豊富で、砂漠ばかりではなく東南アジアやアフリカには豊かな農地が広がる。「世界のグローバル化はアメリカ主導であり、世界のフラット化、単一市場化をめざしている」という内田さんと中田さんは、もう一つのグローバル共同体であるイスラーム共同体との衝突に帰結することを指摘する。「貨幣ベース・市場ベース」のアメリカン・グローバリズムに対して、カリフ制を「生身の人間ベース」と見る。
「イスラーム、キリスト教、ユダヤ教」と副題にあるが、「砂漠、遊牧文化、決断のリーダーシップ、歓待の文化」と「農耕、定住文化、合意のリーダーシップ、断る文化」を対置する。「一神教の特徴を見分けるポイントは、遊牧民の宗教か定住民の宗教か、ということ」という。当然、日本人は典型的な定住の農耕民だ。今では全く別々の宗教になっているユダヤ教、キリスト教、イスラームの三つの一神教だが、そのルーツは同じ中東の砂漠で、同じ唯一絶対の神を戴いて成立した兄弟のような宗教だが、そこに築かれた国家とグローバリズムの現実を、対談のなかで浮き彫りにしている。
4月19日、静岡県浜松市から愛知県新城市、豊橋市の東三河地方に行き、道路、港湾のインフラ整備の状況や地域産業の状況を視察。川勝平太静岡県知事、大村秀章愛知県知事をはじめ地域の市町村長、経済界の代表者の方々と、地域の課題や発展の方向性について意見交換しました。
「三遠南信を道路でつないで発展させよう」「2年前に浜松まで通った新東名が来年は豊田市までつながる。東三河は更に発展のチャンスを迎える」「2027年には長野県の南信の飯田市にリニアの駅ができる。東三河と静岡県遠州、豊橋と浜松と飯田の三遠南信は一変する」――。この日に会った両知事や浜松、豊橋、豊川、蒲郡、新城、田原の各市長、設楽、東栄、豊根の各町村長、そして各商工会議所や商工会の方々から、未来に向けての意欲的発言が相次ぎました。
私の生まれ育った新城市や豊橋市は今、変貌の大チャンスを迎えています。トヨタなどの製造業、外国からの輸入車の陸揚げ日本一の三河港、農業生産額全国一、良質な果物生産、気候の良さや交通の利便性、豊富な観光資源など、大きなポテンシャルをもつバランスのとれた地域となっています。
各市町村の連携と未来に向けて大きな構想力(防災の角度も加えた)をもった地域づくりが大切ですが、しっかりと支援していきたいと思います。
きわめて貴重な重要な本となっている。2005年にスタートした水害サミットの証言・提言集だ。被災地の首長さんが体験に基づいて「水害現場でできたこと、できなかったこと」を実践的に述べたことをまとめたもの。私も昨年の「第9回水害サミット」に参加した。
「災害時にトップがなすべきこと」「災害発生時の対応」「発災後における対応」「平常時の対策」等をまとめているが、集約すれば「序論 災害時にトップがなすべきこと 11項目」となる。
1.「命を守る」ということを最優先し、避難勧告を躊躇してはならない
2.判断の遅れは命取りになる。トップの決断を早くすること
3.人は逃げないものであることを知っておくこと(人を逃がすための工夫)
4.ボランティアセンターをすぐ立ち上げること
5.住民はトップを見ている。トップは住民の前に、マスコミの前に全力で働いている姿を見せること
6.住民の苦しみや悲しみを、トップはよく理解していることを伝えること
7.記者会見を毎日定時に行い、情報を出し続けること
8.大量のゴミ対策を
9.お金のことは後で何とかなる。やるべきことは全てやれ
10.視察は嫌がらずに受け入れること(現場を見た人は必ず味方になる)
11.応援・救援に来てくれた人に感謝の言葉を伝え続けること
避難勧告、指示など、「どう住民に危機を伝え、的確な指示を出せるか」ということで苦労してきた首長たちの珠玉の生の声、現場の声があふれている。良書。
東京計画2030+。2030年の東京都心市街地像。激しい世界の巨大都市間競争のなかで、東京の誇れる人材と資産を活かし、世界から「人・モノ・カネ」を呼び込む。東京23区の生産年齢人口がピークとなり、減少し始める2030年までに、世界があこがれる首都・東京をめざし勝ち抜こう! まさに「たたかう東京」だ。
7つの計画を示す。「山手線内の安全市街地化」「都市部の高容積化(都心市街地のエリア区分)」「国際居住区の指定(都心周辺部に)」「羽田空港第5、第6滑走路と地下鉄新線の整備(首都高の再構築・地下化も)」「リニア中央新幹線と品川地域再開発の融合」「江戸東京商店街のルネッサンス」「臨海部・アミューズメント国際特区の推進」――。土地利用、交通、防災、環境、エネルギー、法制度、マネジメントを広範囲に入れ込んだ「現実的な都市計画像」を示している。
"Invest Tokyo""Visit Tokyo"として、東京が老いる前に、力と魅力ある、世界一の都市・東京へ向けての意欲が伝わってくる。
12日、穏やかな晴天のなか、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」が新宿御苑で行われました。
遅咲きの八重桜が満開のなか、各界から招待された約1万4千人の方が集まり、歓談をしました。参加者の明るい姿が印象的でした。安倍首相も「今年は景気回復の実感を全国津々浦々に届けることだ」と、経済活性化への決意を述べました。
「中小企業にも景気回復が実感できるように頑張ってください」「私の県もよろしくお願いします」「素晴らしい天気で良かった」など、多くの声をいただきました。
またその後、都内で行われた少年少女空手道選手権大会に出席し、北海道から沖縄までと海外14カ国の子どもたちが一堂に介し、盛大に行われました。
私は「各流派の垣根をこえて、国の垣根をこえて、心の垣根を打ち破って、世界の選手と一緒に見事な大会にしてください」と挨拶をしました。