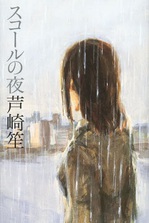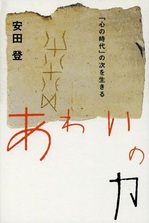ドストエフスキーの巨大さ、偉大さは「人間とは何か」の問いに全精神力を傾注して、人間実存にひそむ深淵を明るみに出した点にある。「地下生活者の手記」「罪と罰」「悪霊」「カラマーゾフ兄弟」は、悪徳の跳梁する事件の人間心理の日常性をはるかに越え、人間の業、霊性の深奥の次元から人間実存の深刻な問題性を意識させる。「ロシア最大の形而上学者」(ベルジャーエフ)といわれるゆえんだ。
本書では、まず「人間学―社会主義社会の蟻塚と人間的自由」を示す。そこには「神と人間」の苦痛に満ちた問題が常にあり、当時ロシアを風靡する人間理性に基づく科学的、合理主義的ないし功利主義的世界観とそこにふくまれる人間観への批判がある。人間は非合理的存在であり、その主要な目的は、自分自身の恣意によって生きること、自由な意志にある。「功利主義者、実証主義者、科学的社会主義の理論家たち――ベンサムやコントやマルクスたちが提示する理想社会の青写真は眺めている場合にだけ美しいのであり・・・・・・"蟻塚"にすぎず、住まうのは人間ではなくて畜群」なのだという。
その自由探究の途は、背徳とニヒリズムへの"人神"に導くことを、キリーロフやラスコーリニコフ、イワン、カラマーゾフたちの悲劇の人物として描く。「神がなければ全ては許される」――神と最高善とに対する叛逆の途だ。イワンらの悲劇的運命を通して、バクーニンやシュティルナー的無神論の陥弄を暴露している。それは大審問官の「自由(天上のパン)と地上のパン」「人類愛が人間蔑視に堕すこと」「自由の重荷」「従順な畜群と全体主義的権力」に凝縮される。「神と人間」の問題だけではなく、無神論的社会主義、さらにはスターリンの独裁、ナチズムの心理構造としてのエーリッヒ・フロムの「自由からの逃走」へと連なるものだ。全体主義的民主主義の精神的弁証法を指摘したニーチェ、民衆にやさしく、ていねいで、人道的な全体主義的福祉国家が民衆を幼年のままにおく民主政治の危険性を指摘したトクヴィル――ドストエフスキーは早々と世俗的・自然的ヒューマニズムの陥る袋小路を摘発したのだ。「悪霊」の人神、キリーロフはニーチェの哲学を先取りしていることは明らかだ。
神を見失った現代人は、神なき世界のなかで、その空虚を満たすべく一時の思想や理論をあみ出し、また思考停止に日常を委ねている。本書は1968年に書かれた。哲学不在、問うことさえかき消された今日だが、昨年は、ニーチェが静かなるブームを呼んだという。その意味でも本書の意義は大きい。驚嘆すべき力作。
5月10日、11日の2日間にわたり、北海道の札幌、苫小牧、函館、白老などに行き、空港のWi-Fi設置、苫小牧港、道路整備や函館への北海道新幹線の新駅建設現場、アイヌ民族博物館、観光施設を視察。また、高橋はるみ北海道知事をはじめ、地元の市町村長、経済界の代表者の方々と北海道の活性化や今後の発展に向けた具体的な方策、課題等について要請を受け、意見交換をしました。
「北海道は、観光、農業、水産業など高いポテンシャルをもっている。そのためにもインフラを整備してほしい」「札幌への新幹線を前倒ししてほしい」「苫小牧港は北海道の外国向けコンテナ貨物の約7割を取り扱っている。北極海航路の拡大など国際物流が大きく動き出しており、今後さらに重要な国際物流拠点となる」「平成28年春に北海道新幹線が開業すると東京から函館に4時間10分で到着する。歴史と文化、豊かな食を有する函館の観光を大きく拡大できる」「白老町に民族共生の象徴となる空間をつくり、アイヌ文化を世界に発信したい」――。関係者からは意欲的な提案と要請がなされました。
また、JR北海道本社を訪問し、経営陣に対し「4月から新しい会長、社長の体制となり、安全第一の鉄道として再生に力を注いで欲しい」と話しました。
北海道の活性化と発展のため、現地と良く連携して戦略的に取り組んでいきます。
都市銀行トップのメガバンクに女性総合職一期生として入行した吉沢環が、女性初の本店管理職に抜擢された。その任務は利益供与や不祥事隠しの隠れ蓑にされてきた子会社の清算。しかも、背後には、経営幹部の派閥抗争があり、女性への偏見や差別が渦巻く。
「たしかに純粋にひとつの目的のために行われている仕事なんて探しても見つからないかもしれない。どんな仕事も不純な目的や割り切れないしがらみをなにがしか抱えながら進んでいる」――。清算という厳しい仕事を終え、主人公はカンボジア地雷除去のNGOに参加する。数メートル先も見えないスコールを浴び「いっそこのまま異国のスコールに身を委ねて20年の間に全身にこびりついた組織の垢をすべて洗い流してしまいたい」と思う。
仕事とは。組織の中で働くとは。女性と仕事とは。ハデなドラマ仕立てでないゆえに、その苦悩がリアルに迫ってくる。財務省現役キャリアが書いた第5回日経小説大賞受賞作。
「心の時代」の次を生きる、と副題にある。安田さんは能楽師でワキ方。「能楽師は、己の身体を駆使して舞い、身体の底から声を出して謡う。・・・・・・古来の日本語には"脳"だけではとても捉えきれない豊かな広がりと奥行き、彩りや香りがあり、身体的な感覚を使って、はじめて感じ取ることができる」「笛は師匠から弟子へと代々受け継がれた名管ですが、・・・・・・しばらくはまったく音が鳴らない。息を吹き続け何年か経つと音が鳴り始める。それも師匠そっくりの音が・・・・・・。能の謡もまったく"声が出ない"。身体という"道具"の師匠と弟子の伝授。"声が出る"ようになった瞬間を今でも鮮明に覚えている」という驚くべきことから本書は始まる。
己と他者、異界と現実、時間と空間、あっちとこっちをつなぐ間(あわい)の存在。そしてその媒介。人は身体という「あわい」を通して外の世界とつながる。現代は、「異界」と出会う場を奪われた時代だ。知識、実学、見えるもののみに奪われ、「見えないもの」を浮かび上がらせることができない世界と化している。「現代に"異界"を取り戻し、その"異界"から新しいものを生み出していくためには、"何もない""何も与えない"時間や空間をつくることが大切だ」「人生をつらくしてしまう傾向にプログラムされた現代。これこそ"心のしわざ"だ。その"心"から自由になってみてはいかが」という。
有と無、有限と無限、"からだ"と"こころ"、宇宙と我、そして祈りと呪術――世阿弥は「離見の見」として我欲、我見から離れることを示したというが、安田さんは「心がなかった時代の内臓感覚」「無限と有限をつなぐ"あわい"」「見えないものを見る力」などを開示しつつ、西行、定家、芭蕉などの境地を見せてくれる。感銘した。
なつかしいZ会の機関紙に「こころの物語」と題して加地伸行先生が語った連載。利己主義、個人主義、家族主義について繰り返し、説かれる。
「個人主義者とは、自律・自立し、自己責任をもって自己決断する人のことである。一方、利己主義者は己のためにだけ行動する人である。何もだれも信じない。信じるのは、自己と金銭財物だけである。ただし個人主義的生き方はなかなか難しい」「そこでキリスト教の神(唯一最高・絶対者)が、内面的に個人主義とつながり、崩れようとするときの抑止力となっていったのである」。「こうしたキリスト教的世界と異なり、日本・朝鮮・中国という儒教的世界では、個人主義は生まれず、家族主義ひいては一族主義をすぐれた生きかたとした」。
そこで家族の思想に貫かれる無償の愛を説き示す。「無償の愛がないから他人」「日本人を変質させた"個人主義のものまね"」「他者への無償の愛、すなわち友情」「教養人(君子)であれ、知識人(小人)にはなるな」。「沈黙の宗教――儒教」「家族の思想」「論語」の大家・加地先生が易しく、繰り返し、青年たちに語っている。