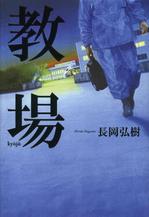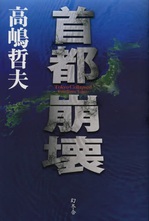3月22日は「世界水の日」。それを記念して21日、都内青山の国連大学で開催された式典に出席し、基調講演を行いました。
「世界水の日」は国連総会で決定され、毎年世界で水に関する活動が展開されていますが、国連の式典が日本で開催されるのは今回が初めてです。式典には皇太子殿下のご臨席を賜り、海外からの参加者を含む約300名が出席。「水とエネルギーのつながり」をテーマにスピーチや議論が行われました。
皇太子殿下のお言葉をいただいた後、私が講演。洪水や津波、渇水など水に関わる自然災害が頻発する我が国で、古くから「無常」や「常住」の思想が生まれたことに触れながら、独自の水文化や技術が育まれたことを紹介しました。特に、「川をなだめ」「自然と折り合い」ながら発展してきた共生の治水技術や、水道から直接おいしい水を飲むことができることなど、我が国の水技術の展開を説明。「我が国の技術を活用して、世界の水問題解決に取り組む」と決意を表明しました。
その後の議論では、ジャロー・UN-WATER(国連水関連機関調整委員会)議長から、「環境、エネルギー、食糧、そして水関連の災害など包括的な水のガバナンスが必要。それができるのが日本だ」と強い期待が表明。ルワンダ、タジキスタン、ドイツの参加者からは各国の水事情や行政の取り組みが披露されました。
世界の水問題を共に考えるとともに、我が国の優れた技術を世界に示すいい機会ともなりました。
【2014年世界水の日の太田国土交通大臣基調講演 要旨】
世界水の日開催への祝辞
○マローン国連大学学長、ジャローUN-WATER議長、そして世界各国から、本日の国連世界水の日の式典にご参加いただいた皆様に、心から歓迎を申し上げます。
○また、本式典が、皇太子殿下のご臨席のもと開催されますことを、お慶び申し上げますとともに、この地東京での開催にご尽力されました国連並びに関係者の皆様に、厚くお礼申し上げます。
○そして、我が国に未曾有の被害をもたらしました東日本大震災から、3年経ちました。この間、復旧・復興のために、世界各国の皆様から温かいご支援を頂いていることに深く感謝申し上げます。
○国連がこれまで「世界水の日」に、水と人との関わりの様々な側面に焦点をあててきたことは、大変意義あることと認識しております。今年の「水とエネルギーのつながり」も、水に関する施策を進める上で重要なテーマとして注目されるべきものと考えます。
○本日ご列席の皆様は、世界で水に係わる様々な問題に取り組まれている方々や、水問題に関心の深い方々であり、我が国の水行政を担当する立場として、お話しをする機会を得たことは大変光栄に存じます。
大相撲の朝稽古――私が想起したのは、未知の厳しい世界に飛び込んだ若者たちの不安と絶望と、かすかな光を求める背水の陣からくる緊張感、闘争心だ。警察学校は新入社員の研修よりもはるかに厳しい「警察官としての資質に欠ける学生を、早い段階ではじき出すための篩」だという。
不安と緊張の半年に及ぶ合宿生活――。そこには未熟(経験不足)、嫉妬、誤解、競争、挫折、裏切りもあるが、それが修羅場と化す社会の現実であることを突き付ける。その荒砂で揉むがごとき教場で、じっと見つめる白髪の教官・風間は教師というより師匠だ。
人間を鍛え、育てるとはどういうことか。あえて突き放したり、情愛で包んだり・・・・・・。学園ものの小説を装っているが、厳父の愛、とくに師匠がいかに人間を育て、鍛えることにおいて大切かという「師弟」に魅力を感じた。ところで表紙の指紋は長岡さんのものだろうか。
17日、ベトナムのチュオン・タン・サン国家主席が来日し、宮中晩餐会など、国賓としての諸行事が行われました。また、国家主席に同行し来日したディン・ラー・タン交通運輸大臣が、国土交通省を訪れ、会談をしました。タン大臣とは、昨年9月に東京で開催されたAPEC交通大臣会合、同月の私のベトナム訪問、昨年暮れの日・ASEAN40周年特別首脳会談ガラディナー、今回と半年の間に4回目の会談となります。
ベトナムでは、日本との貿易額が増大しており、特にインフラ輸出が進んでいます。具体的なインフラプロジェクトとしては、ハノイ・ホーチミンを結ぶ高速道路や高速鉄道、ハノイ近郊のラックフェン港、ホーチミン近郊のロンタイン新国際空港、ハノイ市内のニャッタン橋(日越友好橋)の整備などが進展しています。タン大臣との会談では、各プロジェクトの具体的な進捗状況を確認したほか、「地方は川を渡ることに苦労している。橋の建設を進めたい。協力して欲しい」などの要請も受けました。
ベトナムとの協力関係の強化が進んでいます。
大災害に備えるには科学的想像力がいる。そして危機を察知したなら間髪をおかずに実行することだ。失敗学からいえば、必ず人間は「まあ今やらなくても」「何とかなるのではないか」と安易な方向に流れるからだ。
私も繰り返し言っているが、1755年、リスボンが津波に襲われ、それがポルトガルの時代の終わりを告げたことを絶対に忘れてはならない。本書の焦点は首都直下地震。それも東日本大震災によって首都直下の地層に乱れが生じている。何度も地震が発生して、頻度を増しつつ、マグニチュード8級に至るということ。加えて、日本国債が売られ、円の価値は急落し、株は暴落する。国内の銀行、証券までが円、国債売りに走る。それを狙っている諸勢力が世界にいる。日本は壊滅する――。そうした想定を高嶋さんは、小説で描く。しかも国交省がその中心舞台となる。その首都崩壊、日本崩壊を食い止めるのが、首都移転の短期間での断行という設定だ。
首都直下型地震は必ず来る!それによって1929年をはるかに上回る世界大恐慌が起こる――それをどう食い止めるかを考えさせる。