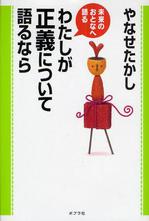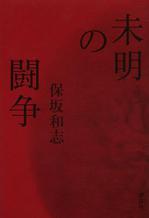2月に入り連日、補正予算の審議があり、今は衆議院で来年度予算の審議が続いています。豪雪、災害、建設業の執行状況、若い人の担い手確保の取組み、観光や東京オリンピック・パラリンピックへの備えなど、国土交通省の所管する分野は幅広いだけに、答弁する機会が多くあります。
本日19日、衆議院国土交通委員会が今年初めて行われ、国土交通行政についての所信表明を行いました。また、ラオスのソマート・ポンセナー公共事業・運輸大臣と会談しました。会談では、インフラ整備、建築技術、航空、観光、技術交流や人材育成等について意見交換を行い、2間関係を一層緊密化していくことを確認しました。
これから予算委員会や国土交通委員会が連日のように行われますが、しっかり答え、国民の皆様の理解が得られるようにしたいと思います。
頑張ります。
 「21世紀の対話」(池田大作・トインビー対談)が刊行されて約40年。世界で28言語に翻訳出版されたこの対談を、佐藤優さんが今こそ必要な哲学として鮮やかに解き明かす。本書にあるのは生命の尊厳の人間哲学だ。
「21世紀の対話」(池田大作・トインビー対談)が刊行されて約40年。世界で28言語に翻訳出版されたこの対談を、佐藤優さんが今こそ必要な哲学として鮮やかに解き明かす。本書にあるのは生命の尊厳の人間哲学だ。
佐藤さんは現代社会の迷妄はリーダーたちの「思想の欠如」にあると見る。現代社会の浅薄さは「哲学の不在」にあることは間違いないが、その哲学は現実に根ざし、行動を伴なって初めて意味をもつ。本書は「価値を創り出す理性的直観の力」「宗教と科学」「ニヒリズムの超克」「正義について」「労働の哲学」「一神教と汎神教への考察」「愛と慈悲」「生命の尊厳」など、佐藤さんが対談のなかから抽出して、21世紀の今こそ、この対談がその光を放つと解説する。
やなせたかしさんが今年亡くなった。「手のひらを太陽に」は今も歌われ、「それいけ!アンパンマン」は毎日、朝のBSで放映されている。いばらず、自慢せず、「人生の楽しみの中で最大最高のものは、やはり人を喜ばせることでしょう。すべての芸術、文化は人を喜ばせたいということが原点で、喜ばせごっこをしながら、原則的には愛別離苦、さよならだけの寂しげな人生をごまかしながら生きている」「ぼくは怒るよりも笑いたい」「愛と勇気だけが友達さ、とアンパンマンのマーチでいっている」と語る。
キャラクターをつくる大変さと工夫。スーパーマンと違ってアンパンマンは弱点をもったヒーローだ。しかし、少し優等生。一方ばいきんまんは結構人気がある。どこかガキ大将とか、不良とか、片目の海賊とか愛嬌のある悪人も素適だとウケることがある。
本書の第一章は「正義の味方って本当にかっこいい?」と、?から始まっている。
小説は物語、ストーリーの面白さと思っていたが、この「未明の闘争」は全く違う。あるのは生命の流れだ。その生命の流れが次々と絵巻物のように、しかも時空を飛んで連続する。記憶をエピソードとしてまとめず、自由に生命のおもむくまま飛ばす。思ったのは仏法の法概念。「法とは水(サンズイ)が去ると書くが、目の前の水は既に今あった水ではなく去っていく。しかし目の前の水は常に厳然と絶え間なく流れゆく。無常と常住の十字路に今の瞬間を位置づける。それが中道の生命である」――。その諸法実相の世界を時空を越えて描いたのだと思う。死んだ友人が目の前に現われたり、子供の頃の思い出が突然出てきたり、音楽や哲学がサッと現われたり、家族同然の猫の生老病死が語られたりする。しかもどれも温かい。
「人生の時間の流れに出遭いや出来事が点在するのではなく、出遭いや出来事が起きるそのつどそのつど人生の時間の流れが起こる」「現在とは何十年前であろうと、それを現在状態たらしめようとする記憶装置なんだ」「ジョジョは突然、"アオーン!アオーン!"とカン高い声で激しく鳴きながら、二階に向かって階段を駆け上がった。いまボッコの魂が去ってゆくのがジョジョにわかってそれを追いかけた」・・・・・・。「私は一週間前に死んだ篠島が歩いていた」という冒頭の一節から、定番とは違う世界にいきなり誘い込まれた。
「しまなみ海道」を走る自転車の通行無料化が大きく前進しました。「しまなみ海道」は、広島県と愛媛県の間を、瀬戸内海に浮かぶ多くの島々に橋を架けて結ぶ本四連絡橋。地元では「しまなみ海道」という愛称で呼んでいます。橋の部分には自転車と歩行者の専用道が設けられており、美しい海と島々が織り成す景色を眺めながらわたることができます。
2月6日、広島県の湯崎英彦知事、愛媛県の中村時広知事が国土交通大臣室に来られ、「しまなみ海道」の自転車通行料金の無料化について要請を受けて意見交換しました。
「しまなみ海道」は、自転車で瀬戸内海を横断できる唯一のルート。サイクリング愛好者のメッカとして多くの人が集まる国内でも貴重な観光資源です。昨年10月には、国内外から約2500人のサイクリストが参加した大会が盛大に開催されるなど、地元が主体となってサイクリングを核にした地域づくり・観光振興の機運が盛り上がっています。
両知事から、全ルートを自転車で走ると500円かかる料金を無料化する要請を受け、私は「観光資源として極めて有効。両県も努力している。実現に向けて調整する」と方針を示しました。無料化によってさらなる知名度アップと観光客の増加が期待されます。
無料化はこれまで両県の悲願だっただけに、両県知事から明るく感謝の言葉がありました。