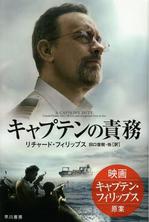「リーダー篇」「国家と歴史篇」に続く第三弾、民主党政権の始まりから安倍政権誕生までの期間の42本。日本の"決められない政治"、3.11東日本大震災、そしてユーロ危機、モンティ内閣・・・・・・。イタリア(文明と文化の欧州)と日本と古代ローマを踏まえた深き思索とゆるぎなき視点が開示される。
「リーダー篇」「国家と歴史篇」に続く第三弾、民主党政権の始まりから安倍政権誕生までの期間の42本。日本の"決められない政治"、3.11東日本大震災、そしてユーロ危機、モンティ内閣・・・・・・。イタリア(文明と文化の欧州)と日本と古代ローマを踏まえた深き思索とゆるぎなき視点が開示される。
「明治維新が成功したのは、維新の志士たちも反対側にいた勝海舟もイデオロギー不在であったからだと、私は思っている。・・・・・・彼らを動かしたのは、危機意識であった。・・・・・・イデオロギーは人々を分裂させるが、危機意識は団結させる」「(永井陽之助のアメリカでのジョーク『世界に絶対ないものが4つある。アメリカ人の哲学者、イギリス人のクラシック作曲家、ドイツ人のコメディアン、日本人のプレイボーイ』を引いて)日本人は、馬鹿正直でお人よしで世間知らずで、それでも日本人同士ならば充分にやっていけるので、悪知恵を働かせる必要に目覚めないのだろう(他国人となると通用しにくくなる)」「(日本人は)入社試験に限らず、拒絶されるということへの反応が過剰すぎると思える(政治家も、就職も、安定志向の社会も)。・・・・・・どうにかなりますよ」「人間は、不幸なときこそ真価が問われるのだし、予期していなかった事態にどう対処するかに、その人の気概が表われるのだ」「指導者に求められる資質は次の5つである。知力。説得力。肉体上の耐久力。自己制御の能力。持続する意志。ユリウス・カエサルだけが、このすべてを持っていた」「寄って立つ支柱がなければ生きてこられなかった人は、その支柱が倒されても必ず別の支柱を求めるようになる」「権力自体は悪ではないのだ。リーダーを自覚できない人間が権力者であった場合にのみ、権力は悪に変わる(そうしたリーダーを選ぶな)」「衆愚政にだけは向かわないように。一人一人が愚かになった訳ではなく、一人一人が以前より声をあげ始めた結果ではないか。加えて、これら多種多様になること必定の民意を整理し、最優先事項を見きわめ、何ゆえにこれが最優先かを有権者たちへ説得した後に実行するという、冷徹で勇気ある指導者を欠いていたのではないか」・・・・・・。考えること大であった。
 この秋一番の小春日和となった16日と17日、北区において、第14回全国新選組サミットが開催されました。
この秋一番の小春日和となった16日と17日、北区において、第14回全国新選組サミットが開催されました。
近藤勇、土方歳三の墓がJR板橋駅滝野川口(東口)にあり、新選組まつりが行われるようになって11年。今年は滝野川新選組まつり実行委員会が主催して、全国サミット開催となりました。
今年は新選組が誕生(1863年)して150周年、また慶応4年(1868年)4月25日に板橋の一里塚で斬首処刑された近藤勇の墓を今の板橋駅前に造立した永倉新八の100周忌です。
16日には150周年記念事業パレードが小石川・伝通院から板橋駅東口広場まで行われ、夜には北とぴあで交流会がもたれ、私も参加しました。
この交流会には、東京の日野、茨城、岡山、埼玉、福島、岩手など、各地にある新選組にちなんだ団体も結集。岡山県からは、なんと永倉(長倉)新八の4代~6代の子孫も参加して下さり、大いに盛り上がりました。 塩野七生氏が最新の著作「日本人へ 危機からの脱出」で言っているように、明治維新はイデオロギーではなく、日本人の危機意識によって成功した。「彼らを動かしたのは危機意識であった。・・・イデオロギーは人々を分裂させるが、危機意識は団結させる」ーー。
塩野七生氏が最新の著作「日本人へ 危機からの脱出」で言っているように、明治維新はイデオロギーではなく、日本人の危機意識によって成功した。「彼らを動かしたのは危機意識であった。・・・イデオロギーは人々を分裂させるが、危機意識は団結させる」ーー。
この二日間、全国の多くの新選組ファンや仲間たちが北区滝野川に集まりました。
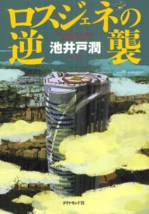 半沢直樹――「顧客を優先し、自らの地位さえ顧みない肝のすわった仕事ぶり。知恵と努力で相手を上回り、僅かな糸口から事態を逆転に導く手腕」「どんな場所であっても、また大銀行の看板を失っても輝く人材こそ本物だ。真に優秀な人材とはそういうものなんじゃないか」「自らのサラリーマン人生を賭した。その結果、どんな事態が降りかかろうとも、半沢は決して後悔などしない。その信念と、潔さこそ、半沢直樹という男の真骨頂だ」「人事が怖くてサラリーマンが務まるか」......。
半沢直樹――「顧客を優先し、自らの地位さえ顧みない肝のすわった仕事ぶり。知恵と努力で相手を上回り、僅かな糸口から事態を逆転に導く手腕」「どんな場所であっても、また大銀行の看板を失っても輝く人材こそ本物だ。真に優秀な人材とはそういうものなんじゃないか」「自らのサラリーマン人生を賭した。その結果、どんな事態が降りかかろうとも、半沢は決して後悔などしない。その信念と、潔さこそ、半沢直樹という男の真骨頂だ」「人事が怖くてサラリーマンが務まるか」......。
東京セントラル証券に無念の出向となった半沢はIT企業の買収を担当する。そこに立ちふさがったのが、なんと親会社の東京中央銀行だった。団塊の世代、バブル世代、ロスジェネ世代。それぞれに社会と組織の見方は確かに違うが、それをグチるのではなく、世代を突き抜けて戦え――半沢の魅力が本著でもあふれ出ている。半沢直樹シリーズの最新作。
 11月13日、長野県飯田市の牧野光朗市長が国土交通大臣室に来られ、要請を受けました。飯田市はリニア中央新幹線の駅が設置される予定。2027年の開業に向けて道路整備など地域の課題について、意見交換しました。
11月13日、長野県飯田市の牧野光朗市長が国土交通大臣室に来られ、要請を受けました。飯田市はリニア中央新幹線の駅が設置される予定。2027年の開業に向けて道路整備など地域の課題について、意見交換しました。
その際、飯田東中学校の生徒さんからのリンゴをいただきました。真っ赤で甘い香りがするリンゴです。今年は、昭和28年にリンゴ並木が植樹されて60周年。リンゴ並木は飯田市のシンボルになっています。私は中学3年の豊橋市立青陵中学校の生徒会長の時、このリンゴ並木の話に感動し、地元に夏ミカン並木を提案し、実現しました。その後、それが縁で、両校で姉妹校の交流も始まりました。
生徒さんから直筆の手紙もいただき、感激しました。本当にうれしい中学生からの真心の贈りものでした。