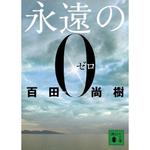 あの戦争はいかなるものであったのか。あの戦争の最前線はいかなるものだったのか。命がけの最前線を知らぬ者が、命令を下す側に立った時、いかに過ちを犯し、いかに逡巡し、支離滅裂なものになり果てるのか。現場を知らぬエリートとマスコミがいかに悲劇を生み出すか。百田尚樹さんの「永遠の0(ゼロ)」は、真珠湾、ミッドウェー、ラバウル、ガダルカナル、沖縄の戦いの最前線を、世界に轟く名戦闘機"零戦"に乗る「臆病者」「命を惜しむ男」「人間としての尊厳と愛を貫いた男」「妻子のために生きて帰ることを約束した倫たる男」である熟練の宮部久蔵の心中に迫ることによって描く。その男がなぜ特攻に身を捧げることになったのか。時代がいかなるものになっても、人間として死守しなければならないものとは何か――ギリギリの極限状況のなかで描く本格小説。
あの戦争はいかなるものであったのか。あの戦争の最前線はいかなるものだったのか。命がけの最前線を知らぬ者が、命令を下す側に立った時、いかに過ちを犯し、いかに逡巡し、支離滅裂なものになり果てるのか。現場を知らぬエリートとマスコミがいかに悲劇を生み出すか。百田尚樹さんの「永遠の0(ゼロ)」は、真珠湾、ミッドウェー、ラバウル、ガダルカナル、沖縄の戦いの最前線を、世界に轟く名戦闘機"零戦"に乗る「臆病者」「命を惜しむ男」「人間としての尊厳と愛を貫いた男」「妻子のために生きて帰ることを約束した倫たる男」である熟練の宮部久蔵の心中に迫ることによって描く。その男がなぜ特攻に身を捧げることになったのか。時代がいかなるものになっても、人間として死守しなければならないものとは何か――ギリギリの極限状況のなかで描く本格小説。
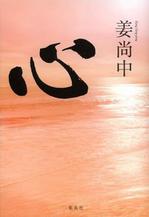 姜尚中さんが亡くなった息子と感じた西山直広君とのメールのやりとりから成る小説。直広君は心友・与次郎君の生と死に導かれ、東日本大震災における遺体の引き上げという過酷なボランティア「デス・セービング」に取り組む。ゲーテの「親和力」が基調音を奏でる。
姜尚中さんが亡くなった息子と感じた西山直広君とのメールのやりとりから成る小説。直広君は心友・与次郎君の生と死に導かれ、東日本大震災における遺体の引き上げという過酷なボランティア「デス・セービング」に取り組む。ゲーテの「親和力」が基調音を奏でる。
親友の死、裏切り、良心の呵責、募る恋、さまざまな親和力、大地震、デス・セービング、PTSD......。不可思議な人間関係、人と人との出会いのなかにこうした親和力や分離力が働くのは、宇宙広しといえども人間だけだ。諸法は実相であり、諸法の実相を如実知見せよ。無常の中にも常住を見よ。常住壊空のなかにも永遠性を信じ真面目に生き抜け――そういっているようだ。
最後は姜尚中さんの息子さんの最後の言葉「生きとし生けるもの、末永く元気で」で締めくくられている。この言葉があまりにも重いために、姜尚中さんは、ピュアで普通の小説にしたのだと私は思った。
8月7日、8日の二日間、「子ども霞が関見学デー」が行われ、夏休み中の多くの子どもたちが国土交通省を訪れました。さまざまな展示・紹介のコーナーを設け、そのなかで「国土交通大臣とお話ししよう」という場を開催。8日の昼、国土交通省の大臣室に18人の小中学生とその保護者の方をお招きして懇談しました。
大臣室の窓から見える国会議事堂、最高裁判所、総理官邸などを説明し、陸海空に幅広く関わる国土交通省の仕事内容を子どもたちに説明。「質問がありますか」と聞くと、子どもたちから次々と手が挙がりました。
「子どもの頃に好きだった本は何ですか」「好きなスポーツは何ですか」といったことから、「災害が起こったときに国土交通省はどう対応するのですか」「東北の復興のために必要なことは何ですか」「国土交通大臣になってよかったことは何ですか」「鉄道が好きですが、今後鉄道は増えていきますか」「鉄道貨物は将来どうなりますか」まで、質問は多岐にわたりました。
鉄道や航空、道路、災害など国土交通省の仕事は子どもたちにも身近な分野のようです。純粋で何でも興味をもつ年代。社会や行政について関心を深めてもらういい機会になったと思います。
明るく元気な子どもたちとの楽しいふれあいができました。
 欲望、人間中心主義、自然との対立概念、科学技術優先――。そうした近代西洋文明批判、近代合理主義批判がなされて久しい。むしろ最近では、骨太の文明論は少なくなっている感すらある。しかし、梅原猛さんは、それに代わり人類文化を持続的に発展せしめる原理が、日本文化のなかに存在する。それは「草木国土悉皆成仏」だという。
欲望、人間中心主義、自然との対立概念、科学技術優先――。そうした近代西洋文明批判、近代合理主義批判がなされて久しい。むしろ最近では、骨太の文明論は少なくなっている感すらある。しかし、梅原猛さんは、それに代わり人類文化を持続的に発展せしめる原理が、日本文化のなかに存在する。それは「草木国土悉皆成仏」だという。
文明と文化を全的に把握したうえで、真正面からナタを振り降ろすがごとき大きな肺活量の文明論だ。天台本覚思想、縄文文化、アイヌ文化。そして西洋のデカルト、ニーチェ、ハイデッガーの哲学。更にヘブライズムとヘレニズムという西洋近代文明の源を示しつつ、西洋哲学から人類哲学への転換を説く。「草木国土悉皆成仏」「森の思想」だ。
生命の尊厳、色心不二、草木成仏、一念三千論、五陰・衆生・国土の三世間・・・・・・。私はそうしたことを想いつつ読んだ。壮大な人類哲学は、想いがあふれなければ、とうてい書けるものではないと思った。
猛暑、豪雨、渇水の気候不順の夏――。8月2、3、4の週末3日。地域では納涼祭、祭礼、盆踊り、子ども大会、カラオケ大会、サンバパレードなどの商店街行事、伝統の王子田楽など多くの行事が行われました。また、日本海洋少年団全国大会が高円宮妃殿下のご臨席の下で力強く行われ、ますます大事になる海洋国家・日本を担う次の人材が全国から集い、友情の輪を広げました。
地域での人の交流、子どもたちとの交流はとても大切です。関係の方々に感謝です。懇談もでき、多くの声を聞きました。

