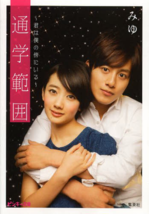9月1日の「防災の日」、政府、国土交通省、そして地元の防災訓練に参加しました。
9月1日の「防災の日」、政府、国土交通省、そして地元の防災訓練に参加しました。
まず、政府の総合防災訓練。早朝6時5分にM9.1、最大震度7の南海トラフ巨大地震が発生したという想定で、8時前に安倍総理以下全閣僚が官邸に参集。緊急災害対策本部会議で被害状況や対応状況を報告し、臨時閣議で災害緊急事態への対処方針を決定しました。
そして9時20分から、国土交通省の防災センターで地震防災訓練。南海トラフ巨大地震発生から1日経過したという想定で、中部地方を中心とする6県3政令市、250を超える関係団体、約1万5000人が参加する大規模なものでした。中部地方整備局、中部運輸局とのテレビ会議や、関東、北陸、中部の各地方整備局から派遣されたテック・フォース(緊急災害対策派遣隊)の報告など、現場とやり取りしながら訓練を行いました。
特に今回の訓練では、8月23日に取りまとめたばかりの国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画に即して、緊急輸送ルートの確保や津波による浸水を排水するための訓練を新たに盛り込みました。
国土交通省は国土の安全保障を担う組織。国民の命を守ることを第一に、現場が緊急度の高い行動を判断して、それに専念できるようにすることが重要です。災害対策本部会議では優先順位や時系列を踏まえたメリハリのある対応ができるよう、指示しました。 その後、地元の防災訓練に参加。いざという時には、地域のつながり、防災力、防災意識が大事です。真剣に訓練に取り組まれていた方々と懇談しました。
その後、地元の防災訓練に参加。いざという時には、地域のつながり、防災力、防災意識が大事です。真剣に訓練に取り組まれていた方々と懇談しました。
訓練は何よりも積み重ねが大事。訓練で得られた教訓を今後に活かしながら、防災・減災対策にしっかり頑張ります。
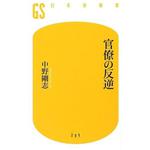 オルテガの大衆社会論と、ウェーバーの官僚論がまず提起される。「官僚の反逆」とは、オルテガの「大衆の反逆」をもじっている。オルテガの大衆批判は辛らつを極めるが、今なお鋭い。オルテガのいう大衆とは「個人としての特定の意見をもたず、附和雷同、大勢に流される人間」という。一方で「エリート、貴族とは決して現状に満足することなく、より高みを目指して鍛錬を続け、常に緊張感をもって生きている存在」であり、オルテガ大衆社会論に依れば、当然ながらエリートは大衆に嫌悪されることになる。この困難な道を引き受けて進もうとすれば、官僚バッシングを蒙ることになるが、その道を逃げれば(エリートからの逃走)凡愚に屈する大衆的人間となり果てる。
オルテガの大衆社会論と、ウェーバーの官僚論がまず提起される。「官僚の反逆」とは、オルテガの「大衆の反逆」をもじっている。オルテガの大衆批判は辛らつを極めるが、今なお鋭い。オルテガのいう大衆とは「個人としての特定の意見をもたず、附和雷同、大勢に流される人間」という。一方で「エリート、貴族とは決して現状に満足することなく、より高みを目指して鍛錬を続け、常に緊張感をもって生きている存在」であり、オルテガ大衆社会論に依れば、当然ながらエリートは大衆に嫌悪されることになる。この困難な道を引き受けて進もうとすれば、官僚バッシングを蒙ることになるが、その道を逃げれば(エリートからの逃走)凡愚に屈する大衆的人間となり果てる。
ウェーバーは、官にも民にも及ぶ近代社会の「官僚化現象」――「官僚は規則の拘束の下で職務を執行し、"非人格的"な没主観的目的に奉仕する義務を負う」「そのためには批判基準の定量化・数値化や、主観的価値判断・感情の排除が随伴する」ことを示す。人格的、主観的な「政治」とは対極に位置する。
私自身が長く意識してきた「大衆社会論」「ファシズム論」には、1930年代のオルテガ、ウェーバー、ホイジンガ、アドルノやベンヤミンらのフランクフルト学派、その後のE・フロム等が常に基底にあった。
本書では、70年代頃から日本の大衆社会化が顕著になり、80年代には決定的になったと見る。「政治の上に立つような"国土型官僚"は60年代までは多数存在したが、70年代には"政治的官僚""調整型官僚"が優勢となり、80年代にはそれとは全く異なる"吏員型官僚(非政治的な官僚)"が現われるようになった。それはウェーバーが抽出した官僚像だ。90年代にはグローバル化の進展とともにその官僚制的支配の拡大が顕著になる」。そして「非政治化・官僚制化による自由民主政治の破壊」となると指摘。
現代社会は、オルテガの大衆社会化状況、ウェーバーの官僚制化現象、ホイジンガの小児病化が顕著になっている。そして中野さんは、リーマン・ショック、ユーロ危機、日本の失われた20年等で、官僚制的支配の破綻が明らかになった今、「自由民主政治」を復活させなければならない。「政治とは何か」を考え、「政治主導」なる意味を真に蘇らせなければならないという。


29日、実験線の延伸工事により中断されていた「リニア」の走行試験が再開されました。私も、再開に先立ち、山梨県都留市で開催された出発式に参加し、リニアの試乗も体験してきました。
リニアは 時速500kmを超える速度で走行し、東京・名古屋間を40分程度、東京・大阪間を1時間強で結ぶ夢の超特急。
走行試験では、42.8kmの実験線をわずか9分で駆け抜けました。最高速度は505km、秒速にすると140m。試乗後の会見で、「スピード感は感じるが不快ではない。音が静かになったということだが会話も普通にできた。通常の新幹線に乗っている感覚とそれほど変わりなく、振動も若干感じる程度だった」「世界最高水準の技術が出せることは誇るべきこと」と感想を述べました。
リニアの開発は、今を遡ること約50年前、昭和37年より開始されました。以来、多くの関係者のご努力と情熱が注ぎ込まれ、実用化まであと一歩のところまで来ています。まさに、世界に類を見ない、我が国独自の高速鉄道技術です。実用化すれば、我が国の鉄道技術水準の高さを、改めて世界に示すことになります。かつての東海道新幹線がそうだったように、多くの国民の方々に「技術大国日本」の象徴として、誇りと将来への大きな希望を与えることができると思います。
また、これができれば(2027年の完成目標)、三大都市圏間の人の流れを劇的に変え、国民生活や経済活動にも非常に大きなインパクトをもたらすことになります。さらに、リダンダンシーの強化が図られ、防災面でも重要です。
リニアは次代に向け、安全と安心と夢と希望を乗せ走行します。乗り越えるべき課題はまだまだありますが、一日でも早い実用化を期待します。
頑張ります。
8月26日、東京都の三宅島と新島を視察しました。南海トラフ巨大地震が発生した場合、静岡県から高知県に至る各地域に30mにも及ぶ津波が襲来するため、その対応を急いでいますが、反対の海側にある離島の津波対策も重要です。その観点に立って、両島で村長さんをはじめ関係者と打ち合わせをしました。
火山島である三宅島は、数十年に一度の割合で大規模な噴火を繰り返しています。2000年の大噴火の際、私は現地へ行って対応。全島避難の方々と同じ船で帰ってきた経験があります。今年に入って何回か地震があり、心配していましたが、現在は落ち着いています。櫻田昭正村長から、「多くの砂防堰堤が建設されたことが、最も島民の安心につながっています」とのお話がありました。津波(三宅島では最大17m)への対応という視点も加えて打ち合わせを行いました。
その後、新島に移動。新島は、南海トラフ巨大地震が起これば最大約30mの津波に襲われると想定されている島。しかも、人口約2300人のほとんどが低地部に住んでいる上に、夏のシーズンにはサーフィンや海水浴に多くの観光客が訪れるため、いかに避難を的確に行うかが課題です。出川長芳村長からは、標高と避難ルートを記した「津波避難マップ」を各戸や
民宿に配布している取り組みの紹介がありました。また、高齢者の避難や津波情報の迅速な伝達などの課題が提起されました。
また、三宅島でも新島でも、発電所が海岸沿いにあるため、高台への移転や発電車の配備も課題です。
南海トラフ巨大地震対策に万全を期すために、有意義な視察ができました。さらに頑張ります。