 10月7日、第3次安倍改造内閣の発足に伴い、国土交通大臣を退任しました。今後は、公明党議長(全国議員団会議議長)として、約3000名の地方議員をバックアップし、来年の参院選等の党勢拡大に頑張ります。よろしくお願いいたします。
10月7日、第3次安倍改造内閣の発足に伴い、国土交通大臣を退任しました。今後は、公明党議長(全国議員団会議議長)として、約3000名の地方議員をバックアップし、来年の参院選等の党勢拡大に頑張ります。よろしくお願いいたします。
国土交通大臣としての在任期間は約2年9か月、1015日――歴代の国交大臣としては最長となりました。その間、災害や事故も多く、緊張した毎日が続きました。
退任に当たっての記者会見では、
・東日本大震災の復興に全力を挙げて取り組んだこと
・「防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化」を公共事業のメインストリームに位置付けたこと
・社会資本のストック効果に焦点を当てて「選択と集中」を図ったこと
・訪日外国人の飛躍的増加など観光を大きく前進させたこと(訪日外国人旅行者は、私が就任した当時の800万人台から、1000万人以上増え、今年は1900万人を越える見込み)
など、一生懸命取り組んできたと述べました。
 また8日には、石井啓一新大臣への引き継ぎを行い、国交省の職員に対して挨拶。「国土交通省は国土の安全・安心を守る最後の砦。最前線の現場まで一体となって課題に取り組むことができた」と感謝を述べました。
また8日には、石井啓一新大臣への引き継ぎを行い、国交省の職員に対して挨拶。「国土交通省は国土の安全・安心を守る最後の砦。最前線の現場まで一体となって課題に取り組むことができた」と感謝を述べました。
大臣在任中は多くの方々にお世話になり感謝申し上げます。これからも全力を尽くして頑張っていきます。
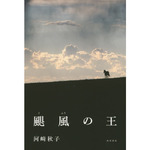 圧倒的な感動小説。「丈夫が こころ定めし 北の海 風吹かば吹け 波立たば立て」(依田勉三)、「波浪は障害にあうごとに、その頑固の度を増す」を思う。明治から平成にかけて、東北から北海道に向かった祖父とその孫、そのまた孫の6世代にわたる家族と命をつないだ馬の物語。
圧倒的な感動小説。「丈夫が こころ定めし 北の海 風吹かば吹け 波立たば立て」(依田勉三)、「波浪は障害にあうごとに、その頑固の度を増す」を思う。明治から平成にかけて、東北から北海道に向かった祖父とその孫、そのまた孫の6世代にわたる家族と命をつないだ馬の物語。
雪崩で馬とともに遭難しながらも、その愛馬を食べて生き延び、腹の中にいた捨造の命を守った母。その手紙で事実を知った捨造の号泣。その孫・和子が世話をする馬・ワカ。離島に残された馬に会いに行く和子の孫・ひかり・・・・・・。「およばぬ」ものとして畏怖される苛烈な風土、そのなかで必死に生き抜く人と馬。壮絶ななかに「生き抜け」「馬に生かされたんだ。報いねばなんねえ」との心奥の叫びと、「わたしのどこが哀しいのだ。島に独り残り出られないのではない。この島の王として凛として君臨する」と感じさせる馬の存在が、大地に屹立する。
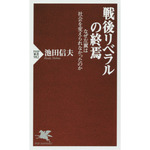 「なぜ左翼は社会を変えられなかったのか」と副題にある。「本書ではこういう日本的な左翼(中道左派)を"戦後リベラル"と呼ぶ。彼らは反戦・平和を至上目的とし、戦争について考えないことが平和を守ることだという錯覚が戦後70年、続いてきた」「彼らは戦後の論壇で主流だったが、何も変えることができなかった。全面講和も安保反対も大学解体も、スローガンで終わった」「団塊世代の特徴は新憲法バイアスである。生まれたのが終戦直後だから、戦争は絶対悪で、平和憲法は人類の理想だという教育を子供のころから受けた」「憲法を超える"空気"は、戦前も今も変わらない。それをかつて右翼は"国体"と呼んだが、戦後は"国民感情"に変わっただけだ」・・・・・・。そして、「今の日本で重要な政治的争点は、老人と若者、あるいは都市と地方といった負担の分配であり、問題は"大きな政府か小さな政府か"である」と結ぶ。
「なぜ左翼は社会を変えられなかったのか」と副題にある。「本書ではこういう日本的な左翼(中道左派)を"戦後リベラル"と呼ぶ。彼らは反戦・平和を至上目的とし、戦争について考えないことが平和を守ることだという錯覚が戦後70年、続いてきた」「彼らは戦後の論壇で主流だったが、何も変えることができなかった。全面講和も安保反対も大学解体も、スローガンで終わった」「団塊世代の特徴は新憲法バイアスである。生まれたのが終戦直後だから、戦争は絶対悪で、平和憲法は人類の理想だという教育を子供のころから受けた」「憲法を超える"空気"は、戦前も今も変わらない。それをかつて右翼は"国体"と呼んだが、戦後は"国民感情"に変わっただけだ」・・・・・・。そして、「今の日本で重要な政治的争点は、老人と若者、あるいは都市と地方といった負担の分配であり、問題は"大きな政府か小さな政府か"である」と結ぶ。
まさに私の戦後は、人生そのもの、全てである。たどった人生、出来事、思想を、そのまま思い起こしながら読んだ。
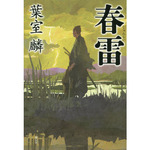 時代社会が変化していることを知らず、武士という特権意識に何の疑問ももたず安住する者。また名君気取りで質素の形だけに溺れ、見せかけの善政で体裁をつくろう者。信を寄せている訳でもなく、ただへつらい生きる者・・・・・・。そのなかで、恐れず、ぶれず、ためらわず、ただ心奥に秘めた一心の成就にかけた鬼と呼ばれた男がいた。財政難に喘ぐ豊後・羽根藩の改革断行に指名された多聞隼人。
時代社会が変化していることを知らず、武士という特権意識に何の疑問ももたず安住する者。また名君気取りで質素の形だけに溺れ、見せかけの善政で体裁をつくろう者。信を寄せている訳でもなく、ただへつらい生きる者・・・・・・。そのなかで、恐れず、ぶれず、ためらわず、ただ心奥に秘めた一心の成就にかけた鬼と呼ばれた男がいた。財政難に喘ぐ豊後・羽根藩の改革断行に指名された多聞隼人。
「米一粒たりとも作らぬ武士こそ、悪人ということになる」「悪人とはおのれで何ひとつなさず、何も作らず、ひとの悪しきを謗り、自らを正しいとする者のことだ」「殿は名君にあらず、稀代の暗君である」「多聞様は自らが鬼となることで、まことの正と邪を明らかにされようとしていたのではないか」・・・・・・。
「多聞様は、世のひとを幸せにしたいと願って鬼になられたのです」――鬼と謗られる孤高の男の想いは誰も知らず。それを「蒼穹を、春雷がふるわせている」と結んでいる。




