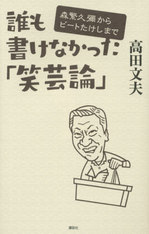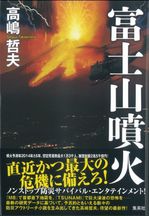「身近な日韓友好のすすめ」と副題にある。金さんは、韓国・ソウル生まれの国際法学者で、「テロ防止策の研究――国際法の現状及び将来への提言」(早稲田大学出版部)など、テロに関する国際法の専門家。
本書はその専門とは全く別。嫌韓・反日のどぎつい風潮が飛び交うなか、「四季を想う」「食を楽しむ」「文化・習慣を知る」「アジアの心をつなぐ」「平和への願い」など、日常のなかに、いかに日韓の共通性、交流があるか、長いつながりがあるか――そうしたことを愛情を込めて書く。一部の激しい対立ではなく、落ち着いた日常をかみしめるなかに理解がある。その身近な日韓友好が大事だということを静かに語る。「スイカに塩をかける日本、砂糖をかける韓国」「月を見てウサギの餅つきと感ずるのは日韓共通」など、面白い日常の話題も語られる。
軍事アナリストとして、危機管理のプロとして、実際に政府、地方自治体の危機管理に携わってきた小川さんの警世の書。今こそ必要な書だ。
「狙われる企業、安全な企業」と副題にある。「巨大企業の危機管理についてのコンサルタントをしてきたが、情報が氾濫する一方で、日本企業の危機管理レベルは低いままで推移しており、その立ち後れに警鐘を鳴らし、日本の経済立国を基礎の部分から確かなものにしたい」と考えたからだという。
日本の場合、たしかに「危機管理を語る」だけで、危機意識そのものが、トップを含めてなさすぎる。世界では国も企業もどうしているか、小川さんがコンサルタントをして各組織はどう対応したか。何から始めようとしたか。防災も、私は「危機管理は実務だ。現場だ。リーダーシップだ。日頃からの情報収集、備えだ」と考えてきたが、本書は、世界がより高度化、複雑化しているなかでの危機管理の水準を示している。
「海外緊急事態」「日本の危機管理は形だけ」「社員と家族を脱出させるためのコストは月1000万円」「平時型組織しか知らない日本人」「コンサルタントを活用できているか」「日本も政府も危機管理はCEOにしかできない」「日本に求められるテロ対策」「企業人のための情報活動のイロハ」の8章よりなる。
たしかにこの「笑芸論」は高田さん以外は「誰も書けない」ものだろう。「森繁久彌からビートたけしまで」の戦後「笑芸史」が、紙面からあふれるほど、ものすごいスピードで四方、八方、空間狭しと飛び出している。「私のこの両目は誰よりも沢山の面白い人を見つめてきたし、私のこの両耳は誰よりも多くの笑い声を聞いてきました。その量だけが自慢です。・・・・・・」と結んでいるが、その通り。
笑いが大好きで、今も「エンタの神様」をはじめお笑い番組を録画したりする私だが、テレビ等で観てきたスターたちの生の姿にふれた本書は、きわめて面白かった。この60年を思い出したりもした。また地方から見て、当時の「東京」への感情の核にふれた思いもした。
火山噴火は、台風・水害・土砂災害とも地震とも違う。台風等はタイムラインが通用する。地震は予知できないうえに、瞬時の大災害だ。しかし火山噴火は、予知等はある程度できるが、規模や終結までの期間の判断が難しい。
富士山噴火という大テーマに、高嶋さんが挑んでいる。「美しき山」「異変」「避難」「噴火」「火砕流」「山体崩壊」の6章だてだが、危機は深刻化していく。首長や組織を担っている者が「避難」の決断を下すことがいかに難しいか、火山灰の影響(目をこすらないとか、雨によっての火山泥流)、噴石・火山灰・火砕流のなか、どこへ、いかなる方法で、避難を行うか――まさに陸海空全てに常識を超える国をあげての対応が不可欠となる。
「箱根町は火山の恵みで今日まで来た。しかし、この2ヶ月余り、観光客が大幅に減り、困っている。大涌谷周辺の1kmの範囲が警戒区域なのに、箱根山全体が危険と思われてしまう。歯をくいしばって頑張っている」――17日、箱根町の実情を視察。山口昇士町長らの要望を受け、箱根湯本の商店街を回り、切実な声を聞きました。
箱根は6月29日から30日にかけて地震活動の活発化と噴石があり、噴火警戒レベルが2から3に引きあげられました。7月以降は噴石は一度もなく、震度1以上の有感地震もほとんどありません。しかしながら、現在も地殻変動は継続していること、新たな噴気口ができるなど噴気活動が活発なことから、噴火警戒レベル3を継続している状況です。
私は、こうした現状を説明するとともに、「神奈川県の温泉地学研究所と連携し観測体制をさらに強化する」「機動観測班2名を常駐させているが、毎日最新状況を地元に報告する」「"今でも箱根駅伝のコースは大丈夫""箱根湯本・強羅・仙石原・芦ノ湖周遊コースは公共交通機関で可能"など、旅行者にわかりやすい正確な情報を提供する」「世界三大旅行博のツーリズムEXPOジャパンが9月にある。箱根をPRする」など、支援を強調しました。