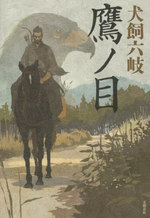1945年の敗戦から1952年4月のサンフランシスコ講和条約発効までの7年弱。現代日本の法的・政治的基盤は、まさにこの時に創られた。この時の重い苦渋の決断の数々が、今の日本の"国の形"をつくっている。当初占領政策は、日本の非軍事化・民主化の推進に置かれ、日本国憲法が誕生する。しかし、アメリカとソ連による冷戦が深刻化していくなか、民主的な「平和国家」の創設だけでなく、新たに日本を「親米反共」国家にすることが付加され、「経済復興」政策が推進されることになる。ドッジライン、朝鮮戦争、そして結ばれたサンフランシスコ講和条約は、日米安保条約とセットの締結となる。そのなかで「全面講和か単独講和か」は、世界の冷戦構造の深刻化のなか、いかに大きな国際政治の渦の中で行われた選択であったかを今改めて考える。
1945年の敗戦から1952年4月のサンフランシスコ講和条約発効までの7年弱。現代日本の法的・政治的基盤は、まさにこの時に創られた。この時の重い苦渋の決断の数々が、今の日本の"国の形"をつくっている。当初占領政策は、日本の非軍事化・民主化の推進に置かれ、日本国憲法が誕生する。しかし、アメリカとソ連による冷戦が深刻化していくなか、民主的な「平和国家」の創設だけでなく、新たに日本を「親米反共」国家にすることが付加され、「経済復興」政策が推進されることになる。ドッジライン、朝鮮戦争、そして結ばれたサンフランシスコ講和条約は、日米安保条約とセットの締結となる。そのなかで「全面講和か単独講和か」は、世界の冷戦構造の深刻化のなか、いかに大きな国際政治の渦の中で行われた選択であったかを今改めて考える。
本書は「東京・ワシントン・沖縄」が副題となっているが、それぞれの国を背負っての決断の実像が描き出される。「憲法」「安保」「沖縄」「政党の生成と分裂」「労働運動」「経済復興論争とドッジライン」「東京裁判」「国際社会の中の日本」・・・・・・。まさに戦後70年、今後の日本を考える時、不可欠の7年弱といえる。2015年度読売・吉野作造賞受賞。
 「先人に学ぶ防災」と副題にあり、「天災を勘定に入れて、日本史を読みなおす作業が必要とされているのではなかろうか。人間の力を過信せず、自然の力を考えに入れた時、我々の前に新しい視界がひらけてくる」「喪失はつらい。しかし、失うつらさのなかから未来の光を生み出さねばならぬと思う」という。古今の文書を調べ上げ、全国に足を運んで古い記録、古文書に当たる。その徹底した姿勢は驚嘆に値する。先人の知恵が浮かびあがる。
「先人に学ぶ防災」と副題にあり、「天災を勘定に入れて、日本史を読みなおす作業が必要とされているのではなかろうか。人間の力を過信せず、自然の力を考えに入れた時、我々の前に新しい視界がひらけてくる」「喪失はつらい。しかし、失うつらさのなかから未来の光を生み出さねばならぬと思う」という。古今の文書を調べ上げ、全国に足を運んで古い記録、古文書に当たる。その徹底した姿勢は驚嘆に値する。先人の知恵が浮かびあがる。
「秀吉と二つの地震――天正地震(地震に救われた家康)と伏見地震」「宝永地震が招いた津波と富士山噴火」「土砂崩れ・高潮と日本人」「佐賀藩を"軍事大国"に変えたシーボルト台風」・・・・・・。
昭和8年三陸大津波という地獄を見て、岩手県普代村の村長・和村幸得さんは周囲の反対を押し切って15.5mの防潮堤を築き、今回の東日本大震災で死者を防ぐことになった。その回想録「貧乏との戦い40年」にふれつつ、「教訓は、過去の災害の大きさを参考に、自然と人間の力量の境目を冷徹にみよ、自然に逆らわぬ防災工事をすすめよ。この二つではなかろうか」と結んでいる。すぐれた蓄積の書だ。
9月26日、富山県南砺市、岐阜県白川村と高山市に行き、伝統的な集落・町並みを保存して多くの観光客を呼び込んでいる地域活性化の取組みや、アクセス改善の中部縦貫自動車道、国道41号線など道路整備の状況を視察しました。また、古田肇岐阜県知事をはじめ地域の市町村長、商工会や観光業の代表者と意見交換を行い、要請を受けました。石井隆一富山県知事からも要請を受け、懇談しました。
白川村の白川郷と南砺市の五箇山は、茅葺きの合掌造りの集落を地域一体で保存(古いものは築400年)。1995年に世界遺産に登録されて今年で20周年です。ここでしか見られない景観を求めて国内外から訪れる観光客は年々増加。昨年は白川郷で約150万人、五箇山は約70万人で、今年はさらに増加しています。
高山市では城下町・商人町の古い町並みを伝統的建造物群保存地区として保存しています。江戸時代さながらの景観を求めて訪れる観光客は年間約400万人。そのうち海外からは約28万人で、フランスの「ミシュランガイド」では「必ず訪れるべき観光地」として最高の三つ星評価を獲得しています。
高山市での意見交換では、「この地域は観光がメインの産業。アクセス改善のため道路整備が重要」「今年は北陸新幹線の開業で観光バスなど大幅に増えている。観光シーズンには渋滞が激しいので、東海北陸自動車道の4車線化や中部縦貫自動車道の整備を進めてほしい」「国道41号線はカーブも多く、雨量規制や積雪で通行止めが多い。バイパス整備を進めてほしい」「鉄道の接続が悪いので改善をお願いしたい」など発言が続きました。
私は「この地域の観光ポテンシャルの高さを実感した。国道41号については、石浦バイパスのトンネルをおおむね5年で開通させたい」と具体的整備目標を初めて表明しました。
25日、「ツーリズムEXPOジャパン2015」が、東京お台場の東京ビッグサイトで開幕。私もイベントに参加し、各国ブースを訪問しました。ツーリズムEXPOジャパンは、ベルリン、ロンドンと並ぶ世界3大観光イベント。47都道府県から約460の団体・企業、140を超える国・地域から約600の団体・企業が参加し、17万人を超える来場者が見込まれています。伸長著しい日本観光のさらなる起爆剤として、内外の関係者の大きな注目を集めています。
会場は大変な熱気に包まれており、参加の企業・団体は趣向を凝らし、各国・地域や旅行商品の宣伝を行っていました。
私は中国、韓国、ブルガリアやルーマニア、沖縄県、北海道、岩手県などたくさんのブースを訪問しました。また、箱根観光をPRするイベントに参加しました。
夜には東京駅の前で「ジャパンナイト」が盛大に開催されました。私は、冒頭挨拶するとともにイベントに参加したタイ、ブルガリア、リトアニア、ミャンマー、ルーマニアの大臣、副大臣や各国の大使などと懇談しました。