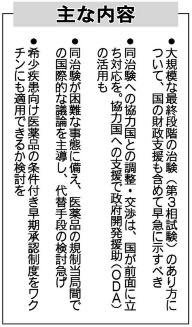27日、日本旅行業協会(会長=坂巻伸昭・東武トップツアーズ 代表取締役社長執行役員)との懇談会に出席しました。これには、伊藤渉財務副大臣、佐藤英道衆院議員などが出席しました。
同協会からは、コロナ禍による影響・現状などを聞くとともに、「雇用調整助成金の更なる延長」「地域観光復活のための支援拡大」「デジタルパスポートの導入」などについて強い要望を受けました。
私は「旅行業界は未曾有の危機に直面している。事業規模の大小にかかわらず、国の全面的な支援、バックアップをやらなくてはならない。また、ワクチン接種、パスポートなど一刻も早く陣形を整えて、少しでも安心感を与えていかなくてはならない」と挨拶しました。
東北中央自動車道の相馬―福島間(45.7キロ)が24日、全線開通しました。福島市から相馬市へ行くには、阿武隈山脈越えのため、大変な時間がかかっておりましたが、これで大きく短縮されます。福島支援の復興支援道路です。
24日は赤羽国交大臣が、霊山―伊達桑折間の開通式典に参加しましたが、ここは、私が国交大臣の時に着工したものです。8年で完成するという類例のないスピードでの全線開通です。
開通により、沿岸部を通る常磐自動車道と内陸部を走る東北自動車道がつながりました。立谷秀清・相馬市長から、「郡山からも米沢からも相馬の方へ一気に人流・物流が増えることになります」と、感謝と喜びの電話がありました。
大変嬉しい相馬―福島間の全通です。