 26日に発足した自民、公明両党連立による第2次安倍内閣で国土交通大臣を拝命しました。
26日に発足した自民、公明両党連立による第2次安倍内閣で国土交通大臣を拝命しました。
安倍内閣での重要課題は、景気・経済を再生すること、被災地の復興を加速すること、防災・減災をはじめとする危機管理を構築することです。実現に向けて現場でしっかり仕事をするのが、私の役割だと決意しています。
何よりも景気・経済に力を入れるとともに、国土交通行政を預かる身として、防災・減災ニューディール政策を推進する先頭に立ちたいと思います。
さらに、震災から二度目の冬を迎える中、被災地で本当に悩んでいる方々が復興の加速を実感できるように全力で取り組んでいきます。
一昨日は、中央自動車道・笹子トンネルの天井板崩落事故で地元・山梨県から、迂回路になっている国道の渋滞が頻発していることに対する交通分散対策の要望を受け、中日本高速道路に対策検討を指示し、中央道・富士吉田線が1月1日から無料となりました。これで交通が分散化し、渋滞が少しでも緩和する手助けになると思います。
大変お世話になりました地域の皆様、そして全国の皆様のご期待に応えられるように、しっかり仕事をして頑張ってまいります。
 昨日2日に発生した中央自動車道の笹子トンネル崩落事故は、深刻かつ重大です。犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表すると共に、取り残された方々の一刻も早い救助を心からお祈り申し上げます。
昨日2日に発生した中央自動車道の笹子トンネル崩落事故は、深刻かつ重大です。犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表すると共に、取り残された方々の一刻も早い救助を心からお祈り申し上げます。
原因は調査中のようですが、ともあれ、巨大地震の危険性と、構造物の経年劣化が指摘される今、総合的な防災・減災対策は急務です。
全国知事会が2日に発表した、9党の衆院選マニフェストに対する評価でも、私どもの防災・減災対策や地域経済対策などは、高く評価されました。
日本再建のために、何を、どうするのか。私は今、3つの観点からお訴えさせていただいています。
第1は、【太田は中小企業の味方 だから 景気回復が最優先!】という点です。
「強い経済」は、社会保障など、国のすべてを支える土台です。特に、「経済の現場」を支える中小企業が元気になる経済政策が求められます。
そのために、一つは、防災・減災対策に集中投資を図り、100万人の雇用を生み出します。
もう一つは、「女性」「不安定雇用の若者」「60代以上」──この三者に、雇用の場を生み出すことです。
第2は、【太田は耐震工学のエキスパート だから 地震対策の即戦力!】という点です。
私は、京都大学・同大学院で、耐震工学を研究しました。そのスキルを生かし、ライフワークとしてきた学校の耐震化も、建物それ自体の耐震化は、10年前の44.1%から84.8%にまで倍増しました。
次は、体育館の天井ボードや照明器具などの耐震化を、100%、実現してまいりたい。
さらに、河川流域を守る水門の耐震化や、河川敷の液状化対策も、進めねばなりません。
政治の役割は、備えること。「想定外」などという言い訳は、許されません。
第3は、【太田は現場第一 だから 北・足立の暮らしを向上!】という点です。
史上最多38個のメダル獲得に大きく貢献した北区・西が丘のナショナルトレーニングセンターは、私が、その早期開設を推進してきたものです。
長年にわたる地域の願いであった、日暮里・舎人ライナーの早期開業も実現。竹ノ塚駅周辺の高架化も、時の国交大臣に何度も迫り、地元の皆さまと共に推進してきました。
運営主体の解散によって存続が危ぶまれた東京北社会保険病院も、存続を実現できました。
「政治は結果」──これが私の信念です。「結果」以外のもので国民の歓心を"買う"のは、政治家ではありません。それは「政治屋」です。
その場しのぎのパフォーマンス、いわば瞬間芸のような一瞬の風頼みという、「点の政治」に躍起なのは「政治屋」。
何があろうともブレず、志をもって実行し続け、お約束したことは、必ず実現するという、「線の政治」に邁進するのが「政治家」。
私は、政治への信頼を取り戻していただくことが、日本再建への基盤──そのためには「政治家への信頼」こそ根本だと信じ、どこまでも誠実に、走り抜いてまいります。
公職選挙法の規定により、公示日以降はホームページやブログの更新、メールマガジンの発行等ができません。ご理解とご容赦のほど、よろしくお願い申し上げます。
 昨日25日は晴天のもと、秋の諸行事が行われました。防災訓練を行う町会・自治会もありましたが、一昨日には東京で、突き上げるような震度4の地震があったばかり。地域の皆さまの真剣な取り組みに、頭の下がる思いです。
昨日25日は晴天のもと、秋の諸行事が行われました。防災訓練を行う町会・自治会もありましたが、一昨日には東京で、突き上げるような震度4の地震があったばかり。地域の皆さまの真剣な取り組みに、頭の下がる思いです。
外交や景気・経済など、民主党政権の3年間における大失政は、日本に大打撃を与えました。今、大事なのは「日本再建」。私は、そのために、まずやるべきことこそ、景気・経済の再建・活性化と、防災・減災対策への積極的な取り組みだと思います。
そこで主張しているのが、「防災・減災ニューディール」です。
この「防災・減災ニューディール」には、3つの側面があります。
第1は、高度成長期に建造された橋や道路、建築物などは、その多くが、建造から50年近くたち、劣化を起こしています。「住民の命を守るための公共投資」という側面です。
第2は、日本列島は今、地震の活動期に入ったといわれています。首都直下地震は、これまでの最大震度6強との予測が、震度7に上げられました。建物の損壊は数倍になるともいわれています。すなわち「首都直下地震など、巨大地震への対応が急務」という側面です。
第3は、需要を生み出すことで、日本経済を活性化させ、雇用をつくり、今、日本で最も重要な景気・経済の再建にも大いに資すること。つまり「デフレ克服の突破口になる」という側面です。
私は4月25日、首相官邸で官房長官と会い、政府に対して、地震対策の緊急提言を申し入れました。さらに5月18日には、文科大臣に会い、「学校体育館の天井ボードや照明器具などの耐震強化を急げ」との申し入れを行いました。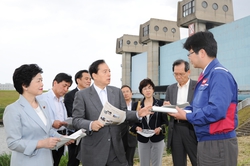 私は、地元にある岩淵水門や芝川水門の早期耐震化も、直接足を運んで話を聞き、推進してきました。地域住民の避難場所である荒川河川敷への進入路として、唯一、大規模地震における耐震性能が不足していた志茂橋も、たびたび国交省に足を運んで訴え、耐震補強・改修が実現し、来月にも工事が着手されます。
私は、地元にある岩淵水門や芝川水門の早期耐震化も、直接足を運んで話を聞き、推進してきました。地域住民の避難場所である荒川河川敷への進入路として、唯一、大規模地震における耐震性能が不足していた志茂橋も、たびたび国交省に足を運んで訴え、耐震補強・改修が実現し、来月にも工事が着手されます。
「防災・減災ニューディール」は、"ばら撒き"などではありません。何が、国民の命を守るために最優先なのかを、「足」で調べて順位付け、そこに集中投資するのです。「現場第一」であってこそ、「防災・減災ニューディール」は実現できるのだと思います。
大学・大学院で耐震工学を研究してきた者として、そのお役に立ってまいりたい。この思いで私は、今日も現場を歩いています。
 昨日22日は、「やり続ける政治家」の大切さを、改めて教えていただく再会がありました。
昨日22日は、「やり続ける政治家」の大切さを、改めて教えていただく再会がありました。
ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会の竪山勲事務局長、全国ハンセン病療養所入居者協議会の神美知宏会長など代表の皆さんから、国立ハンセン病療養所の職員増員について要請をいただきました。
全国の療養所入居者は、現在、平均年齢が82.1歳。介護が必要な方が多くなっています。しかも、重度の合併症から、自由に物を持つことができず、例えば食事でも、一人で食べるとなると、口を直接、食器に運ばなければ食べられない方も多くいるそうです。それによって、食べ物が誤って気管などに入り、肺炎を引き起こして、多くの方が亡くなっていると伺いました。
この原因は、政府の国家公務員削減方針です。それによって、療養所の職員も削減されていく流れにあります。皆さんの訴えは、「ハンセン病療養所だけは除外してほしい」との悲痛な叫びでした。
私は2001年5月、ハンセン病訴訟熊本地裁判決で国が敗訴したことを受け、小泉首相に控訴断念を要請しました。特に、坂口厚生労働大臣(当時)の奮闘もあり、国は控訴断念を決定。さらに、ハンセン病への取り組みを反省する趣旨を含めた国会決議の取りまとめにも、尽力しました。
あの日から11年、政治が"液状化"している今という時にあって、再び私を頼りにしてくださったことに、使命感と大きな責任を感じ、私は「問題解決に、信念をもって取り組み続けます」とお応えしました。
薬害肝炎問題しかり。学校耐震化しかり。児童手当の拡充しかり。私がライフワークとして取り組んできた仕事は、多くあります。最初は大変でした。薬害肝炎問題も、厚労省は「一律救済は莫大な財源が必要」と、全面解決に消極的でした。しかし私たちは、原告団、弁護団と一体になって主張し続けました。
何が、その原動力となったか。私は、「代理役」としての責任感だったのではないかと思います。代理として、ご本人たちの心情に肉薄すればするほど、途中で投げ出せるはずがありません。「やり続ける」といっても、その内容は、連日ニュースで取り上げられるような性質のものとは、まったく違います。たいていは光の当たっていない世界のこと。パフォーマンスの政治家から見れば、地味で、目立たなくて、まったく関心のないことばかりでしょう。
しかし、それでは何のための「代議士」なのでしょうか。
「国民の声を代弁して、国政を議論する」──大局観に立つことと同時に、声なき声を政治に反映させてこそ、私は政治家だと信じています。
「一人を大切に」──この当たり前のようで当たり前になっていないことを、当たり前にしていきたいと、いっそう決意しています。
■私のレポートと、竪山勲事務局長からの応援メッセージの動画を、Youtubeチャンネルでご紹介しています。ぜひご覧ください。
≫ビデオメッセージ@国立ハンセン病療養所職員増員要請


