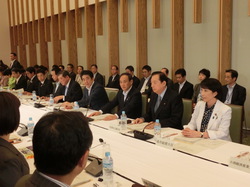「この秋からは地方創生が重要テーマ」――9月17日に国交省の「まち・ひと・しごと創生対策本部」を立ち上げ、19日には政府の「まち・ひと・しごと創生会議」の第1回会議が開かれ、各分野の有識者も交えて本格的議論がスタートしました。
地方創生を具体化していく上で私が特に強く打ち出しているのが、国交省が7月4日に発表した「国土のグランドデザイン2050~対流促進型国土の形成~」です。これは2050年という長期を見据えて我が国の国土や地方、都市のあり方を明らかにしたもの。政府の基本方針でも、このグランドデザインの考えが中心を成しており、位置付けは極めて重要です。
我が国は今、大きな変化、危機に直面しています。急激な人口減少、少子化により、2050年には人口が1億人を切るとの推計もあります。また国土を1㎞メッシュで区切ると、2050年には現在の居住地域の63%で人口が半分以下に減少、うち20%は無居住地化するという試算もあります。さらに首都直下地震や南海トラフ地震は、30年以内の発生確率が70%。2050年までにはどちらかが起こっていることも十分考えられます。
このような危機に対し、創生会議の有識者の一人である増田寛也さんは「地方消滅」という言葉で人口減少や少子化の問題を大胆に提起しました。私は「今ならまだ間に合う」「今が最後のチャンス」という考えで、長期的な視点に立って構造的な問題として取り組むことが必要だと考えています。その基軸を成すのがこのグランドデザインです。
グランドデザインの基本的コンセプトは「コンパクト + ネットワーク」。それぞれの地域が個性に磨きをかけ、異なる個性を持った地域が連携することが重要です。地域間で個性の違いがあるからこそ対流が起き、人や物の動きが起きるという「対流促進型国土」が実現できます。その個性を創り出すためには、それぞれの地域がどう生き抜くかという知恵を自ら生み出すことがまず何よりも大事です。
グランドデザインの考えを軸に何としても地方創生をやり抜く覚悟です。

6日、関西国際空港で、関空20周年、伊丹空港75周年の記念式典に出席しました。
関空、伊丹両空港は関西の発展に欠くことのできない基幹インフラ。新関空会社が両空港を一体的に運営し、近年、LCCを中心に大きく利用者が伸びています。現在、さらなる発展を目指し民間事業者への事業運営権の売却、いわゆるコンセッションに向けた手続きが進行しています。
「今後とも関西の発展を牽引して欲しい」「さらなる機能向上に向け全力で支援したい」――。式典では、両空港への期待の言葉が相次ぎました。私も祝辞の中で「両空港が関西圏の成長の原動力となることを期待する。引き続き最大限支援したい」と述べました。
式典の後、第2ターミナルビルにおいて日本初のLCCであるピーチのコスト削減への取り組み状況などを視察しました。

その後、大阪市内に移動し、うめきた開発を視察しました。うめきた開発は旧国鉄梅田貨物駅24haを再開発するビッグプロジェクト。大阪の都市競争力を強化する切り札として、大きな期待が寄せられています。昨年4月に先行してオープンした「グランフロント大阪」は多くの大学・企業と連携した最先端の科学技術の展示エリアとテナント、オフィスなどの複合施設。家族連れや若い人を中心に大変な賑わいでした。また、現在検討が進む2期事業のコンセプトは、「世界に比類なき『みどり』と『イノベーション』の融合拠点」という斬新なもの。計画の実現に向け、大阪市や関係の事業者などと意見交換しました。テクノロジー、インテリジェンス、ビジネス、ショッピング――。関西のみならず日本全体をリードできる大きな潜在力を実感しました。
7日には京都で門川京都市長と懇談。桂川の水害対策、観光、京都のまちづくりなどについて、じっくりと意見交換をしました。
9月3日に発足した第2次安倍改造内閣で、引き続き国土交通大臣、水循環政策担当大臣を拝命しました。
安倍内閣の掲げる重要課題は、引き続き、「景気・経済の再生」、「被災地の復興加速」、「防災・減災をはじめとする危機管理」の3本柱。さらに、魅力あふれる元気で豊かな「地方の創生」もこの秋からの重要課題になります。国土交通省はこれらの課題の全てに重要な役割を担うため、実現に向けてしっかり取り組んでいきます。
総理官邸での初閣議、記念撮影の後、記者会見で私が強調したのは、まず第一に被災地の復興を加速化すること。三陸鉄道の全線開通や常磐道開通の報に多くの方が喜んだことを私自身、現場で感じてきただけに、「復興の実感」に全力を上げます。そして「防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化」にさらに重点を置いて取り組んでいきます。巨大地震が切迫し、全国的に雨の降り方がこれまでと変わってきている中で、命を守るための取り組みを進めます。気象の変化、集中化・局地化・激甚化というステージの変化を直視し、「人命を守り抜く」ため真正面から取り組みます。
さらに、長期的視点を常に考えて進むことです。急激な人口減少、少子高齢化という問題に対し、7月に国交省でとりまとめた「国土のグランドデザイン2050」を具体化しながら、地方創生という新たなテーマにも力を入れます。
国交省は、インフラ、防災、交通、観光庁、海上保安庁、気象庁、水循環と幅広い分野を管轄しています。総合力を発揮できるよう頑張ります。
安倍総理はこの内閣を「実行実現内閣」にすると表明。私は国民生活の安全・安心と経済再生の実現に向けて、引き続き全力で取り組む決意です。
1日、インドのモディ首相と会談しました。インドは人口12億を擁する大国。政治的にも経済的にも大変重要な親日国です。
今回の安倍首相とモディ首相との首脳会談でも、インフラ整備が極めて重要な柱となっています。この日の会談では、私がインフラ、交通、観光、防災、海上保安などを担当するだけに、インフラ整備での協力関係の強化を目指してのものとなりました。モディ首相からは、高速鉄道、地下鉄や貨物鉄道の整備、道路ネットワークの整備、港湾整備や沿岸地域から内陸部へのアクセスの改善、国際空港の整備などに強い意欲が示され、日本のさらなる協力を求められました。
また、観光の双方向の交流拡大についても、突っ込んだ議論を行い、連携を強化していくことで一致しました。そのほか、海上保安分野や防災分野の連携についても、意見交換を行いました。
2国間の関係強化に向け、今後につながる意義のある会談となりました。
9月1日、防災の日。7時10分にM7.3の首都直下地震が発生したという想定で、首相官邸に総理以下全閣僚が参集して緊急対策本部会議の訓練を行いました。その後9時10分より、国交省の防災センターで全局長が集まる会議を開催。私から政府の訓練の状況を報告し、さらに今は訓練というより広島や礼文島で起こった災害の復旧が重要との観点から、第4回非常災害対策本部を行いました。広島の中国地方整備局と運輸局、北海道開発局とTV会議を行い、土砂撤去や生活再建に向けての取り組み、2次災害防止等について打ち合わせをしました。
昨日は朝9時から、防災・減災をテーマとしたNHKの日曜討論に出演。土砂災害防止法の改正やハード、ソフトの対策について専門家と議論しました。終了後直ちに地元に駆けつけ、滝野川、田端、王子、神谷などの町会連合会や町会の防災訓練に参加しました。例年よりさらに緊迫感のある工夫された訓練になっていました。
異常な豪雨災害が頻発する中、住民の命を守るために全力を挙げます。