政治コラム 太田の政界ぶちかましCOLUMN
NO.121 大地震、大水害、高潮など大災害/「ステージが変わった」――腹の決まった防災対策を!
北海道胆振東部地震、台風21号によりお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞いを申し上げます。
 大災害が起きる大変な夏となった。6月には大阪北部地震、7月初めには西日本豪雨、9月初めに台風21号、そして9月6日には平成30年北海道胆振東部地震。いずれも近年見られなかった巨大災害、しかも様相が全く異なっている。それに加えて、連日35度を超える暑さで、熱中症から死亡する人まで出る厳しい自然の大変化。まさに災害列島日本であることを見せつけられた夏となった。徹底したハード、ソフトの対策と、今までとはステージを一段階アップした対策、予算組み、避難現場で逃げる"行動回路"を築き上げなければならない。
大災害が起きる大変な夏となった。6月には大阪北部地震、7月初めには西日本豪雨、9月初めに台風21号、そして9月6日には平成30年北海道胆振東部地震。いずれも近年見られなかった巨大災害、しかも様相が全く異なっている。それに加えて、連日35度を超える暑さで、熱中症から死亡する人まで出る厳しい自然の大変化。まさに災害列島日本であることを見せつけられた夏となった。徹底したハード、ソフトの対策と、今までとはステージを一段階アップした対策、予算組み、避難現場で逃げる"行動回路"を築き上げなければならない。
6日未明に発生した北海道胆振東部地震は、震度7を記録した。震度7は北海道では初めてのことで、厚真町では山体が崩れるような大規模な土砂崩れが発生、北海道全体が停電するという"ブラックアウト"が起き、札幌市内では液状化現象による被害が発生した。まずは人命救助、そして生活インフラの復旧、新千歳空港をはじめとしての交通網復旧に全力をあげる。大阪北部地震の様相とは違い、広大な地方における直下地震の恐ろしさ、地盤が、押されて上下にずれる「逆断層型」の直下地震の恐ろしさだ。
9月初頭の台風21号は、「強風」「高潮」。ルートは昭和36年の第2室戸台風と全くといっていいほど酷似し、強い勢力を維持したまま四国、関西を直撃した。強風は車も看板、トタン等をなぎ倒し、大阪府の民家・マンションの窓ガラスを軒並み破り、ビル風等の地形もあって、なんと瞬間風速は80m/sを記録した所もあったという。いよいよ"スーパータイフーン"も想定しなければならなくなった。高潮は通常より3mも上昇し、関西空港を水浸しとし、連絡橋にタンカーが激突、復旧は簡単ではない。東京湾でも、羽田空港や荒川・江戸川等の高潮被害は深刻に想定しなければならない。通常より3mも海面が上昇するというのはゼロメートル地帯が広がる東京下町では大変なことだ。
NO.120 豪雨の激甚化への対応強化を/マイ・タイムラインの行動回路急げ!
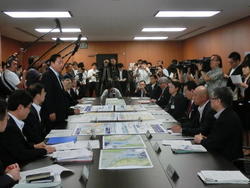 7月の西日本豪雨はきわめて厳しい大災害となった。「阪神淡路大震災、東日本大震災に次ぐ、平成の三大災害だという認識で対応すべきだ」――当初から私はそう言ってきた。現実に被害は甚大だ。8月2日現在、死者220人、行方不明者9人、住宅被害47074棟(うち全壊5074棟)、土砂災害1518件、河川堤防の決壊37件。きわめて厳しい状況のなか、捜索活動、救援活動が続き、行政・ボランティア等の力が猛暑のなかで発揮されている。一刻も早い復旧・生活再建に努めたい。
7月の西日本豪雨はきわめて厳しい大災害となった。「阪神淡路大震災、東日本大震災に次ぐ、平成の三大災害だという認識で対応すべきだ」――当初から私はそう言ってきた。現実に被害は甚大だ。8月2日現在、死者220人、行方不明者9人、住宅被害47074棟(うち全壊5074棟)、土砂災害1518件、河川堤防の決壊37件。きわめて厳しい状況のなか、捜索活動、救援活動が続き、行政・ボランティア等の力が猛暑のなかで発揮されている。一刻も早い復旧・生活再建に努めたい。
今回のような雨の降り方はかつてなかった。「特別警報」は、私が国交大臣の時、法改正によってつくった制度だが、長崎県から岐阜県まで西日本を縦断してなんと11府県に「特別警報」が出された。つくられた当時から「50年に1度、いまだ遭遇してないような豪雨」を「特別警報」としたが、1年に1回1県で起きる位が昨年までのことだ。今回はまさに広域、しかもどの府県も総雨量が400mmを超える豪雨となり、高知県馬路村では1800mm超、岐阜県郡上市では1200mm超を記録するすさまじい降り方だ。「雨の降り方が激甚化・集中化・局地化している」と警告してきた私だが、「線状降水帯」「バックビルディング現象」の広域化にも備えることが急務となってきた。
広島、岡山、愛媛でとくに被害が大きかった。しかも広島は「土砂崩れ」、岡山は「破堤しての大洪水(天井川であること、バックウォーター現象が起きたこと)」、愛媛では「土砂崩れ」と「洪水」が顕著だ。広島では4年前に土砂災害があった安佐北・安佐南の両区を中心に砂防堰堤の整備を急ピッチで進めているが、今回は別の地域で豪雨に見舞われた。流木等も含め「透過型砂防堰堤」の建設が土石流の危険地域では一刻も早く必要となる。倉敷市では天井川のために水がはけず、家屋1階には土砂が考えられないほど入り込んだ。ここでは何といっても河川の水位を下げること、堤防を強化することだ。日本の河川工学では力ずくでなく「水をなだめる」ことを総合的に行う。「堤防を強化する」「川底を掘る」「川幅を広げる」「遊水池等へ逃がす」「ダムで貯水する」等の組み合わせだ。これを各河川について"異常な降水時代"であることを認識して、積極的に乗り出すことだ。今のダッシュが肝要だ。
 今回、私がとくに主張しているキーワードは「タイムライン」と「マイ・タイムライン」だ。「タイムライン」は、避難の発令や仕方等を5日前、3日前、24時間前、6時間前・・・・・・と区切り、役所・警察・消防、学校・病院・老人ホーム等の福祉施設、鉄道・バス等の交通施設、企業・・・・・・などの関係者が事前に動くことを決めておくものだ。2012年10月、米ニューヨークにハリケーン・サンディーが襲いかかったが、これを採用したニューヨークは甚大な被害を免れた。それを教訓として私が国交大臣時代、まず東京の荒川からタイムラインを始めた。今や全国の国管理の河川109水系についてはこれができた。これからの問題は2つ。1つはタイムラインの参加機関を増やし厚くする。病院・介護施設・保育所などの弱者対応としてキメ細かいタイムラインの取り決めをすること。2つには、まだタイムラインが十分に出来ていない中山間地の中小河川の氾濫にどう備えるか(これは一気に増水し、氾濫し、流木が凶器となる)ということだ。その意味で、これを今年「タイムライン本格化の年」と定めて、各自治体と河川関係者が徹底してやることだ。
今回、私がとくに主張しているキーワードは「タイムライン」と「マイ・タイムライン」だ。「タイムライン」は、避難の発令や仕方等を5日前、3日前、24時間前、6時間前・・・・・・と区切り、役所・警察・消防、学校・病院・老人ホーム等の福祉施設、鉄道・バス等の交通施設、企業・・・・・・などの関係者が事前に動くことを決めておくものだ。2012年10月、米ニューヨークにハリケーン・サンディーが襲いかかったが、これを採用したニューヨークは甚大な被害を免れた。それを教訓として私が国交大臣時代、まず東京の荒川からタイムラインを始めた。今や全国の国管理の河川109水系についてはこれができた。これからの問題は2つ。1つはタイムラインの参加機関を増やし厚くする。病院・介護施設・保育所などの弱者対応としてキメ細かいタイムラインの取り決めをすること。2つには、まだタイムラインが十分に出来ていない中山間地の中小河川の氾濫にどう備えるか(これは一気に増水し、氾濫し、流木が凶器となる)ということだ。その意味で、これを今年「タイムライン本格化の年」と定めて、各自治体と河川関係者が徹底してやることだ。
NO.119-2 南海地震の経済被害1240兆円/防災・減災対策の強化緊要
6月18日、大阪府北部を震源とするマグニチュード6.1、最大震度6弱の地震が発生した。5名の死者、400名を超える負傷者が出る大きな災害だ。これまで社会インフラの耐震化を進めてきたが、今回、改めて大都市における地震対策の重要性が認識された。特に、ブロック塀の脆弱さ、交通網遮断による通勤・帰宅困難者問題、水道・ガスなどの生活インフラの補強、そして密集市街地の火災対策だ。私はこれまで、国土交通大臣の時も含め、常に「防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化の強化」を主張し推進してきた。学校や公共施設の耐震化、都市の防災対策、津波に対する防潮堤や津波タワーをはじめ、あらゆる対策を進めてきたが、今回は改めて大都市地震対策の緊要性を突きつけられたと言えよう。
同じ6月、土木学会が衝撃的な報告書を出した。「『国難』をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書(H30.6.7)」だ。「国難」をもたらす巨大災害の被害推計で、南海トラフ地震で20年間の経済被害を累計すると1,240兆円に及ぶ、との発表に多くの人が驚いたと思う。この報告書の冒頭部分では、1755年ポルトガルの首都を襲った「リスボン大地震」により国力が衰退し、そしてポルトガルの時代が終わった史実が記されている。日本は今、巨大災害に備えておかなければならない。日本がつぶれかねない。そういった危機感あふれる報告であった。
報告書は、「国難」と呼びうる致命的事態を回避し、巨大災害に遭遇してもその被害を回復可能な範囲にとどめうる対策、すなわち国土のレジリエンス確保方策を示そうとするものだ。対象災害は、首都直下地震、南海トラフ地震、三大湾の巨大高潮、三大都市圏の巨大洪水。その災害を軽減するための対策として、主に道路、河川、港湾、海岸のインフラ整備が挙げられている。今回の報告書の特徴は、「被害額として長期的な経済被害を推計」している点だ。
NO.119 出水期、重要な水循環施策/洪水、渇水への備え万全に
 いよいよ6月、出水期を迎える。昨今は、雨の降り方がおかしくなっている。水害等も局所化、集中化、激甚化してきたが、その傾向はますます強まっている。平成26年7月に水循環基本法が成立し、私は初代の水循環政策担当大臣を務めた。水循環はきわめて重要な課題であるが、日常的にはそれを忘れてしまっているのが現状ではないか。集中豪雨対策としては、タイムラインによる備えや堤防、ダム、遊水池の整備等を進めている。常に備えていかないといけない。
いよいよ6月、出水期を迎える。昨今は、雨の降り方がおかしくなっている。水害等も局所化、集中化、激甚化してきたが、その傾向はますます強まっている。平成26年7月に水循環基本法が成立し、私は初代の水循環政策担当大臣を務めた。水循環はきわめて重要な課題であるが、日常的にはそれを忘れてしまっているのが現状ではないか。集中豪雨対策としては、タイムラインによる備えや堤防、ダム、遊水池の整備等を進めている。常に備えていかないといけない。
もう一つの大切なことは渇水である。集中豪雨の陰に隠れ、渇水が忘れられている。これへの備えを国としてしっかりやっていかなければいけない。
我が国では、高度経済成長期以降、危機的な渇水が何度も発生し、国民生活・経済活動に多大な影響・被害を生じさせてきた。例えば、昭和36年から39年にかけての"オリンピック渇水"や昭和53年の福岡渇水、平成に入ってからも全国的に渇水が発生している。
こうした水需要の急増に伴う深刻な水不足に対し、安定した水供給の確保を図るため、ダムを整備したり、霞ヶ浦等の湖沼において水資源開発が計画的に進められてきた。しかし、近年の異常少雨の増加や降水量の変動幅の拡大により、毎年のように取水制限が実施されるなど全国的に渇水が発生している。四国の早明浦ダムでは毎年のように渇水が発生しているし、私のふるさと豊川上流にある宇蓮ダム、大島ダムでもダムが完成した平成14年以降、4年に1回の頻度で渇水が発生している。さらに記憶に新しいところでは、平成28年に利根川で、平成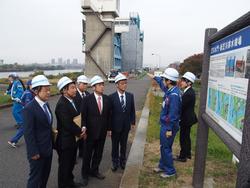 29年には荒川と、首都圏では2年続けて渇水が発生した。平成28年は利根川の上流で降雪量が観測開始以来最小で雪解けも1か月早くなったこと、5月の雨量が平年の半分以下であったことから、ダムの貯水量が急激に減少し、利根川本川では過去最長となる79日間にわたって取水制限を実施するに至った。
29年には荒川と、首都圏では2年続けて渇水が発生した。平成28年は利根川の上流で降雪量が観測開始以来最小で雪解けも1か月早くなったこと、5月の雨量が平年の半分以下であったことから、ダムの貯水量が急激に減少し、利根川本川では過去最長となる79日間にわたって取水制限を実施するに至った。
NO.118 「AI・IoT時代に備えダッシュ/混在の時代」「危機管理」「人間力」の視点を
 日本は現在、避けがたい3つのインパクトにさらされている。対応のスタートダッシュは今だ。私が「今年は国家的行事も少ない。仕事をする年だ」と年頭から言っているのはそう考えているからだ。1つは人口減少・少子高齢化の急な坂にいよいよ登ること。2つには、AI・IoT・IT・BT(バイオテクノロジー)・ロボットのデジタル革命の破壊力。3つにはエネルギー制約とエネルギー革命、地球温暖化対策だ。「時間軸を持った政治を」と私が主張しているのはそうした危機感、逆に言えば「チャンスを逃すな」「今やれば間に合う」と考えるからだ。
日本は現在、避けがたい3つのインパクトにさらされている。対応のスタートダッシュは今だ。私が「今年は国家的行事も少ない。仕事をする年だ」と年頭から言っているのはそう考えているからだ。1つは人口減少・少子高齢化の急な坂にいよいよ登ること。2つには、AI・IoT・IT・BT(バイオテクノロジー)・ロボットのデジタル革命の破壊力。3つにはエネルギー制約とエネルギー革命、地球温暖化対策だ。「時間軸を持った政治を」と私が主張しているのはそうした危機感、逆に言えば「チャンスを逃すな」「今やれば間に合う」と考えるからだ。
AI・IoT・IT・BT・ロボットのインパクトを思うと考えなくてはならないことが幾つもある。第一人者の坂村健教授は著作「IoTとは何か」のなかで「今までの日本のICT戦略は、技術で始まり技術で終わることが多い。技術革新から社会革新へ。オープン・イノベーションだ」という。「人工知能と経済の未来」(井上智洋著)では、「第四次産業革命(汎用AI・全脳アーキテクチャ)は、2030年頃から助走を始めて2045年には本格化。2030年頃を境にして、それ以前は"特化型AIの時代"、それ以降は"汎用AIの時代"となる」という。また「文系人間のための『AI』論」(高橋透著)では、「その後人間や社会はどうなるか。AIと共存し、やがて合体して、人間を越えるものになる。ハイパーAIと融合するポスト・ヒューマンだ」と人間存在の根源的問題を突きつける。最近、話題となっているダン・ブラウンの小説「オリジン」でも「進化論と人工知能、科学か宗教か」がメインテーマとなっている。
大事なことは、危機を煽ることでも、夢を語ることでもない。「今やるべきこと」は、今年のダッシュをどうするか、時間軸を常に考えていくことだと思う。































