政治コラム 太田の政界ぶちかましCOLUMN
NO.136 安全・安心の勢いのある国づくり!/東京オリ・パラ後の経済・社会へダッシュ
新しい年がスタートした。昨年は「令和」「ラグビー」「台風19号」の年であったと思う。「令和」は国民の祝賀のなかで始まった。「ラグビー」は身体が小さい日本だが、鍛錬と結束があれば勝利を得ることができるとの自信と感動を与えてくれた。スポーツの力は大きい。「台風19号」――15号とともに19号は甚大な被害を与えた。大雨特別警報はなんと13都県に及んだ。災害が多い年でしたね、ではない。今回、荒川上流域の降雨は3日間で446ミリと戦後最大を記録した。しかし、重要なことは50年に1回の大雨ということではなく、気象の大変化を考えるとこうした豪雨は5年に1回程度は覚悟しなければならないということだ。レベルの変わった頻発化・激甚化・広域化する災害には、レベルを変えた対策が不可欠だ。
 今年は何といっても東京オリンピック・パラリンピックだ。一時心配された新国立競技場も見事に出来上がった。諸整備も進んでいる。私の地元である北区のナショナル・トレーニングセンターも拡充され、パラリンピックのトレーニングのできる新施設も昨年完成した。パラリンピックの意義も大きい。今回のパラリンピックのメッセージは、無理だと諦める「Impossible(無理)」ではなく、「I'm Possible(私はできる)」となっている。ImpossibleではなくPossibleで頑張ろうということだ。2020年代の初頭に当たって、全てに通じる大事なメッセージだと思う。
今年は何といっても東京オリンピック・パラリンピックだ。一時心配された新国立競技場も見事に出来上がった。諸整備も進んでいる。私の地元である北区のナショナル・トレーニングセンターも拡充され、パラリンピックのトレーニングのできる新施設も昨年完成した。パラリンピックの意義も大きい。今回のパラリンピックのメッセージは、無理だと諦める「Impossible(無理)」ではなく、「I'm Possible(私はできる)」となっている。ImpossibleではなくPossibleで頑張ろうということだ。2020年代の初頭に当たって、全てに通じる大事なメッセージだと思う。
NO.135 平和、福祉、防災で命を守る!/結党55年、連立20年の公明党
今年は10月に自公連立20年、11月には公明党結党55年の節目を迎えた。歴史を思い起こすと感慨深いものがある。
 公明党は1964年(昭和39年)11月17日に結成された。この年は、私が故郷を出て大学に入学した年で、10月1日には新幹線が走り、10月10日には東京オリンピックが開幕した。戦後の復興を世界に向けて発進した年でもあり、高度成長の躍進が全ての面で展開された年だ。公明党結成大会では「日本の柱 公明党」「大衆福祉の公明党」のスローガンが壇上の左右に大きく掲げられた。その2年前、公明党の前身である公明政治連盟の第1回全国大会があり、「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆のなかに死んでいく」との不変の精神が発表となっており、立党精神、党是となって今日に至っている。当時の政治は自民、社会の二大政党時代。「庶民・大衆の声を代弁する政党・政治家はいないのか」との声を受けて誕生したのが公明党であった。
公明党は1964年(昭和39年)11月17日に結成された。この年は、私が故郷を出て大学に入学した年で、10月1日には新幹線が走り、10月10日には東京オリンピックが開幕した。戦後の復興を世界に向けて発進した年でもあり、高度成長の躍進が全ての面で展開された年だ。公明党結成大会では「日本の柱 公明党」「大衆福祉の公明党」のスローガンが壇上の左右に大きく掲げられた。その2年前、公明党の前身である公明政治連盟の第1回全国大会があり、「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆のなかに死んでいく」との不変の精神が発表となっており、立党精神、党是となって今日に至っている。当時の政治は自民、社会の二大政党時代。「庶民・大衆の声を代弁する政党・政治家はいないのか」との声を受けて誕生したのが公明党であった。
「大衆福祉の公明党」――。昭和40年代には児童手当が実現した。その後、白内障の眼内レンズ手術の保険適用が実現した。年金の充実にも奔走した。難病支援、ハンセン病やC型肝炎やさい帯血にも力を注いだ。そして今や、「全世代型社会保障」が国の柱となった。今年10月から3歳から5歳までの全ての子どもへの「幼児教育の無償化」が実現した。小中学校の普通教育無償化以来、70年ぶりの大改革だ。また、来年4月からは、公立だけでなく、「私立高校の実質無償化」ができる。さらに無利子奨学金や給付型奨学金も充実させ、加えて生活が困窮しているために大学など高等教育を断念することがないよう「高等教育の一部無償化」が実現となる。「3つの無償化」という画期的な施策の実現だ。
NO.134 新たなステージの防災対策を/ハード、ソフトの整備が急務!
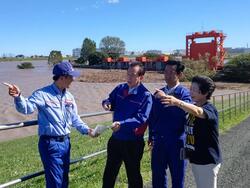 台風19号は東日本全域に大被害をもたらした。死者86名、行方不明8名、家屋の倒壊5802棟、浸水した家屋は、床上浸水29,383棟を含め、じつに62,785棟に及ぶ(10月24日現在)。堤防の決壊は7県で139か所にもなる。これだけ広域にわたって被害を被った例は今までにないことだ。私の地元である荒川も水位が上がり、東京北区の水位観測所では、戦後でいえばキャサリン台風、狩野川台風に次いで3番目となる7.17mを記録し、隅田川を守る岩淵水門が12年ぶりに閉じた。日本を取り巻く気象は大きく変わった。50年に1回、100年に1回の大水害などと言っている場合ではない。新たなステージに入ったと見るべきだ。それに対応できるハード、ソフト両面にわたっての対策強化に全力を上げ、「安全・安心の国土づくり」にダッシュしないと大変なことになる。「脆弱国土を誰が守るか」――首都直下地震、東海・東南海・南海地震も含め、懸命な対策が不可欠だと心から思う。
台風19号は東日本全域に大被害をもたらした。死者86名、行方不明8名、家屋の倒壊5802棟、浸水した家屋は、床上浸水29,383棟を含め、じつに62,785棟に及ぶ(10月24日現在)。堤防の決壊は7県で139か所にもなる。これだけ広域にわたって被害を被った例は今までにないことだ。私の地元である荒川も水位が上がり、東京北区の水位観測所では、戦後でいえばキャサリン台風、狩野川台風に次いで3番目となる7.17mを記録し、隅田川を守る岩淵水門が12年ぶりに閉じた。日本を取り巻く気象は大きく変わった。50年に1回、100年に1回の大水害などと言っている場合ではない。新たなステージに入ったと見るべきだ。それに対応できるハード、ソフト両面にわたっての対策強化に全力を上げ、「安全・安心の国土づくり」にダッシュしないと大変なことになる。「脆弱国土を誰が守るか」――首都直下地震、東海・東南海・南海地震も含め、懸命な対策が不可欠だと心から思う。
今回の台風19号で考えなくてはならない第一は、その規模だ。明らかに、気象が従来とは異なり、海域によっては海水温が2~3度上昇、温暖化の進行が背景にある。10月12日、13日で大雨特別警報がなんと13都県に出た。この特別警報は、私が国土交通大臣であった時に、「注意報や警報では弱い。本当にいまだかつてない大雨だから、逃げないと危ない」との意識の下に、新しくつくったものだ。わずか5年前、当時は特別警報は1年に1~2回、それも複数の県にまたがる大雨というよりも、単一の県でおさまるほどの大雨がほとんどであった。「降雨が局地化、集中化、激甚化している」ということを背景にしてきたものだ。それが昨年の西日本豪雨では、岡山・広島・愛媛などの11府県と広域化した。広域化、激甚化だ。今回、なんと特別警報は東日本と東北の13都県に及んだ。
NO.133 深刻化した停電・断水・生活災害/無電柱化の強力な推進を!
 9月9日未明、台風15号は強い勢力を持ったまま首都圏を襲い、甚大な被害をもたらした。特に千葉県では、負傷者は重傷6人、軽傷61人、住宅被害は全壊41棟、半壊424棟、一部損壊9544棟(9月20日時点)で、ブルーシートでの応急処置等が行われた。なかでも深刻だったのは停電。経済産業省の推計では2000本の電柱が倒壊したという。それに伴っての断水も続いた。昨年の北海道胆振東部地震ではブラックアウトが衝撃を与えたが、今回の長期に渡った停電問題を踏まえ、防災・減災の最重要事項として対策に踏み出さなければならない。災害時にはがけ崩れ、倒木、飛散した屋根等によって電柱がなぎ倒されて停電を起こす。対策は簡単ではないが、電線の地中化、無電柱化の推進は、大地震・大災害への対応として重要なことだ。対策を急ぐ必要がある。
9月9日未明、台風15号は強い勢力を持ったまま首都圏を襲い、甚大な被害をもたらした。特に千葉県では、負傷者は重傷6人、軽傷61人、住宅被害は全壊41棟、半壊424棟、一部損壊9544棟(9月20日時点)で、ブルーシートでの応急処置等が行われた。なかでも深刻だったのは停電。経済産業省の推計では2000本の電柱が倒壊したという。それに伴っての断水も続いた。昨年の北海道胆振東部地震ではブラックアウトが衝撃を与えたが、今回の長期に渡った停電問題を踏まえ、防災・減災の最重要事項として対策に踏み出さなければならない。災害時にはがけ崩れ、倒木、飛散した屋根等によって電柱がなぎ倒されて停電を起こす。対策は簡単ではないが、電線の地中化、無電柱化の推進は、大地震・大災害への対応として重要なことだ。対策を急ぐ必要がある。
無電柱化は「防災」「交通安全」「景観」の観点から重要だ。この重要性から、2016年に「無電柱化の推進に関する法律」が成立した。法律では、国や事業者等の責務を定め、無電柱化施策を総合的・計画的・迅速に推進することを目標としている。それに基づき、昨年4月には2018年から2020年の3年間で1400kmの無電柱化を目標とする「無電柱化推進計画」を国土交通大臣が決定した。加えて、昨年の台風21号で大阪府を中心に1700本以上の電柱が倒壊したことを踏まえ、3カ年の緊急対策として、既往最大風速が一定以上の特に対策が必要な区間1000kmの無電柱化に着手することとなっている。
NO.132 時代の激変と政治のリーダーシップ/時間軸をもち先手を打つ政治を!
時代の進展は速い。社会の変化は激しい。だからこそ政治のリーダーシップ、政治家の構想力が不可欠だ。官僚機構に乗っかり、利害の調整に力を注ぐ時代ではない。「時間軸をもった政治」が求められるゆえんだ。
 「2025年には団塊の世代が75歳以上になり、認知症700万人、全国の空家が1000万戸になる」――大変なことだ。いよいよラグビーワールドカップが始まり、即位の礼が行われると、明年2020年の東京オリンピック・パラリンピックへ一直線となる。勢いをつけることは重要だが、2025年まで6年、2030年までわずか11年しかない。人口減少・少子高齢社会、AI・IoT・ロボットの急進展という構造変化にどうダッシュするか。喫緊の課題といってよい。
「2025年には団塊の世代が75歳以上になり、認知症700万人、全国の空家が1000万戸になる」――大変なことだ。いよいよラグビーワールドカップが始まり、即位の礼が行われると、明年2020年の東京オリンピック・パラリンピックへ一直線となる。勢いをつけることは重要だが、2025年まで6年、2030年までわずか11年しかない。人口減少・少子高齢社会、AI・IoT・ロボットの急進展という構造変化にどうダッシュするか。喫緊の課題といってよい。
宮部みゆきの近著「さよならの儀式」は面白いが恐ろしい。短篇集だが、「被虐待児とその親を保護・育成するために"マザー法"なるものが成立し、親子のつながりに国が介入して遮断する」「汎用作業ロボットが各家庭に行き渡り、家族のようになる。廃棄する時の別れる辛さ、廃棄業者のあり方をどうするか」「いつの間にか街には防犯カメラ等が増え、監視されているが、どうもそのカメラ自体にモノが侵入し、意識的に操作が行われる」「ネット上にフェイクニュースがあふれ、知らないうちに自分が教祖のようになっていたというフェイクの暴走」「人間と人造擬体とが共存する村」・・・・・・。全くのSFとは思えなくなっているから恐ろしいのだ。同じく東野圭吾の新作「希望の糸」も「人工授精、卵子提供の取り違えが、殺人事件にまで発展してしまう"運命に操られる家族"」を描いている。































