政治コラム 太田の政界ぶちかましCOLUMN
NO.171 首都直下地震への対策急務/「パニック」「火災」の実践訓練を
トルコでこの2月、死者5万人を超える大地震が発生したが、日本では首都直下地震、南海トラフ地震を警戒しなければならない。首都直下地震は「30年以内に70%の確率で発生する」と予測されている。最大の被害となるのは、M7.3、最大震度7の南部直下地震。被害想定は、建物の倒壊・焼失が最大61万棟、死者は約2.3万人に及ぶ。関東大震災から100年の今年こそ、地震対策を加速しなければならない。
 まず、防災・減災――。首都直下地震を考える場合、最重要なのは建物の「耐震・免震」だ。トルコでは、建物の倒壊、なかでもビルが瞬時に崩れ落ち人命を奪った。パンケーキ・クラッシュともいわれる。トルコでは1999年の地震を契機として新たな耐震基準を設定したが、耐震を施さない建物がきわめて多かったという。しかしあまり報道されていないが、免震を施した病院などは全て崩壊を免れたことが報告されている。日本の場合は1981年に新しい耐震基準を設定、現在は東京の場合92%が基準を満たしている。既存不適格は8%ということになる。100%をめざして更に努力が必要だ。建物とともに、「高速道路」「橋梁」をはじめとするインフラの耐震化についても、再度徹底することを提唱したい。首都圏は、軟弱地盤の地域も多く、更なる耐震強化が必要だ。
まず、防災・減災――。首都直下地震を考える場合、最重要なのは建物の「耐震・免震」だ。トルコでは、建物の倒壊、なかでもビルが瞬時に崩れ落ち人命を奪った。パンケーキ・クラッシュともいわれる。トルコでは1999年の地震を契機として新たな耐震基準を設定したが、耐震を施さない建物がきわめて多かったという。しかしあまり報道されていないが、免震を施した病院などは全て崩壊を免れたことが報告されている。日本の場合は1981年に新しい耐震基準を設定、現在は東京の場合92%が基準を満たしている。既存不適格は8%ということになる。100%をめざして更に努力が必要だ。建物とともに、「高速道路」「橋梁」をはじめとするインフラの耐震化についても、再度徹底することを提唱したい。首都圏は、軟弱地盤の地域も多く、更なる耐震強化が必要だ。
そして「首都直下」では、「火災」が問題となる。東京での木造密集市街地対策は、まだ道半ばである。新たな街づくり、再開発事業として、時間はかかるが、加速しなければならない。加えて、地域の初期消火体制など、自治体、地域・消防団などの協力を得て、日頃からの実践的訓練を特に留意すべきだ。もう一つ、注意・徹底が重要なのは、高層ビルにおける「長周期地震動」対策だ。 3·11東日本大震災の時、東京の高層ビルが大きく揺れ、これが長周期地震動として新たな課題となった。なんと大阪でも高層ビルが大きく揺れたという。これは、各ビル内の備品を固定するなど、今すぐにでも可能なことがある。今年中に行動に移したい。
NO.170 「2024物流危機」の打開を!/ドライバー不足の背景に構造的要因
2025年問題、2040年問題というのは、人口減少・少子高齢社会の構造変化から指摘される問題だが、最近言われているのが2024年問題だ。2025年には団塊の世代が全て75歳以上になり、全国の空き家が900万戸、認知症の人が700万人を超える。そして高齢者人口が2040年頃まで増え続ける一方、社会を支えるべき労働力人口が毎年60万~80万人という水準で減っていく。しかも2040年以降、ピークに達した高齢者人口が微減しても、労働力人口も減少していく。この人口構造の変化とともに、AI・DX社会の急進展、自動運転やEVへの激変、エネルギー・地球環境問題の深刻化などが加わる。今こそ2040年問題への備えにダッシュしなければならないということだ。
 2024年問題とは、2019年施行の「働き方改革関連法」に基づき、建設・運送業などが5年の猶予期間を終え、いよいよ来年4月、時間外労働について上限規制が適用され、「建設できない」「輸送できない」などの事態が発生する深刻な危惧だ。職人不足、ドライバー不足は、建設業・運送業の業務遂行に深刻な打撃を与えるゆえに、広範な支援体制の構築が不可欠だ。とくに「2024年物流危機」だ。運転業務の時間外労働については、年960時間(休日労働含まず)の上限規制が適用される。あわせて、厚生労働省がトラックドライバーの拘束時間を定めた「改善基準告示」により拘束時間、運転時間等が強化される。拘束時間(労働時間+休憩時間)が、1日当たり原則13時間以内、最大15時間以内、長距離運行は週2回まで16時間。1か月当たりでは原則284時間以内、年3300時間以内となる。このまま対策をとらないと、2024年には輸送能力が14%減、2030年には34%減との試算もあり、物流に与える影響は大変なものになる。働き方改革も大事、しかし物流も大事というなかでの2024年問題というわけだ。
2024年問題とは、2019年施行の「働き方改革関連法」に基づき、建設・運送業などが5年の猶予期間を終え、いよいよ来年4月、時間外労働について上限規制が適用され、「建設できない」「輸送できない」などの事態が発生する深刻な危惧だ。職人不足、ドライバー不足は、建設業・運送業の業務遂行に深刻な打撃を与えるゆえに、広範な支援体制の構築が不可欠だ。とくに「2024年物流危機」だ。運転業務の時間外労働については、年960時間(休日労働含まず)の上限規制が適用される。あわせて、厚生労働省がトラックドライバーの拘束時間を定めた「改善基準告示」により拘束時間、運転時間等が強化される。拘束時間(労働時間+休憩時間)が、1日当たり原則13時間以内、最大15時間以内、長距離運行は週2回まで16時間。1か月当たりでは原則284時間以内、年3300時間以内となる。このまま対策をとらないと、2024年には輸送能力が14%減、2030年には34%減との試算もあり、物流に与える影響は大変なものになる。働き方改革も大事、しかし物流も大事というなかでの2024年問題というわけだ。
NO.169 切れ目ない子育て支援策を!/待ったなしの少子化日本
少子化が加速している。昨年の出生数は、統計上初めて80万人を割る見通しだという。コロナ禍で婚姻数も戦後最少、妊娠中の感染の不安があり、産み控えもあったようだが、深刻だ。合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子どもの数)が、「1.57ショック」といわれたのが1989年。「ひのえうま」という特殊要因で過去最低であった1966年の1.58を下回った。2005年には過去最低の1.26となり、様々な手を打ったが依然として低水準のまま、2021年は1.30という状態だ。「失われた第三次ベビーブーム世代(戦後のベビーブーム世代の孫の世代が形成されなかった)」「人口減少は、いったん動き出すと止まらない」「毎年、政令指定都市クラスの人口が消えていく」「2050年、日本全国38万㎢を1㎢のメッシュで切ると、63%の地域で人口が半分以下、そのうち19%は無人になる」「地方ではすでに防災や祭り等の担い手がいない」・・・・・・。この急激な人口減少は国土形成、都市・街づくりにも、経済活動にも深刻な状況をもたらし、社会保障の持続可能性を根底から脅かすことになる。
 日本の難しさは、人口減少をもたらす出生率の減少、高齢者数の増加、そして社会の支え手である働く世代の減少という、それぞれ要因の異なる3つの課題の同時進行にある。自公政権のこの10年、「全世代型社会保障」「働き方改革」「地方創生」に力を入れたのもそこにある。保育無償化、高校授業料の無償化、大学奨学金の拡充、認知症やがん対策、就職氷河期世代への支援、育児休業制度の拡充など実現・拡充したものは多い。しかし、少子化対策としての結果を出すに至らなかった。
日本の難しさは、人口減少をもたらす出生率の減少、高齢者数の増加、そして社会の支え手である働く世代の減少という、それぞれ要因の異なる3つの課題の同時進行にある。自公政権のこの10年、「全世代型社会保障」「働き方改革」「地方創生」に力を入れたのもそこにある。保育無償化、高校授業料の無償化、大学奨学金の拡充、認知症やがん対策、就職氷河期世代への支援、育児休業制度の拡充など実現・拡充したものは多い。しかし、少子化対策としての結果を出すに至らなかった。
「次元の異なる少子化対策」――。通常国会が始まり、岸田首相が最大の柱としたのが少子化対策、子ども・子育て支援の強化だ。その柱として、①児童手当などの経済的支援 ②幼児教育や保育サービスなどの支援 ③働き方改革の推進――を上げている。「子ども家庭庁」が4月に発足するが、それまでに具体策を整理し、6月の「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)の閣議決定に向け、子ども関連予算の倍増に向けた道筋を提示する。公明党が昨年11月にまとめた「子育て応援トータルプラン」が反映されることは間違いないと思われる。
NO.168 必要な安保、人口減少への国民理解/世界調査から見る日本人の考え方
「民の憂い募りて国滅ぶ」「民の欲する所 天必ず之に従う」という中国古典の言葉を政治活動のなかで大事にしてきた。「現場の変化を察知するセンサーを持て」ということも心掛けてきた。民意を察知することの大事さ、庶民の現場感覚の重要さだ。ところが先日、「仮に戦争が起こる事態になったら、自分の国のために戦いますか」との世界価値観調査の質問に、「はい」と答えた人は、2019年の調査時点で、日本は13%と際立って低く、77か国中最下位だったという報告に接した。しかも見逃してはならないのは、「わからない」という回答が38%もあり、これは国際比較で極めて多いという事実である(「いいえ」は50%)。日本人の意識には、あの昭和の戦争の戦禍から反戦意識がきわめて強い。国際的に見ても、日本人はかなり強いレベルで戦争を忌避している。そして戦後長らく戦争のない世界に住み、考えたことがない、あるいは判断がつかない人が多いことが現れている。
 この調査は、世界各地の個人を対象に、1981年以降おおむね5年おきに実施されている世界最大規模の意識調査。世界120もの国や地域で、同じ質問をする形でこの40年間で7回、世界の人々の「世界価値観調査」として実施してきた。調査項目は290に及び、内容は生活意識や労働意識、ジェンダー意識、国際社会意識など多岐に渡っている。時系列データの蓄積が特徴であり、日本では電通総研が日本代表として参画している。そして、二つの大きな価値観シフトが世界各国で確認されている。一つは「伝統的価値観」から「世俗的価値観」へのシフト、もう一つは「生存重視の価値観」から「選択の自由と自律性に重きを置く自己表現重視の価値観」へのシフトだ。調査結果を見ると、世界的に、「格差と分断」が生じていることや、結婚や家族、ジェンダーと性的志向に関する価値観に劇的な変化があり、環境問題意識も高まっている。日本でもこのことは実感するところだ。日本で特徴的な傾向は、仕事への意識が変化している。「仕事」について「重要」「やや重要」の割合は81.3%で、 77か国中で71位、「生活において仕事よりも余暇時間を重視する傾向」が見られ、「仕事優先」という価値観が弱くなっているようだ。「ナショナルプライド」や「権威の尊重」なども日本は低い。「権威や権力が尊重されることは良いこと」との回答はわずか1.9%で77か国中で77位の最下位だ。政治への関心も低く、とくに政治行動は極めて低い。
この調査は、世界各地の個人を対象に、1981年以降おおむね5年おきに実施されている世界最大規模の意識調査。世界120もの国や地域で、同じ質問をする形でこの40年間で7回、世界の人々の「世界価値観調査」として実施してきた。調査項目は290に及び、内容は生活意識や労働意識、ジェンダー意識、国際社会意識など多岐に渡っている。時系列データの蓄積が特徴であり、日本では電通総研が日本代表として参画している。そして、二つの大きな価値観シフトが世界各国で確認されている。一つは「伝統的価値観」から「世俗的価値観」へのシフト、もう一つは「生存重視の価値観」から「選択の自由と自律性に重きを置く自己表現重視の価値観」へのシフトだ。調査結果を見ると、世界的に、「格差と分断」が生じていることや、結婚や家族、ジェンダーと性的志向に関する価値観に劇的な変化があり、環境問題意識も高まっている。日本でもこのことは実感するところだ。日本で特徴的な傾向は、仕事への意識が変化している。「仕事」について「重要」「やや重要」の割合は81.3%で、 77か国中で71位、「生活において仕事よりも余暇時間を重視する傾向」が見られ、「仕事優先」という価値観が弱くなっているようだ。「ナショナルプライド」や「権威の尊重」なども日本は低い。「権威や権力が尊重されることは良いこと」との回答はわずか1.9%で77か国中で77位の最下位だ。政治への関心も低く、とくに政治行動は極めて低い。
NO.167 円安に潜む日本のデフレ構造/観光振興も大切な起爆力
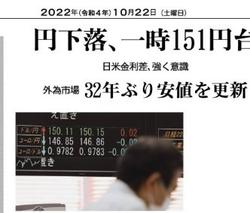 円安が続いている。10月20日の東京・外国為替市場で、円相場が32年ぶりに1ドル=150円を超えた。今年初めに1ドル=115円台であったから急激な下落だ。政府・日銀は円買いの介入を複数回実施したが、円安傾向は続いている。要因は明らかだ。日米の金利差、金融政策の差異によるものだ。米国は、消費者物価指数(CPI)の上昇率が8%以上で推移し、インフレの抑え込みが最優先課題であり、今年3月のゼロ金利解除以降、利上げを繰り返し、政策金利は、あのリーマン・ショック直前以来の3%台に達する。昨年の秋以降のポスト・コロナの経済インフレ、そしてウクライナ情勢、米中間選挙も関係する。一方、日本は景気を下支えするためにマイナス金利政策を続けている。物価上昇で大変だというが、根本的には景気回復によるものではない。日本は世界に類例のない「長期」で「1%程度の緩やかなデフレ」の構造から脱していない。アベノミクスで完全なデフレ脱却寸前のところで、19年の消費税上げ、そして2年半にわたるコロナで景気・経済はデフレ構造から脱せず、金融緩和を続けざるをえないのだ。
円安が続いている。10月20日の東京・外国為替市場で、円相場が32年ぶりに1ドル=150円を超えた。今年初めに1ドル=115円台であったから急激な下落だ。政府・日銀は円買いの介入を複数回実施したが、円安傾向は続いている。要因は明らかだ。日米の金利差、金融政策の差異によるものだ。米国は、消費者物価指数(CPI)の上昇率が8%以上で推移し、インフレの抑え込みが最優先課題であり、今年3月のゼロ金利解除以降、利上げを繰り返し、政策金利は、あのリーマン・ショック直前以来の3%台に達する。昨年の秋以降のポスト・コロナの経済インフレ、そしてウクライナ情勢、米中間選挙も関係する。一方、日本は景気を下支えするためにマイナス金利政策を続けている。物価上昇で大変だというが、根本的には景気回復によるものではない。日本は世界に類例のない「長期」で「1%程度の緩やかなデフレ」の構造から脱していない。アベノミクスで完全なデフレ脱却寸前のところで、19年の消費税上げ、そして2年半にわたるコロナで景気・経済はデフレ構造から脱せず、金融緩和を続けざるをえないのだ。
急激な円安は日本の物価にも影響を及ぼしている。総務省が10月21日発表した9月の全国消費者物価指数(2020年=100)は、生鮮食品を除く総合で102.9%となって前年同月比3.0%上昇した。消費税上げの時を除くと、1991年8月以来、実に31年ぶりの3%台だ。昨年来の資源高騰とこの半年の円安の影響は明らかで、エネルギー、電気・ガス、食料などの生活必需品の値上がりが目立ち、家計の負担は増している。政府はガソリン等の燃料と小麦等の価格の低減に手を打ち、今は電気・ガスの低減を決めている。それは当然の政策である。しかし、その根源は欧米を中心とした世界的なインフレと日米の金融政策の差異による円安、加えてロシアのウクライナ侵略にあるがゆえに、眼前の対策とともに、その世界と日本の構造自体を凝視することが重要だ。
さらに日本の「エネルギー」「食糧」事情を考えれば、エネルギーの約90%、食糧の60%以上を輸入に依存している。この脆弱性が「長期の緩やかなデフレ」と重なり、為替水準に反映している。また貿易収支の赤字がこのところ顕著だ。技術力による魅力ある商品の輸出で稼いだ日本の底力が低下していることも「円安」として現われているのではないか。「長期の緩やかなデフレ」「エネルギー・食糧自給の脆弱性」「産業の底力の低下」という根本問題が「円安」の下に横たわっている。































